プロダクトの未来をつくる仕事──UXリサーチャーの魅力と可能性
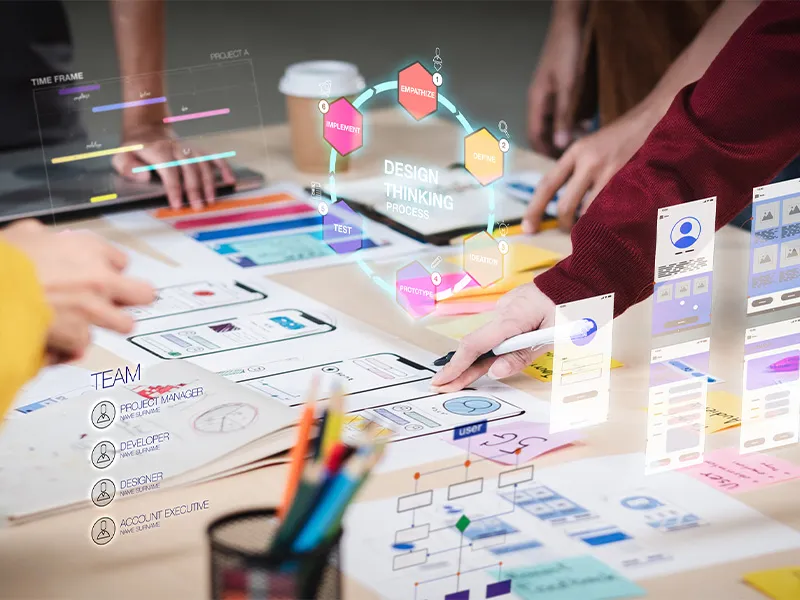
「もっと使いやすいサービスはないの?」
「どうしてこのアプリはこんなに分かりづらいの?」
そんなユーザーの“もやもや”に真正面から向き合い、プロダクトを根本から改善へ導く――それがUXリサーチャーという仕事です。近年、このUXリサーチャーに注目が集まり、転職市場でも“熱い職種”として急浮上しています。2024年のデータでは、UX関連職の求人数は前年に比べて約25%増加しており、特にリサーチ専門人材へのニーズが急速に拡大しています。
プロダクトの成功が“使いやすさ”や“ユーザーの満足度”に大きく左右される今、UXリサーチャーは企業にとって不可欠な存在となりつつあります。
なぜ今、UXリサーチャーが求められているのか?
デジタル化の加速により、企業は従来のプロダクト志向からユーザー志向へと舵を切りつつあります。使いやすさや満足度がプロダクトの成功を左右する現在、ユーザーの声を丁寧に拾い上げるUXリサーチャーの存在は、企業にとって極めて戦略的な役割を果たしています。
UXリサーチャーは、ユーザーインタビュー、アンケート調査、ユーザビリティテスト、行動観察などの手法を用いて、ユーザーが何に困っているのか、何を求めているのかを明らかにします。そして、その結果をもとに、デザイナーやエンジニア、プロダクトマネージャーと連携しながら、製品やサービスの改善へとつなげていきます。まさに「プロダクトとユーザーをつなぐ架け橋」と言える存在なのです。
UXリサーチャーに求められるスキルとは?
UXリサーチャーには、定量・定性の両面からユーザーを理解するスキルが求められます。たとえば、Googleフォームなどを活用したアンケート設計や、100人以上の回答データから傾向を抽出する統計的分析の力が必要です。同時に、インタビューや行動観察といった定性的手法を用いて、数字には表れないユーザーの感情や価値観を読み取る力も求められます。
加えて、調査結果をチームに分かりやすく伝えるための資料作成能力や、異なる職種のメンバーと協働するコミュニケーションスキル、会議やプロジェクトを円滑に進行させるファシリテーション力も重要です。近年では、FigmaやNotionなどのツールを使いこなすデジタルリテラシーも期待されています。
キャリアの広がりと転職市場のリアル
UXリサーチャーの経験を積むことで、将来的にはプロダクトマネージャーやUXディレクター、さらにはカスタマーエクスペリエンス(CX)戦略を担う上級職へのキャリアアップも目指すことができます。実際に、大手IT企業ではUXリサーチャーから戦略企画部門に異動した例も増えており、職域は広がりを見せています。
転職市場においても、UXリサーチャーの求人は拡大傾向にあります。2023年のデータによると、UX関連職種の平均年収は約650万円で、実務経験3年以上の場合には800万円以上を提示する企業も珍しくありません。特にSaaS企業やBtoCサービスを展開するスタートアップでは、UXの質が競争優位性に直結するため、即戦力となる人材への投資が活発化しています。
転職を成功させるためのポイント
UXリサーチャーとして転職を考える際には、企業がどれだけUXに投資しているか、組織内にUX専門チームが存在するか、またリサーチ結果がどのようにプロダクト改善に反映される体制かを確認することが重要です。また、職務経歴書では単なる業務内容ではなく、「どのような課題を発見し、どう提案し、結果的に何を改善したのか」といったプロセス全体を言語化することが評価につながります。ポートフォリオがある場合は、リサーチ設計やアウトプットの構成を具体的に示すと、より説得力を持たせることができます。
まとめ:ユーザーとプロダクトの未来をつなぐ仕事へ
どんなに優れた機能を持つプロダクトであっても、ユーザーにとって“使いにくい”“わかりづらい”と感じられてしまえば、その価値は半減してしまいます。そんな中、ユーザーの本音を掘り起こし、企業の意思決定に確かな根拠を与えるUXリサーチャーは、いま最も“求められている仕事”のひとつです。
数字やデータだけでは捉えきれないユーザー心理を読み解き、それをチーム全体に伝える力は、まさにプロダクトの未来を左右する重要な役割。働き方の柔軟性、年収の上昇傾向、そして豊富なキャリアパスなど、UXリサーチャーには今後さらに広がる可能性が詰まっています。
「人の気持ちを深く知りたい」「もっと良いサービスを世の中に届けたい」と思っている方にとって、UXリサーチャーというキャリアは、まさに理想的な選択肢になるでしょう。
- カテゴリ
- ビジネス・キャリア





























