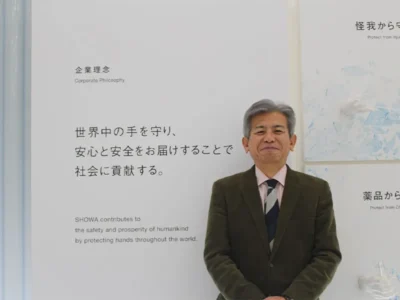2025年超私的世代論──ゆとりとロスジェネに見る“静かな優秀さ”
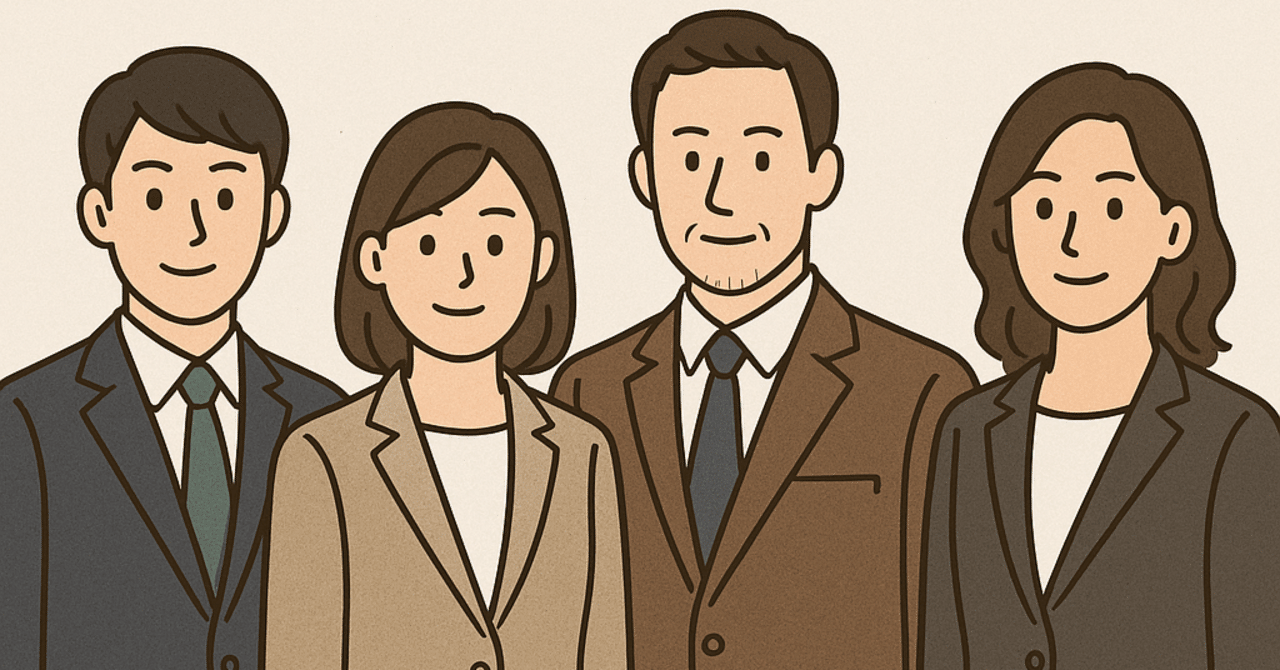
世代論はいつの時代も繰り返されるテーマです。
しかし今、30代〜40代を中心とした「ゆとり」や「ロスジェネ」の世代を見ていると、彼らの中にこそ“静かな優秀さ”があると感じます。
本稿では、ポッドキャスト番組「二番経営」の第79回エピソード「ゆとり世代の底力とロスジェネの真価とは?雑談的「世代論」」でも話した、2025年現在の筆者が私的に考える「世代論」を通して、時代に適応する力と、世代をつなぐ組織の知恵を探ります。
「近頃の若者は」
「近頃の若者は……」という嘆きは、いつの時代にもあります。
読者の皆さんは「古代エジプトの壁画にも若者批判が刻まれている」という話を聞かれた事があるかもしれません(これは都市伝説とされています)。
古典にも世代観を嘆く表現は多く、たとえばソクラテス(紀元前400)の「今の子供たちは贅沢を愛し、行儀が悪く、権威を軽蔑する」、ローマ詩人ホラティウス(紀元前20年)の「我々の父の時代は祖父の時代よりも悪かった。我々はその息子で、さらに価値がない」等が残っています。
こうした歴史的文脈を踏まえると、世代論は人類共通の話題だと言えるかもしれません。
今回は、“超私的世代論”と題し、人事・組織論の視点から「ゆとり世代」と「就職氷河期世代/ロスジェネ世代」の優秀さを考えてみたいと思います。
ゆとり世代を再評価する
「ゆとり世代」は“競争心がない”“打たれ弱い”といった印象を持たれがちです。
しかし、ゆとり教育の理念は「生きる力(Ikiru Chikara)」の育成にあり、
「自ら課題を見つけ、学び、考え、判断し、行動する力」を重視していました。その方向性は現在の学習指導要領にも受け継がれています。
OECDのPISA 2022調査によると、日本の15歳は
数学536点・読解516点・科学547点とすべてOECD平均を上回り、
数学・科学はOECD加盟国で首位、読解も上位(2位相当)という結果でした。
また、成人スキル調査(PIAAC)でも日本の16〜24歳層は読解力・数的思考力で参加国トップ水準。基礎的情報処理力と論理的思考力は国際的にも証明されています。
私自身、30代のビジネスパーソンと仕事をしていて感じるのは、相手を否定しない協調姿勢と多様な意見を束ねる力です。
これは総合的学習や対話的学びの成果でもあり、共創とスピードが鍵となる現代の組織に、極めてフィットした能力だと感じます。
ロスジェネ世代の「サバイバル・スキルセット」
「就職氷河期(ロスジェネ)」は、バブル崩壊後の厳しい環境で社会に出た世代です。
キャリアの不確実性を抱えながらも、地に足をつけて道を切り開いてきました。この経験が磨いたのが、実践的なサバイバル・スキルセットです。
-
レジリエンス(精神的回復力)
-
プラグマティズム(実用主義)
-
自己責任感と自律性
文化面では、90年代の漫画に象徴される努力と継続の価値観が共有されました。
「あきらめたらそこで試合終了ですよ」SLAMDUNK 27巻(1996年)
「努力した者が全て報われるとは限らん。しかし! 成功した者は皆すべからく努力しておる」はじめの一歩 42巻(1998年)
この価値観を糧に、粘り強く成果を積み上げてきた人たちがいま現場を支える中核になっています。
「巨人の肩の上」に立つということ
物理学者アイザック・ニュートンはこう言いました。
「私が遠くを見られたのは、巨人の肩の上に立っていたからです。」
テクノロジーが社会知を蓄積し、AIがそれを加速する現代。
若い世代はまさに巨人の肩の上からスタートしています。
1990年代以前は個人が自分で「知識の記憶と保有」していることが重視されましたが、今は「情報を選び、編集し、組み合わせて新しい価値を生む力」が問われます。ゆとり世代やZ世代の情報感度と協調性は、
テクノロジー時代に最適化された新しい優秀さのかたちです。
世代の優秀さは「時代の要請」で決まる
-
バブル期:競争力・忠誠心・上意下達への適応が価値
-
ロスジェネ期:レジリエンスと実利志向で環境を切り開いた
-
ゆとり〜Z世代:多様性・協働・スピードで成果を創る
どの世代が優れているかを比べるより、
世代ごとの特性を組み合わせて組織の知を最大化することが重要です。
上の世代が築いた仕組みの上に、次の世代がより速く、遠くへ進む。
それが健全な組織進化の姿だと感じます。
世代をつなぐ「知的共創」が競争力になる
「若者が頼りない」と感じるとき、それはもしかすると、自分が変化に追いつけていないサインかもしれません。
私が超私的世代論というテーマで伝えたいのは、世代を分断することではなく、つなぐことの大切さです。
世代横断のチーミングや対話を増やすこと。それこそが、企業にとっての新しい競争力になる。これが、私の「二番経営」での実践であり、皆さんと共に作る“静かで強い組織力”だと信じています。
ポッドキャスト「二番経営」のご案内
「二番経営 〜No.2の悲喜こもごも〜」は、なかなか表に出ない組織の「二番=No.2」をテーマに、トップのビジョンの実現の仕方や、この仕事の面白さ・大変さなど、「No.2の悲喜こもごも」を毎週水曜日に新エピソードを配信リスナーの皆さんにお届けしています。
Apple Podcast
Spotify
Youtube Music
番組の最新情報やご感想はこちら
-
Xアカウント(旧Twitter):
https://x.com/KatsumiYasuhide -
お便りサイトURL:
https://docs.google.com/forms/d/e/
1FAIpQLSfIAssluiJoSAgI6li4Vj1r8m
ZcoSc3LgdVuNptDV4kkJ5Atg/viewform
ぜひフォローやコメントをお待ちしています。
著者:勝見 靖英(株式会社オーツー・パートナーズ取締役)
- カテゴリ
- ビジネス・キャリア