「自己責任論」を超えて:就職氷河期から見える社会の課題
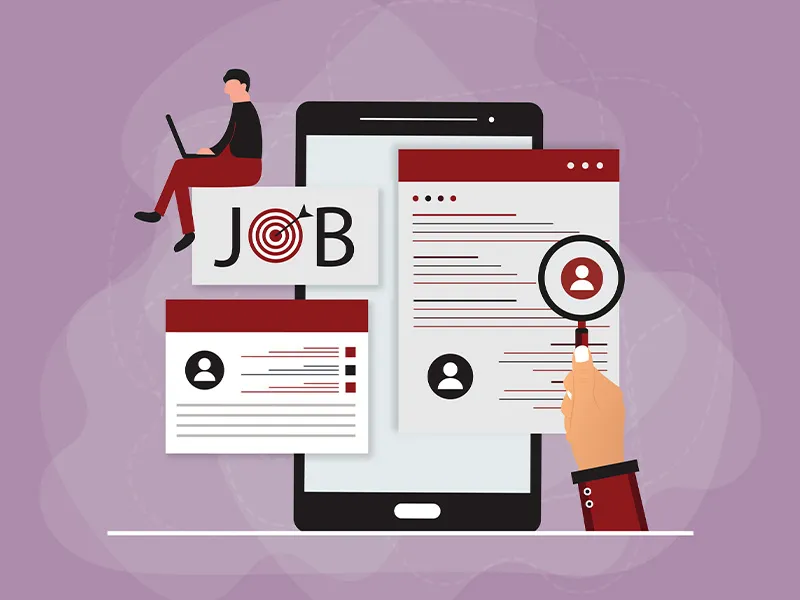
かつて「自己責任」という言葉が、若者たちに突きつけられた時代がありました。バブル経済崩壊後、日本は長い低成長期に突入し、1993年には新卒求人倍率が1.1倍を下回り、2000年には過去最低の0.99倍を記録します。この厳しい時代に社会に出た就職氷河期世代は、努力だけでは越えられない壁に直面しました。それから約30年、彼らが抱えた困難は、今も社会の根幹に深く影を落としています。
就職氷河期とは何だったのか
1991年のバブル崩壊を機に、日本経済は急激に冷え込みました。企業は採用活動を抑制し、新卒一括採用という日本型雇用慣行も大きく揺らぎました。文部科学省の調査によれば、1993年度卒業者の就職率は前年より大きく下落し、2000年前後には新卒の求人倍率が0.99倍という異例の水準に達しています。特に、大学卒業後3年以内に正規雇用に就けなかった若者は、以降も安定したキャリア形成が難しくなるという「キャリアの初期格差」が指摘されるようになりました。
当時の社会では、就職できないのは「本人の努力不足」であるという自己責任論が根強く、個々人の苦境は広く理解されませんでした。しかし実態は、個人の力ではどうにもできない経済環境の悪化に起因していたのです。自己責任論が強調される一方で、社会構造の変化がもたらす問題には、十分な対応がなされないまま年月が過ぎていきました。
自己責任論では片づけられない構造問題
就職氷河期世代は、その後もキャリアの初動の遅れを取り戻せず、現在でも非正規雇用率の高さが際立っています。厚生労働省の調査によれば、2022年時点で就職氷河期世代(現在40代後半から50代前半)の非正規雇用比率は約27%にのぼり、同年代の他世代と比較しても高水準を示しています。
非正規雇用では、賃金水準が正社員に比べて約6割程度にとどまるケースが多く、ボーナスや退職金も得られないことが一般的です。さらに社会保険未加入のリスクが高く、老後の年金額も大きく減少するため、生涯賃金や老後資金に深刻な格差が生まれることになります。
これらは単なる個人の努力不足では説明できない、明確な「構造問題」であり、社会全体で是正に取り組むべき課題だと言えます。
公的支援プログラムの現状と限界
こうした状況を受け、政府も支援に乗り出しました。2019年には「就職氷河期世代活躍支援プラン」が打ち出され、2022年度までの3年間で、30万人の正規雇用化を目標に各種施策が展開されました。具体的には、ハローワークによる専用窓口設置、職業訓練講座の強化、企業への助成金支給などが行われました。
実際に、これらのプログラムを通じて一定数の正規雇用者が生まれたことは事実です。しかし、目標に対して達成率は6割程度にとどまり、十分な成果を上げたとは言い難い状況です。特に、プログラムの利用者からは「制度が複雑で利用しにくい」「支援対象の年齢幅が狭い」といった声が上がっており、支援の実効性には課題が残されています。
また、長年にわたる不安定な生活により自己肯定感が低下し、そもそも支援に踏み出す意欲を持てない層も少なくありません。この「見えないハードル」をどう乗り越えるかが、次なる支援策の鍵となるでしょう。
社会が果たすべき新たな責任
自己責任論を超え、社会が果たすべき責任とは何でしょうか。それは、年齢や経歴にとらわれず、すべての人に機会を開く柔軟な社会システムを築くことに他なりません。企業側も、新卒一括採用の枠組みに依存せず、多様な人材を受け入れる採用文化を根付かせる必要があります。同時に、公的支援は単なる「施し」にとどめるのではなく、本人のキャリア回復を本気で後押しする仕組みとするべきです。たとえば、職業訓練後のマッチング支援を強化する、企業と連携した再雇用プログラムを広げるといった具体策が求められます。
さらに、メディアや教育現場においても、「努力すれば必ず報われる」という一面的な価値観を見直し、構造的困難を正しく理解する力を育むことが重要です。社会全体で、多様な生き方を支える意識改革が必要なのです。
まとめ
就職氷河期世代の歩んできた道は、私たちに一つの大きな問いを投げかけています。それは、努力を重ねても報われない状況に置かれたとき、社会は個人に何を差し出せるのか、という問いです。
自己責任論だけでは救えない現実が、そこにはあります。誰もが不安定な時代を生きる今こそ、過去の失敗に学び、誰一人取り残さない社会を目指すことが求められています。
就職氷河期世代が抱えた痛みは、未来をより良くするための教訓です。社会全体がその声に耳を傾け、寄り添い、共に前に進む時なのではないでしょうか。
- カテゴリ
- 社会



























