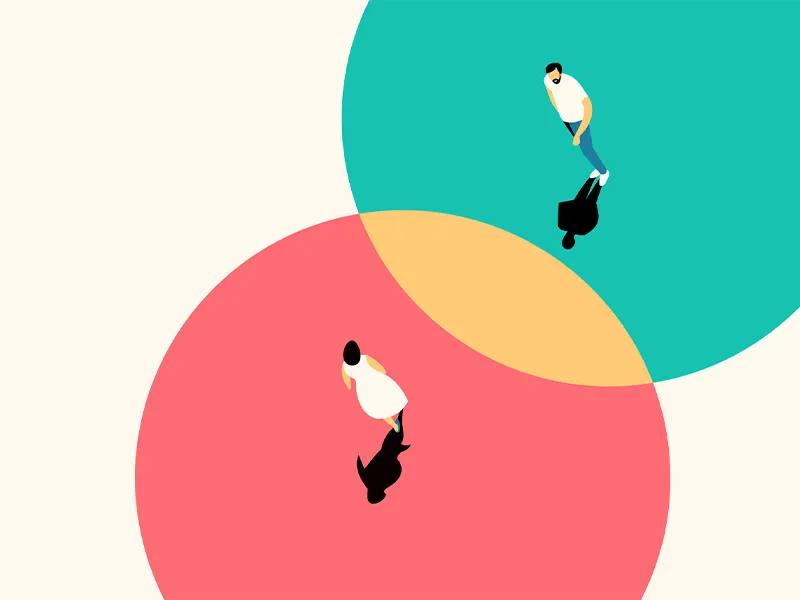“同じ生活、違う扱い”夫婦別姓と税制のすき間とは
変わりゆく家族のかたちと、変わらない制度のすきま
近年、夫婦のあり方に変化が見られるようになってきました。結婚してもそれぞれの姓を名乗りたいと考えるカップルや、法律上の婚姻届を出さずにパートナーとして暮らす事実婚の家庭が少しずつ増えています。しかし、こうした“名前の違う家族”が、公的制度に直面したとき、思いがけない壁にぶつかることが少なくありません。
特に、子育て世帯に欠かせない「児童手当」や、生活に大きく関わる「税金(扶養控除や配偶者控除)」といった制度において、夫婦別姓を選んだことが不利に働く場合があります。家族のかたちが多様化しているにもかかわらず、制度設計はまだ“同姓の夫婦”を前提にしている場面が多いためです。
児童手当の申請で浮き彫りになる“名字の違い”
児童手当は、子ども1人あたり月額1万〜1万5000円が支給される支援制度で、子育て家庭にとって重要な収入源となっています。この制度は原則として、住民票上で子どもと同居している保護者が申請し、自治体から受け取る仕組みになっています。ところが、夫婦別姓や事実婚の家庭では、いくつかのハードルが生じやすくなります。たとえば、親子で名字が異なる場合、親子関係を証明するために戸籍謄本などの追加書類を求められることがあります。また、夫婦が別々の住民票に記載されている場合、同居実態を示すための補足資料の提出を求められることもあり、申請手続きが煩雑になる傾向があります。
一部の自治体では、事実婚や未婚の母という扱いにより、申請者の立場が適切に理解されず、本来なら支給対象となる家庭が受給できていないケースもあります。これは、手続き上の誤解や運用のばらつきによって生じる不利益であり、家族構成の多様化に制度が十分対応していないことの表れといえるでしょう。
税金制度における“扶養”と“公平性”のズレ
日本の税制度では、配偶者や扶養家族がいる場合、所得税や住民税の負担を軽減する「配偶者控除」や「扶養控除」などの仕組みが整備されています。しかし、これらの制度の適用には、「法律上の婚姻関係」が前提とされていることが多く、夫婦別姓で戸籍が分かれている家庭や、事実婚のカップルは対象外になることがあります。
事実婚の夫婦が生計を共にし、どちらか一方が専業主婦(主夫)として生活していたとしても、税制上は「独身」と見なされる可能性があります。その結果、本来であれば年収要件を満たしていても、配偶者控除の適用を受けられず、年間数万円から10万円以上の税負担の差が生まれることもあり、また、扶養控除についても、子どもがどちらの親の扶養に入っているかによって、もう一方の親は控除を受けられないことがあります。さらに、相続税や贈与税においても、法律婚でない場合は非課税枠の適用が難しく、経済的に不利な立場に置かれてしまうことがあります。
こうした状況は、家族の実態と制度上の扱いにズレがあることを示しており、「課税の公平性」の観点からも見直しが求められる部分といえるでしょう。
制度のすき間を埋めるために社会ができること
日本では「夫婦別姓」が法的に認められていない現状があるため、多くの家庭が制度のすき間に悩まされています。「自分らしい姓を選びたい」「仕事の実績を継続させたい」「個としての尊厳を保ちたい」など、夫婦別姓を望む理由は多様です。それにもかかわらず、児童手当や税金などの制度では、依然として“同姓であること”が前提になっており、形式的な違いだけで実質的な不利益を被るケースが存在しています。これは、制度設計が現代のライフスタイルに追いついていないことの表れとも言えるでしょう。
一部では、事実婚を「婚姻に準ずる関係」として認定する動きも出てきており、自治体によっては独自のパートナーシップ制度を整備するなど、徐々に改善の兆しも見られます。ただし、それが全国一律に適用されているわけではないため、根本的な法改正が求められる状況に変わりはありません。
まとめ:これからの社会と家族制度のあり方
夫婦別姓を選ぶ人の中には、「仕事上の名前を変えたくない」「個人のアイデンティティを大切にしたい」など、様々な理由があります。同時に、事実婚や同棲といった柔軟なパートナーシップのかたちが、今や決して珍しいものではなくなってきました。しかし制度面では、いまだ「法律婚=同姓」が前提である場面が多く、マネーや手続きにおいて不利を受ける現実があります。特に児童手当や税制においては、子どもの健全な育成や家庭の経済支援という目的を考えれば、姓の違いで制限されるのは本末転倒とも言えます。
近年では、選択的夫婦別姓を可能にする法改正を求める声も強まっており、社会の理解も少しずつ進んでいます。家族のかたちが多様になる今こそ、制度もそれに追いつくべきタイミングなのではないでしょうか。
- カテゴリ
- 社会