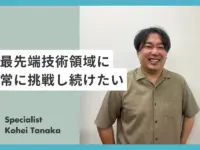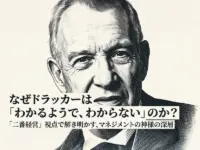働く母親が期待する新政権の支援策 現実とのギャップを探る

共働き世帯が増え続ける中で、働く母親は家庭と職場の両方を支える存在として社会を支えています。しかし、その努力が必ずしも報われるとは限らず、時間・経済・精神のすべてにおいて負担を感じる人は少なくありません。そんな中で新たに誕生した政権に、多くの母親たちは「暮らしの息苦しさを少しでも軽くしてほしい」という期待を寄せています。
新政権は育児と仕事の両立を支援する政策を次々と打ち出し、育児休業給付金の引き上げや、柔軟な勤務制度の拡充、保育体制の改善など、幅広い施策を進めています。政治の現場では“誰もが安心して働ける社会”を掲げ、女性活躍や子育て支援を経済政策の中心に位置づけています。
けれども、現場の声を拾うと、「制度はあるけれど実際には使いにくい」「職場の理解が追いついていない」といった実感が根強く残っています。表向きの支援と、生活の中で感じる現実の間には、まだ深い溝が横たわっているようです。
支援策への期待―働くことを諦めない社会を目指して
母親たちが新政権に望むのは、まず経済的な安心です。育児休業中の給付率引き上げや、扶養世帯への給付金の拡充は、生活の安定につながると受け止められています。収入の減少を理由に仕事を続けられない人が減ることで、安心して産休・育休を取れる社会に近づいていきます。
さらに注目されているのは「働き方の柔軟性」です。子どもの成長に合わせて勤務時間を調整できる制度や、在宅勤務の導入を進める企業が増えれば、母親たちが抱える時間の制約が少しずつ解消されます。こうした変化は、単に労働条件の問題ではなく、家族の生活の質を高める要素でもあります。
制度そのものが整うだけでは十分とは言えませんが、「支援を受けても肩身の狭い思いをしない社会」が形になれば、働く母親たちはこれまで以上に前向きに仕事を続けることができるでしょう。社会全体が家庭を支える意識を持つことが、次世代の育成を支える力になります。
政策と現場のずれ―制度があっても届かない現実
現場では、支援制度の利用が難しいという声が根強くあります。出産をきっかけに退職する女性は依然として少なくなく、その背景には「制度を使うと評価に響く」「同僚に負担をかけたくない」という心理的な壁があります。制度を整えるだけでなく、それを自然に使える職場文化が求められています。また、非正規雇用や自営業といった多様な働き方を選ぶ母親に、支援が十分に行き届いていない現状もあります。制度の対象が限られていることで、働き方を選ぶ自由が制限されることさえあります。都市部では保育施設が充実していても、地方では待機児童が残り、共働きを続けたくても続けられないという声が上がっています。こうした“支援の偏り”を解消するには、中央の政策だけでなく、地方自治体が地域の実情に合わせた柔軟な運用を進めることが不可欠です。
政策と現場の距離を縮めるには、「使いやすさ」に焦点を当てた改革が求められています。支援が“制度として存在する”だけでなく、“暮らしの中に根付く”段階へと進めていくことが課題です。
働く母親としてできること―制度を「使える機会」に変えるために
制度のギャップを少しでも縮めるために、働く母親自身が能動的に取り組めることがあります。まずは、自分自身の働き方・育児状況・家庭の課題を整理して職場に伝えることです。たとえば、子どもが○歳になるまで在宅勤務を希望する、あるいは入学前後に勤務時間を調整したいという具体的な働き方を提示すれば、企業も交渉をしやすくなるでしょう。
さらに、利用可能な制度を把握しておくことも重要です。国・自治体・企業が提供する育児・働き方支援制度や助成金、相談窓口などを知っていれば、「どの制度をどう利用すればいいか」が見えてきます。例えば、2025年4月に施行された改正法では、子どもが小学校3年生まで育児時間を取得できるなど、制度的な利用範囲が拡大しています。加えて、同じ働く母親のネットワークや地域の支援団体との情報交換が、実践的な知識を共有するうえで役立ちます。制度利用に関する“成功事例”を知ることで自信をもって交渉できるようになるでしょう。
新政権への期待―制度を“生きた支援”へと育てるために
制度をただ設けるだけでは十分ではありません。新政権には、制度が現場で実際に活用され、誰もが支援を受けられる環境を整えることを願います。とりわけ、非正規・フリーランス・単身赴任など、従来の雇用形態以外で働く母親を含めた幅広い支援対象を制度設計に入れることが重要です。
さらに、制度の設計段階から働く母親たちの声を反映させる“対話プロセス”を重視してほしいと考えます。現場の経験をもとに政策を練ることで、制度は数字上のものから、日常に根付く支えへと変わります。加えて、制度施行後のモニタリングと改善を繰り返す仕組みを政府が明確に示すことで、制度の信頼性が高まるでしょう。制度が「作ったから終わり」ではなく「使われて意味をもつ」ためには、こうした実行‐検証‐改良のサイクルが欠かせません。
まとめ
働く母親が抱く願いは、決して特別なものではありません。子どもを育てながら、自分の力で社会と関わり続けたい――その思いが支援政策の原点にあります。制度が整い始めた今こそ、政府と企業、そして地域社会が連携し、支援を「形ある仕組み」から「日常に根付く安心」へと進化させていく時期にきています。
母親たちが声を上げ、それを社会が受け止めることで、働くことと育てることが矛盾しない時代が現実になります。支援は与えられるものではなく、関わる人々の理解と協力によって育つものです。新しい社会をつくる一歩は、母親たちの小さな声をすくい上げるところから始まるのではないでしょうか。
- カテゴリ
- 社会