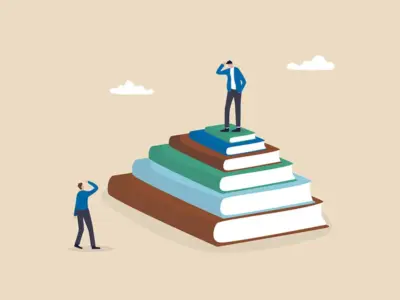PISAショック再び?日本の教育が問われる“思考力”とは

2003年、世界中に衝撃を与えた「PISAショック」。これはOECD(経済協力開発機構)が実施する国際学力調査「PISA」において、日本の生徒の学力が想定以上に低迷していたことから生じたものでした。それから20年余り、日本の教育はこのショックをきっかけに見直され、改善が図られてきました。しかし、近年再び浮上しているのが「思考力の低下」という問題です。果たして、今の日本の教育は、子どもたちの未来に本当に必要な力を育んでいるのでしょうか。
“思考力”とは何か――知識ではない力
「思考力」とは、単に知識を記憶する能力ではなく、それを基に自ら考え、課題を解決する力を指します。PISAで評価される読解力、数学的リテラシー、科学的リテラシーも、こうした思考力を土台としています。たとえば、「なぜこのような現象が起きているのか?」と疑問を持ち、仮説を立てて検証する力は、日常生活にも職業にも不可欠です。
日本の教育はこれまで「知識の習得」を中心としてきました。中間・期末試験では暗記力が問われ、正確に答えを導き出せるかどうかが評価の軸となってきたのです。しかし、PISAでは「知っていること」よりも「知識をどう活用できるか」が問われます。そのため、従来の日本の学習スタイルでは、思考力が十分に伸ばしきれないという課題が顕在化しています。
幼児期からの“問いかけ”がカギ
では、思考力はいつから育むべきものなのでしょうか。専門家によれば、思考力の土台は幼児期に形成されると言われています。絵本の読み聞かせを通して「どうしてこのキャラクターはこんな行動をしたのかな?」と問いかけることで、子どもは考える習慣を自然と身につけていきます。日常の中で「どうして雨が降るの?」「なぜ野菜を食べると体にいいの?」というような素朴な疑問に向き合い、一緒に考える姿勢が重要です。教育機関だけでなく、家庭においても、こうした「思考の対話」を積み重ねていくことが、後の学習スキルの基盤を築くことにつながります。
教育現場でも求められる“変化”
近年、文部科学省もこの問題に危機感を抱き、アクティブラーニングや探究型学習の導入を推進しています。黒板の前で教師が一方的に教える授業スタイルから、生徒同士が意見を交わしながら課題に取り組むスタイルへと転換が求められているのです。
例えば、小学校の理科の授業では「実際に実験してみる」「結果をグループで話し合う」「自分の考えを発表する」といったプロセスを取り入れることで、単なる知識の習得にとどまらない、思考の深化が促されます。
社会全体で育てる“未来の力”
とはいえ、学校教育だけで思考力を完全に育てることは困難です。家庭、地域、企業も含めた社会全体で、「自ら考え、学び続ける力」を育む環境を整える必要があります。たとえば、地域での自由研究イベントや、企業が提供するSTEAM教育プログラムなども、子どもたちの好奇心を刺激し、思考力を高める貴重な機会となっています。これからの時代に求められるのは、AIには代替できない「人間ならではの思考力」です。それは、複雑な課題を読み解き、最適解を自ら見つけ出す力であり、社会の変化に柔軟に対応する力でもあります。
おわりに
再び注目を集めるPISAショックは、私たちに大切な問いを投げかけています。それは「子どもたちは本当に考える力を身につけているのか?」という問いです。知識だけでは生き抜けない時代において、思考力は未来を切り拓くための“知のコンパス”です。
テストの点数や成績だけでは測れない本質的な学びや、正解のない問いに向き合い、自分なりの答えを導き出す力こそが、これからの社会を生きるための真のスキルとなります。そしてその力は、学校だけで育まれるものではありません。家庭での会話、地域とのつながり、社会のあらゆる場面で養われていくものです。
私たち大人が、「問い」を大切にし、「考えること」を楽しむ姿勢を示すことで、次世代に思考力の火を灯すことができるはずです。今こそ、教育のあり方を見直し、すべての子どもが自分の頭で考え、未来を描ける社会を目指していきましょう。
- カテゴリ
- 学問・教育