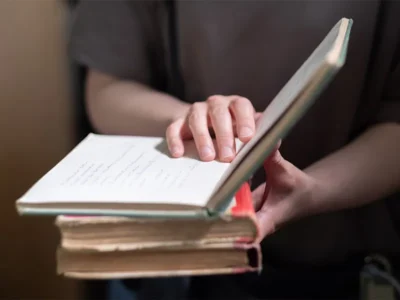読むだけでは記憶できない?科学が教える読書術

「読んだはずなのに内容を覚えていない…」——これは多くの人が抱える読書の悩みです。本を読むことは知識を増やし、人生を豊かにする大切な習慣ですが、読みっぱなしで内容を忘れてしまっては、その効果も薄れてしまいます。脳科学の研究では、記憶に残りやすい読書法にはいくつかの科学的な共通点があることが明らかになってきました。
感情と結びついた読書が記憶を強化する
記憶の定着には、「感情」が重要な役割を果たすことが脳科学の研究で示されています。脳内には「扁桃体(へんとうたい)」という部位があり、これは感情の処理を担う部分です。扁桃体が活性化すると、近くにある「海馬(かいば)」と呼ばれる記憶の司令塔も刺激され、記憶がより強く長期的に保存される仕組みになっています。
たとえば、ある小説の登場人物の気持ちに共感し、涙が出るほど感動した場面は、何年経っても鮮明に覚えているという経験はないでしょうか?これは、感情の伴った情報が記憶に深く刻まれるためです。したがって、読書中はただ情報をインプットするのではなく、「自分の感情を意識して読むこと」が記憶に残す第一歩となります。
読んだ内容を「出す」ことで記憶が固定される
次に重要なのが「アウトプット」の習慣です。脳科学では「生成効果(generation effect)」と呼ばれる現象があります。これは、情報を自分で思い出したり、説明したりすることで、単なる再読よりも記憶が強化されるという効果です。1冊の本を読んだあと、その内容を人に話して説明した場合と、ただ読み返した場合とでは、1週間後の記憶の定着率に約30%もの差が出たという研究結果もあります(※2014年ハーバード大学の研究より)。
実践方法としては、「3行で要約する」「印象に残ったフレーズを手書きでノートに写す」「Twitterやブログで感想を発信する」など、手軽なアウトプットがおすすめです。とくに手書きは、タイピングよりも脳の複数の領域を使うため、記憶に残りやすいといわれています。
読書の目的を明確にするだけで記憶力が変わる
目的意識を持って読書することは、脳の「前頭前野(ぜんとうぜんや)」を活性化させる効果があります。前頭前野は思考・判断・集中といった高度な認知機能を担う部分で、ここが活性化すると、脳が「これは重要な情報」と判断しやすくなるのです。
「この本から教育の変化について学びたい」「この章で記憶術の具体的な方法を得たい」といったように、読む前に目的を事前に決めておくことで、脳の前頭前野が活性化し、重要な情報を優先的にキャッチしようとします。結果として、記憶への定着率も自然と高まるのです。
また、章ごとに目的を変えて読み進める方法も効果的です。こうすることで内容を分類しながら記憶でき、後から情報を引き出しやすくなります。
習慣化で「読む→覚える」を日常に
記憶の定着において最も基本的かつ効果的な方法が「繰り返し」です。エビングハウスの忘却曲線によると、人は学習後24時間以内に約70%の内容を忘れてしまうといわれています。しかし、1日後・1週間後・1ヶ月後と段階的に復習することで、忘却の曲線を大幅に緩やかにできることが知られています。
この復習のタイミングを生活の中に組み込むことが、記憶の強化につながります。毎日同じ時間に読書する「時間の固定化」も、脳に「これは習慣」と認識させ、読書への集中力を高めます。
さらに、「関連付け読書」もおすすめです。ある1冊から派生して、同じテーマの別の著者の視点を読むことで、情報同士がネットワーク化され、単独の記憶よりも強い“記憶の束”が形成されます。これは学習における「スキーマ理論」にも通じる考え方で、脳の理解力と記憶力の向上に寄与します。
まとめ:読書を「記憶の財産」に変えるために
読書は知識を蓄えるだけでなく、自分自身の考え方や価値観を深めてくれる営みです。しかし、それを「記憶に残す」には、読み方にも工夫が必要です。感情を意識しながら読むこと、アウトプットすること、目的を持つこと、そして習慣にすること。これらはすべて、脳の働きと科学的根拠に基づいた方法です。
「読んだ本の内容をいつまでも覚えていたい」。その願いは、少しの工夫と継続で現実のものになります。脳に優しい読書習慣を、今日から始めてみてはいかがでしょうか。
- カテゴリ
- 学問・教育