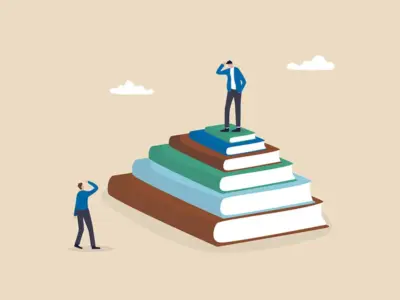インド版「新しい学び」NEP2020とは何か?――教育大国の次なる挑戦

急速に経済成長を遂げるインドでは、次世代を担う若者の教育制度改革が喫緊の課題とされてきました。そんな中、2020年に発表された「国家教育政策(NEP2020)」は、約34年ぶりの大幅な改訂として、国内外から大きな注目を集めています。この政策は、単なるカリキュラムの変更にとどまらず、子どもたちの可能性を最大限に引き出すための包括的な教育改革であり、「学びとは何か」という根本的な問いに対するインドなりの答えとも言えるものです。
なぜ教育改革が必要だったのか?
インドでは、これまで1986年に策定された教育政策に基づいて教育制度が運用されてきました。1992年には部分的な改訂が行われましたが、その後の急速な経済成長や技術革新、そして社会構造の変化には十分に対応できていませんでした。
教育現場では、記憶重視の一方通行の授業が主流となり、創造的な思考力や問題解決能力を育む機会が限られていました。また、都市と農村の間での教育環境や学力の格差、さらには学校教育と就業との接続が弱く、学んだことが実生活に活かされにくいという問題も顕在化していました。
NEP2020は、こうした時代遅れとなった構造を根本から見直し、「21世紀にふさわしい教育とは何か?」という問いに答える形で誕生しました。すべての子どもに公平で質の高い教育を提供し、個性と多様性を尊重することがその中核的な理念となっています。
新しい学びの枠組み:5+3+3+4の教育構造
NEP2020では、従来の「10年間の義務教育+2年間の高等課程」という枠組みから脱却し、子どもの発達段階に合わせた「5+3+3+4」の新しい教育構造が導入されました。この制度は、生涯にわたる学びの基盤を築くことを目的としています。
最初の5年間は、3歳から8歳までの乳幼児期を対象とした「基礎段階」とされ、遊びや対話を中心とした柔軟な学習が行われます。次の3年間は、8歳から11歳までの子どもを対象とした「準備段階」となり、読み書きや計算を通じて基礎的な学力を養います。さらに11歳から14歳までは「中等段階」と呼ばれ、観察や探究活動を通して論理的な思考力や問題解決力を身につけていきます。そして14歳から18歳までは「高等段階」として、各自の関心や進路に応じた専門的な学習を選択できるようになっています。
このように、年齢と認知発達に合わせてカリキュラムを構成することで、すべての子どもが自分に合ったペースで学びを進められる柔軟な教育環境が整えられつつあります。
授業と評価の革新:暗記から探究へ
NEP2020が掲げるもう一つの大きな改革は、教育内容や授業方法、そして評価制度の見直しです。これまでのインドの教育では、試験での得点が重視されるあまり、知識の暗記が中心となり、生徒自身が考えたり表現したりする機会が限られていました。
新たな方針では、「体験型学習」「プロジェクトベースの学び」「協働による問題解決」など、アクティブラーニングが導入されるようになっています。生徒はグループで議論したり、地域の課題を調べて発表したりすることで、思考力と表現力を高めていきます。評価方法についても、単なる年末試験ではなく、学習の過程を重視する「形成的評価」が中心に据えられています。教師による観察や生徒同士のフィードバック、自らの成長を振り返る自己評価が積極的に取り入れられ、生徒一人ひとりの理解や努力をきめ細かく評価する仕組みが整えられています。
言語教育の面では、初等教育段階において母語や地域語を用いた授業が「望ましい」とされており、多言語国家であるインドの文化的多様性に配慮した教育方針が打ち出されています。これは義務ではないものの、学習効果の高い方法として政策文書でも推奨されています。
社会とつながる学び:職業教育の導入
NEP2020では、学校教育と社会・経済活動の橋渡しを担う「職業教育」の重要性も強調されています。中等教育段階にあたる12歳以降の生徒を対象に、最低でも一つの職業技能に触れる機会を提供することが推奨されています。その内容は多岐にわたり、農業、木工、手工芸、ITリテラシー、金融リテラシーなど、実社会で活用できる技術や知識が中心となっています。これは義務ではないものの、すべての生徒が将来の進路や職業選択に向けて早い段階から意識を高め、自立した人生を歩むための準備となることを期待されています。
とりわけ、都市部と農村部での教育機会の差を縮小し、地域に根ざした学びと雇用をつなぐ施策としても注目されています。
高等教育の改革:自由で柔軟な学びへ
大学教育においても、NEP2020は大きな改革を進めています。学士課程は原則4年制となり、1年、2年、3年での中途修了にもそれぞれ証明書(Certificate)、準学士(Diploma)、学士号(Degree)が授与される仕組みが導入されます。これにより、途中で進学を断念した場合でも、それまでの学びが社会的に認められるようになります。「Academic Bank of Credits(ABC)」という新たな制度も計画されており、複数の大学で取得した単位を蓄積・統合しながら、柔軟に学位を取得することが可能になる構想が進んでいます。この制度は現時点では一部試験導入の段階ですが、将来的には全国規模での展開が期待されています。
また、学問分野の横断も積極的に推奨されており、たとえば文学を専攻しながら経済学やコンピュータサイエンスの授業を履修することも可能となります。こうした「学際的学び」が、より多角的な視野を持った人材の育成に寄与するとされています。
世界への影響と日本への示唆
NEP2020は、単なる国内の教育政策にとどまらず、新興国を中心に国際的なモデルケースとなり得る可能性を秘めています。インドのように人口が多く、地域格差が大きい国において、持続可能で多様性を尊重した教育制度を構築することは、他国にとっても極めて有益な示唆となるでしょう。
とくに、創造性や非認知能力を重視する姿勢、職業教育と一般教育の融合、そして大学教育の柔軟化といった点は、日本の教育制度にも共通する課題であり、NEP2020から学ぶことは多いといえます。
まとめ:NEP2020が描く未来の学びとは
NEP2020は、知識の暗記に偏っていた旧来の教育から脱却し、探究心と創造力、そして社会とつながる力を育む新しい教育のかたちを提案しています。すべての子どもが等しく、そして柔軟に学びを深めることができる制度設計は、インドが持つ教育的ポテンシャルを最大限に引き出すものであり、今後の社会・経済発展の基盤となるでしょう。
その改革の行方は、インド国内にとどまらず、世界各国の教育関係者にとっても重要な関心事項となるはずです。教育の未来を見据える上で、NEP2020が示すビジョンは、大きな学びと可能性を私たちに与えてくれます。
- カテゴリ
- 学問・教育