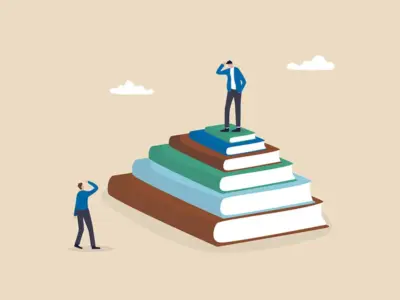デジタル時代の幼児教育 スクリーン利用の“上手な付き合い方”とは
テクノロジーとともに育つ子どもたち
スマートフォンやタブレットが家庭にあふれる今、幼児がスクリーンに触れることは特別なことではなくなりました。動画サイトや知育アプリを通じて、子どもたちは文字や色、音の世界を直感的に学んでいます。一方で、長時間の使用による集中力や情緒面への影響を懸念する声も多く聞かれます。
総務省の調査(2024年)では、3〜6歳児の約7割が日常的にデジタル機器を利用していると報告されています。研究によれば、幼児期におけるスクリーン時間の長さは、発達のさまざまな領域と関連しており、ある研究では1日1時間を超えるスクリーン時間は身体的健康、社会性、言語・認知発達、コミュニケーション能力のいずれも「脆弱(vulnerable)」となる可能性が高いという結果が報告されています。
家庭の中でデジタルが自然に共存する時代において、教育の現場や保護者が求められているのは、排除ではなく「どのように活かし、どう制御するか」という姿勢です。スクリーンとの関わり方を見直すことは、幼児教育全体の質を高める重要な鍵となっています。
感性と知性のバランスを育てる
幼児教育において、知識を獲得する“学び”だけでなく、感性や情緒、他者との関係性を育む時間がとても重要です。アニメや教育アプリなど、デジタル教材が興味を引きやすいのは確かです。音や映像、インタラクティブな要素が知語彙の獲得を促したり、初期の認知刺激になったりもします。
一方で、画面を通じた学びだけでは、他者とのやり取りを通じて育まれる感情表現や共感力が十分に発達しにくいことも指摘されています。アメリカ小児科学会(AAP)は、2歳から5歳の子どもに対し、1日のスクリーンタイムを1時間以内に抑えることを推奨しています。
つまり、重要なのは“どれだけ使うか”ではなく、“どのように使うか”という視点です。絵本を読んだ後に実際に絵を描いてみる、動画で見たものを外で体験してみるなど、子どもがただ受け身で視るだけでなく、親子で読み解んだり、会話をつくったりする「共視聴」「対話的利用」が鍵になります。
家庭と教育現場の協働がもたらす新しい学び
デジタルとの付き合い方を考える上で、家庭と教育機関の連携は欠かせません。保護者が子どもと一緒に映像を見たり、アプリを操作したりする“共視聴”の時間は、単なる娯楽から対話を生む機会へと変わります。親子で感想を共有することで、観察力や語彙力の発達を促すだけでなく、メディアの内容を客観的に捉える姿勢も養われます。
教育現場でも、タブレットを活用した活動が広がっています。海外では、フィンランドの幼児教育において「デジタル遊び」を取り入れ、子どもがカメラで自然を撮影したり、プログラミングの基礎を体感的に学ぶ取り組みが進んでいます。日本でも、地域の保育園で海外の園児とオンラインで交流する試みが始まり、異文化への理解を育むきっかけとなっています。
こうした実践が示すのは、デジタル機器を“隔たり”ではなく“つながり”のツールとして活かす発想の重要性です。保育者と家庭が情報を共有しながら、子どもの興味や特性に合わせた使い方を模索することが求められています。
“使わせる”から“使いこなす”へ
これからの幼児教育では、デジタル機器をどのように扱うかという“リテラシー教育”が基礎となっていきます。画面を操作する力だけでなく、情報を選び取る判断力、他者への思いやりを持って使う姿勢など、総合的な「使いこなす力」を育てる視点が欠かせません。
文部科学省が進める「GIGAスクール構想」では、小学生から1人1台の端末利用が標準化されています。その前段階となる幼児期では、デジタル機器を“教える道具”ではなく、“考えるきっかけ”として扱うことが重要です。たとえば、タブレットで描いた絵を紙に再現したり、動画で見た実験を実際に行ってみたりするなど、デジタルとリアルを往復する体験を重ねることで、創造性と主体性を養えます。
保護者と教育者が協力し、デジタルを単なる情報源ではなく「共に学びを深めるためのパートナー」として位置づける姿勢が、これからの教育の基盤となるでしょう。
まとめ
デジタル時代における幼児教育は、テクノロジーを避けるか受け入れるかという二択ではなく、どう共存させるかを考える時代に入りました。スクリーンを通じて得られる学びと、直接体験から生まれる感動。その両方を調和させることが、子どもの心と知性を豊かに育てます。
家庭と教育現場が歩調を合わせ、デジタルの向こうにある“人とのつながり”を大切にする姿勢こそが、真の意味での「デジタル教育」のあり方といえるでしょう。
- カテゴリ
- 学問・教育