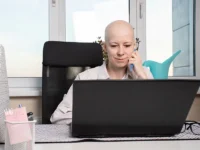年齢を重ねたからこそ見直したい、モノとの付き合い方

〜暮らしを軽やかに整える“人生後半の整理術”〜
年齢を重ねるにつれて、生活のスタイルも価値観も自然と変化していきます。若い頃には「便利さ」や「豊かさ」を象徴するように思えたモノたちも、ある時期を境に「持ちすぎることのストレス」や「暮らしにくさ」を生む原因になることがあります。人生の折り返し地点を越えた今だからこそ、「モノとの付き合い方」を見直すことは、心と身体の健康に大きな影響を与える大切なテーマです。
モノが増える理由と高齢者世帯の課題
高齢者世帯は年々増加しており、2024年の総務省調査によれば、65歳以上の人口は約3,600万人、全体の約29%を占めています。とくに単身高齢者世帯や夫婦のみの世帯では、長年の暮らしで蓄積されたモノが溢れ、管理しきれないケースも少なくありません。
例えば、押し入れの奥に眠る衣類、読み終えたまま積まれた本、使わなくなった家電製品。これらは物理的なスペースを奪うだけでなく、掃除の手間や転倒リスクを増やし、日常生活の快適さを損なう原因となります。とくに床に置かれたモノが原因で転倒・骨折を招く事例は多く、実際、65歳以上の転倒事故の約3割は家庭内で発生していると言われています。
捨てるのではなく、“選び直す”という考え方
贈り物として受け取った食器、旅先で選んだ置物、何度も袖を通したお気に入りの洋服。そのひとつひとつには、思い出や感情が深く刻まれていて、簡単には手放せないものです。
だからこそ、モノとの関係を見直すときは、「捨てる」ではなく、「選び直す」というやさしい視点が大切です。これは、自分の暮らしに今ふさわしいものを、もう一度選び直すという前向きな行動です。決して後ろめたいことでも、無理をすることでもありません。
たとえば、長年使っていない茶碗があったとします。それを見るたびに懐かしさを感じるけれど、もう手に取ることはない。そんなとき、「いまの私の暮らしには少し大きすぎるかもしれない」と気づいたなら、その茶碗に「ありがとう」と心の中で声をかけ、そっと手放してみるのです。地域のバザーやリサイクルに出せば、それを必要としている誰かの手に渡り、新たな役目を果たしてくれるかもしれません。
また、「選び直す」ことで、本当に大切にしたいモノがより際立って見えてくることもあります。思い出の写真を一冊のアルバムにまとめたり、着やすい一張羅を数枚だけ残して楽しんだり。数が減っても、満足度はむしろ高まるのです。
「使いやすさ」こそが安全な暮らしを支える
モノが少ないと、見通しの良い空間が生まれ、日常の動作がスムーズになります。特に高齢者にとっては、取り出しやすく、戻しやすい配置が生活の質を大きく左右します。たとえば、頻繁に使う衣類はタンスの上段へ、薬や眼鏡は手元の棚へ。こうした動線の見直しは、家事の効率化だけでなく、怪我や事故の予防にもつながります。整理整頓とは、単なる片づけではなく、“暮らしの安全対策”でもあるのです。
また、災害時の備えとしても、通路や玄関まわりがすっきりしていることで、いざという時の避難行動がスムーズになります。モノを絞り込むことは、安心を手に入れる行為でもあるのです。
モノの見直しが生み出す、新たな豊かさ
モノを減らすことで生まれるのは、単なる「空間の余白」ではありません。心の余白もまた、同時に手に入れることができます。
不要な家具を処分し、空いたスペースに小さな読書コーナーを作る。着なくなった洋服を手放し、お気に入りの1着を毎日楽しむ。そうした小さな工夫が、日々の暮らしに心地よさと自信をもたらします。
さらに、近年では高齢者向けの「整理収納アドバイザー」の訪問サービスや、地域での片づけ講座も増えています。家族と一緒に進めるのも良いですが、専門家の力を借りることで、より安心して前向きに整理を進めることができます。
まとめ:暮らしを見直すことは、自分らしさを取り戻すこと
モノとの付き合い方を見直すことは、これまでの人生を振り返り、これからの生き方を見つめ直すきっかけになります。
「たくさん持っている=豊かさ」という時代から、「本当に必要なものと丁寧に暮らす」時代へ。
年齢を重ねたからこそ、「今の私にとって大切なものは何か」を問い直すことで、よりしなやかで心地よい暮らしが始まります。
モノを通じて、自分と対話し、家を整え、心を整える。その積み重ねが、これからの人生をさらに豊かなものにしてくれるでしょう。
- カテゴリ
- 生活・暮らし