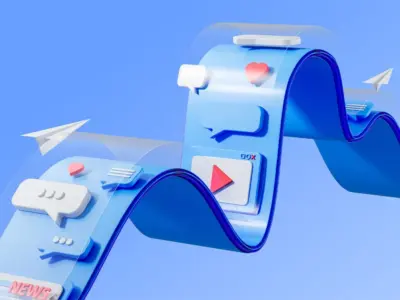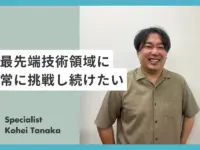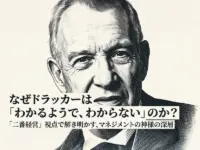スタートアップにバズは効く?拡散時代のマーケ戦略を読み解く

スタートアップにとって、プロダクトやサービスの質と同じくらい重要なのが「どう認知を広げるか」という情報発信の戦略です。創業初期のフェーズでは、広告費を大きくかける余裕はなく、人材も限られる中で、いかにして社会の目に触れるかを考える必要があります。そんななかで、注目を集めているのが「バズマーケティング」と呼ばれる手法です。
SNSで自然に拡散される形で情報を届けるこのアプローチは、運が良ければ一夜にしてフォロワーが数万人単位で増加し、メディアにも取り上げられ、大企業と肩を並べる知名度を獲得することも可能です。ですが、バズは“刃”にもなり得ます。誤った打ち出しや準備不足で、せっかくの注目が一過性で終わるだけでなく、炎上や信頼失墜につながるケースもあります。
SNSがつくる“瞬間の波”に乗るスタートアップたち
バズマーケティングとは、SNSや口コミを通じて自然発生的に注目を集めるマーケティング手法です。広告として仕掛けるというよりも、人々の共感や驚きをきっかけに拡散が起こる仕組みであり、拡散力の高いプラットフォーム──X(旧Twitter)、Instagram、TikTok、YouTubeなど──で特に有効とされています。
実際に、バズマーケティングを巧みに活用したスタートアップの事例は数多く存在します。たとえば、2023年に創業された都内の健康食品D2Cブランドは、「未来の完全栄養おにぎり」という独自商品のプロトタイプをXで発信し、たった一晩で1万リポスト・2万いいねを獲得しています。その後、クラウドファンディングを通じて1,500万円以上を調達し、正式な商品化に至りました。このように、メディア広告費ゼロでもSNSを通じて資金調達と認知拡大を同時に達成することが可能なのです。
なぜスタートアップとバズは“相性が良い”と言われるのか?
スタートアップがバズを起こしやすい理由は、大きく3つあります。
まず1つ目は、スタートアップがもともとユニークで革新的な製品やサービスを提供している点です。世の中にまだ存在しない価値を提示する企業は、それだけで「話題のタネ」になり得ます。
2つ目に、スタートアップには柔軟でスピーディな意思決定が可能な体制があります。トレンドが目まぐるしく変化するSNSの世界では、1日遅れただけでチャンスを逃すこともあります。経営層と現場の距離が近いスタートアップは、タイムリーな反応と施策展開がしやすく、これがバズとの親和性を高めています。
そして3つ目は、リスクテイクに対する心理的障壁が低いことです。知名度の低い初期フェーズであれば、少々奇抜なアプローチでも失うものが少なく、むしろ“尖った打ち出し”がブランドの個性として受け入れられやすいのです。
バズの“先”を設計できなければ成功とは言えない
ただし、バズが起きたからといって、その企業が持続的に成長するとは限りません。実際に、「バズったのに売れない」という現象は少なくなく、2022年のある調査では、SNSで話題になったスタートアップ商品のうち約43%が、半年以内に売上失速を経験していると報告されています(株式会社トライアル調査レポート)。
この原因の多くは、バズの瞬間に注目を集めることに成功しても、その後の導線設計が不十分であることにあります。問い合わせ窓口や公式サイトが混雑し、対応が間に合わなかったり、ECサイトがダウンしたりすることで、ユーザー体験が損なわれ、せっかくの関心が失望へと変わってしまうのです。
また、話題性だけに依存していると、ブランドが“ネタ”として消費され、信頼や愛着を育むことが難しくなります。スタートアップが目指すべきは、単なる一過性の現象ではなく、共感をベースにした“信頼の蓄積”です。
バズを経営戦略に組み込む視点
では、どうすればバズを一過性で終わらせず、経営戦略として活かせるのでしょうか。ここで重要になるのが、バズを中心に据えるのではなく、「バズを起点にストーリーを展開する」という発想です。たとえば、バズによって一時的に集まったSNSフォロワーに対して、定期的に裏側の開発ストーリーや失敗談、ユーザーの声などを発信し、共感を醸成していくことが考えられます。また、メディア露出をブランディングの一環として設計し、第三者からの評価を通じて信頼を高めていく流れをつくることも有効です。
そして、広告運用やパートナー施策など他のマーケティングチャネルと連動させ、バズで得た注目を収益や継続的なリード獲得へと接続させていく視点が求められます。
結論:バズは“武器”ではなく“きっかけ”にすぎない
スタートアップにとって、バズマーケティングは確かに有効な戦術のひとつです。しかし、それはあくまで「きっかけ」であって、「目的」ではありません。短期的な成果だけを追うのではなく、長期的な信頼とブランド形成につなげていくためには、バズの“後”をどう設計するかが勝負になります。
スタートアップが社会に新しい価値を届ける存在であるならば、その価値が正しく伝わる仕組みを、自らの手でデザインしていく必要があります。バズはその第一歩として、非常に優れた導火線になり得るでしょう。
- カテゴリ
- インターネット・Webサービス