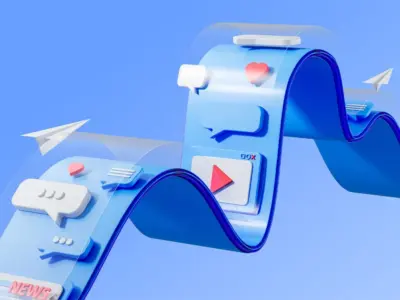「営業とマーケがつながらない」を解決するコンテンツ設計術

企業における「営業」と「マーケティング」は、車の両輪のような存在です。しかし実際の現場では、「マーケが作ったリードが質的に合わない」「営業がマーケティングの戦略を無視して動いている」といったすれ違いが多く見られます。営業とマーケがうまく連携できないままでは、せっかくの施策が空回りし、成果につながりません。この課題を解決するカギとなるのが、両者の“共通言語”となるコンテンツの設計です。
分断の背景:異なる目標と評価基準
営業とマーケティングの分断は、実は「目的の違い」と「評価軸の不一致」に起因することが多くあります。営業部門は主に月間や四半期ごとの売上目標を追い、短期的な数字を重視する傾向があります。一方、マーケティング部門は中長期的なブランディングや潜在顧客の育成(リードナーチャリング)を目指しており、KPIも「サイト流入数」「リード獲得件数」「エンゲージメント率」など間接的な指標が中心です。
実際、ある国内IT企業の調査によると、営業とマーケが「お互いに連携できている」と答えた担当者は全体のわずか32%。残りの68%は「課題がある」と感じており、その主な理由として「情報共有の不足」「指標の違い」「コンテンツ活用の乖離」が挙げられています。
両者をつなぐ「共通言語」と「共通指標」の設計
このような分断を乗り越えるためには、コンテンツが両者の橋渡し役となることが重要です。そのためには、まず営業とマーケが共通の認識を持てる「言語」と「数字」の整備が不可欠です。
たとえば、コンテンツの目的を「潜在顧客の関心喚起」「課題認識の明確化」「ソリューションの提示」「商談誘導」といった形で定義することで、営業とマーケの会話のズレを減らすことができます。さらに、「資料ダウンロード後7日以内の商談化率」や「コンテンツ起点の受注金額」など、双方が追える共通KPIを設定すれば、施策の効果を明確に共有できます。実際に、あるSaaS企業では、営業とマーケが「1コンテンツ=1商談貢献」を意識して共同でコンテンツを設計した結果、営業の商談化率が21%向上し、6か月間で受注件数が前年比で1.4倍に伸びました。
成果につながるコンテンツ設計の3つの要諦
営業とマーケティングの連携を深め、実際の成果に結びつけるためには、単に「情報を発信する」だけでは不十分です。見込み顧客(リード)との信頼関係を育みながら、段階的に購買意欲を高めていく「ナーチャリング(育成)」の視点が不可欠です。
ここでは、営業とマーケの橋渡しとなり、受注につながるコンテンツをつくるための3つの重要な考え方をご紹介します。
1. 営業現場から得られる「生の声」を起点にする
最も説得力のあるコンテンツは、顧客のリアルな疑問や不安から生まれます。
たとえば、営業担当がよく受ける質問に「導入にはどれくらい時間がかかりますか?」「他社と比べて何が違いますか?」といった内容があります。こうした声を拾い、わかりやすく答える形でホワイトペーパーやFAQ、比較表などのコンテンツに落とし込むことで、顧客の不安をあらかじめ解消し、商談を前向きに進めることができます。
また、こうしたコンテンツは、マーケティング活動においても大いに活用できます。広告のランディングページに掲載する、メールマガジンで配信するなど、顧客との初期接点でも「現場目線の説得力」が武器になるのです。
2. 「営業が使いやすい」形式で届ける
どんなに優れた内容でも、営業が使いにくい形式では宝の持ち腐れになってしまいます。
営業担当が即座に商談に使えるように、提案資料やトークスクリプト、動画、チェックリストといった“実用性の高い”形式でコンテンツを整えることが大切です。
あるBtoB企業では、営業用資料を動画付きのPDFで共有し、顧客の反応をリアルタイムで共有できるフィードバックシステムを導入しました。その結果、コンテンツ活用率が2倍に向上し、平均商談時間も25%短縮されるなど、営業効率が大きく改善されました。
営業との共創による“使える資料”づくりは、コンテンツ設計における重要なステップです。
3. 継続的なナーチャリングの導線を設計する
ナーチャリングとは、一度獲得した見込み客に対して、関心度や検討度合いに応じて継続的に情報提供を行い、段階的に購買意欲を高めていく活動のことです。
すぐに商談につながらない見込み客でも、有益な情報を定期的に届けることで「この企業は信頼できる」と感じてもらい、やがて商談化・受注につながる可能性が高まります。
たとえば、「業界の最新動向をまとめたレポート」「成功企業の事例紹介」「製品の使い方解説記事」など、SNSやオウンドメディアを活用して段階的に提供することで、関心層から検討層へと顧客を“育てて”いくことができます。
実際に、あるIT系企業では、ナーチャリング用のメールコンテンツを週1回配信する施策を導入し、開封率は平均23%、コンテンツ経由の商談化率は15%を記録するなど、高い効果が得られました。
「使われるコンテンツ」が企業の成長を支える
営業とマーケティングが真につながるためには、共通の視点を持ち、「現場で実際に使われる」コンテンツを創り上げることが必要です。それは単なる資料ではなく、「顧客に届き、営業が使い、マーケが検証する」三位一体のサイクルを回す設計思想です。
これからの時代、企業の競争力は「コンテンツの質」と「連携の質」によって決まると言っても過言ではありません。営業とマーケの境界を越え、成果を生み出すコンテンツ設計を実践することが、組織全体のパフォーマンス向上につながるでしょう。
- カテゴリ
- インターネット・Webサービス