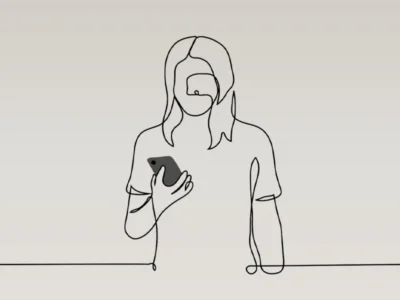マスメディアから“ナローメディア”へ:分断時代の戦略とは

かつては一家団らんの象徴でもあったテレビを中心としたマスメディア。しかし現代では、誰もが同じ情報を同じ時間に受け取るという時代は過去のものになりつつあります。インターネットとSNSの浸透によって、個人が自ら選んだメディアに日々接触するようになり、社会全体の情報接触のあり方が根本から変化しています。
総務省の「情報通信白書(2023年)」によれば、日本国内のインターネット利用率は約83%に達し、10代〜30代に限ると90%を超えています。さらに電通の調査では、2023年のインターネット広告費が3兆3300億円と、テレビ広告費(1兆6750億円)を大きく上回る結果となりました。こうしたデータは、企業やメディアが「マス」ではなく「ナロー」な領域に軸足を移す必要性を如実に物語っています。
ナローメディアとは何か?──“狭く深く”の情報戦略
ナローメディア(Narrow Media)とは、属性や関心軸が明確な人々に向けて、特化した情報を継続的に提供するメディア形態です。YouTubeの専門チャンネル、ポッドキャスト、LINE公式アカウント、サブスクリプション型メディア、あるいは独立系メールマガジンなどがこれに該当します。
たとえば、登録者数2万人程度のYouTubeチャンネルであっても、「30代共働き家庭向けの節約術」や「中小企業の経理担当者向けの業務改善情報」など、対象を明確に絞り込んだコンテンツであれば、高い視聴完了率やコメント参加率を生み出し、企業案件で月収数十万円を超えるケースも多く見られます。ナローメディアの強みは、視聴者のエンゲージメントの“質”にこそあるのです。
なぜナローメディアが選ばれるのか?──価値観の分断と情報の選択
近年、視聴者の情報接触スタイルはますます分散・個別化しています。とくにZ世代やミレニアル世代は、テレビをリアルタイムで視聴する習慣を持たない人が多く、2023年のLINEリサーチによると「1週間にテレビを見ない日がある」と回答した10代〜20代の割合は65%を超えました。
このような状況下では、企業が“誰に届けるか”を戦略的に定めない限り、広告は空回りしてしまいます。「広く届ける」より「深く届く」ことの方が、ビジネス成果に直結する時代に変わったのです。
マスメディアの役割と変化──残る“広域性”と求められる“再定義”
もちろん、マスメディアの全てが機能不全に陥っているわけではありません。NHKやキー局による災害報道や国政選挙の報道など、社会インフラとしての機能は今も重要です。2024年1月の能登半島地震では、地上波テレビとラジオが、ネットの使えない地域の情報ライフラインとして機能し、公共メディアの役割を再認識させる出来事となりました。
しかし、広告主が期待するような「リーチ」や「コンバージョン」において、マスメディアが優位性を持ち続けるのは難しくなっています。結果としてテレビ局の多くは、FOD(フジテレビ)、TVer(日テレ・テレ朝連携)など独自の動画配信サービスを強化し、ナローメディア的な配信モデルへ移行しつつあります。
ナローメディア成功の鍵は「深く理解し、共に育てる」
ナローメディアで成果を出すためには、単に情報を届けるだけでは不十分です。まずは“誰に届けるのか”を明確に設定し、その層の悩み・価値観・日常行動までを具体的に理解することが求められます。たとえば、20代後半の働く女性を対象にしたメディアなら、仕事と美容、節約術、メンタルケアといったテーマの選定とトーン設計が不可欠です。
さらに、継続的なコンテンツ提供によって「関係性」が育ちます。YouTubeでは週2回の定期更新、Voicyでは毎朝5分の音声配信、LINE公式では週1回のニュースレターなど、“習慣化”と“共感性”が鍵を握ります。また、読者とのコミュニケーションを設計に組み込むことで、単なる視聴者ではなく「共創者」としてのファン層が形成されていきます。
まとめ:ナローメディアは分断時代の“信頼”を再構築する
情報があふれ、価値観が細分化されるこの時代、マスメディアの「一律的な信頼」よりも、ナローメディアによる「共感ベースの信頼」が重視されるようになっています。企業やメディア運営者にとって必要なのは、多くに届く情報よりも、“ある誰かの人生に確かに届く”情報の設計力です。
ナローメディアは単なる代替メディアではなく、これからの社会において“信頼の再構築装置”としての役割を担っていく可能性を秘めています。
情報発信の在り方を問い直すとき、マスとナロー、その両方を理解し使い分ける戦略こそが、これからの時代に求められる知恵なのかもしれません。
- カテゴリ
- インターネット・Webサービス