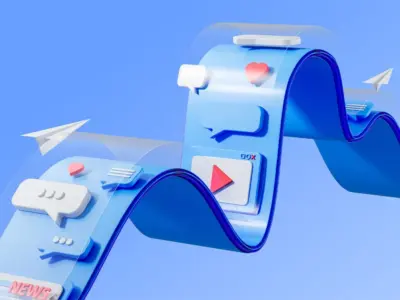ネットの中の「居場所づくり」が人生に与える影響とは
デジタル空間が生み出す「もうひとつの居場所」
スマートフォンやパソコンを開けば、SNSやオンラインコミュニティ、動画配信サービスなど、無数の「つながりの場」が存在しています。総務省の2024年版通信利用動向調査によると、日本のインターネット利用率は全世代平均で約89%に達し、10代から30代ではほぼ100%に近い数値を示しています。
かつて「ネットは現実とは別の世界」と捉えられていた時代から、いまや「ネットも現実の一部」と言える時代へと移行しました。X(旧Twitter)やInstagram、Discordなどで、趣味や価値観を共有する仲間と日常的に交流することは、社会生活の一部になりつつあります。そこには、学校や職場と異なる「もうひとつの居場所」が広がっています。
このデジタル空間における居場所は、物理的な距離を超えた「共感のつながり」を生み出します。現実世界では孤立を感じていた人が、オンライン上で同じ関心を持つ仲間を見つけ、心の拠り所を得るケースも少なくありません。特にコロナ禍以降、「オンライン居場所」の意義は再評価され、多くのユーザーが心理的な支えとして活用するようになりました。
SNSと心理的安全性:孤独を和らげるデジタル関係
LINEリサーチが2025年に実施した調査によると、「SNS上で相談できる相手がいる」と答えた人は全体の64%に上り、20代では75%を超えています。リアルな関係よりもネット上の交流に安心感を覚える人が増えているのは、対面よりも「自分を出しやすい」環境が整っているからです。
SNSでは、匿名性や距離感が心の安全弁として働きます。たとえばXやThreadsなどで日々の悩みや感情を発信すると、同じ経験を持つ人々が共感や励ましのコメントを返してくれる。こうした相互作用は心理学で「ソーシャルサポート」と呼ばれ、ストレスの軽減や自己肯定感の向上に寄与することが知られています。
実際、筑波大学の研究チームが2024年に行った調査では、SNS上で肯定的な反応を多く得ているユーザーは、そうでない人に比べて幸福度が約1.4倍高いという結果が報告されています。
ただし、この「デジタルな安心感」には表裏があります。過度にネットのつながりに依存すると、現実社会との接点が薄れ、孤独感が深まることもあるため、バランスを保つ意識が重要です。心理的安全性を守るためには、自分の発信や受信のペースを調整し、「居場所を持つ」ことと「逃げ込む」ことを区別する必要があります。
AIが導く「もう一人の理解者」という存在
AIやWebサービスの進化により、ネット上の「居場所づくり」はさらに多様化しています。AIチャットボットやバーチャルパーソナリティとの対話は、単なる便利な機能を超え、孤独やストレスの軽減に寄与するケースも増えています。
たとえば、米国で人気のAIチャットアプリ「Replika」は、ユーザーの心理状態に合わせた返答を行うよう学習し、2024年時点で世界で2000万人以上が利用しています。日本国内でも、AIキャラクターと会話できるWebサービスや、生成AIを活用したメンタルサポートアプリが登場し、「デジタルな共感」を提供する動きが広がっています。さらに、趣味や価値観でつながるオンラインサロンやDiscordコミュニティ、匿名で語り合う掲示板型SNSなども「現代の井戸端会議」として機能しています。AIが投稿を整理し、トピックを自動生成する仕組みにより、参加者同士がより快適に意見交換できるようになりました。
こうしたAIとの対話は、単なる娯楽ではなく、“自己理解の手段”として注目されています。言葉を投げかける過程で、自分の感情を整理し、思考を言語化する訓練にもなるからです。人との関係が希薄になりやすい時代において、AIは「聴いてくれる存在」として新しい役割を担い始めています。
もちろん、AIは万能ではありませんが、人が安心して感情を吐き出せる場所をつくるという点では、すでに多くの人の心を支える存在になっています。
居場所がもたらす豊かさと、これからの課題
ネットの中での居場所は、ただ孤独を癒やすだけでなく、自己表現の舞台にもなっています。YouTubeやnoteで自分の作品や考えを発信する人、X(旧Twitter)で意見を共有する人、オンラインサロンで学びを深める人など、その形はさまざまです。自分の経験や価値観を他者と分かち合うことは、承認欲求を満たすだけでなく、「自分の存在を再確認する行為」でもあります。それが継続されることで、新しいキャリアや人生の方向を見出す人も多く、ネットが人生の転機を生み出す時代に入ったと言えるでしょう。
しかし同時に、ネットの居場所は“居心地の良さ”が過剰になる危険もはらんでいます。アルゴリズムによって自分と似た意見ばかりが流れ込む「共感の閉鎖空間」は、視野の狭まりや対立の温床になることがあります。文部科学省の2024年調査では、10〜20代の約4割が「ネット上のつながりに疲れを感じる」と回答しており、情報の取捨選択や距離の取り方を教えるデジタルリテラシー教育の必要性が指摘されています。
それでも、ネットの居場所が多くの人にとって生きる力となっているのも事実です。家庭や職場とは違う空気の中で、自分を受け入れてくれる人がいる。その安心感は、誰かと共に生きていくうえで欠かせない要素です。
テクノロジーの発展が進むなかで、人と人とのつながりの形は変わっても、「誰かと分かち合いたい」という根源的な欲求は変わりません。ネットの中の居場所は、その欲求を柔らかく受け止める現代の新しいインフラと言えるでしょう。デジタル社会における居場所づくりは、孤独を減らすだけでなく、人の心に寄り添う新しい社会のかたちを描きつつあります。
- カテゴリ
- インターネット・Webサービス