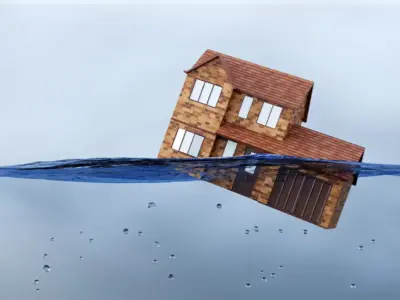「オルタナ伝承館対談」開催。異なる視点から、震災と原発事故の「記憶」と「伝承」を問い直す【福島県南相馬市】
福島県南相馬市にあるおれたちの伝承館で4月、「百年芸能祭」の一企画として「オルタナ伝承館 館長対談」が開催された。この対談に登壇したのは、ヒロシマ・ナガサキ・ビキニ・フクシマ伝言館やALPS処理汚染水放出差し止め訴訟に関わる丹治杉江さん、原子力災害考証館furusatoの里見喜生さん、そしておれたちの伝承館を拠点に活動する中筋純さん。コーディネーターを山内明美さんが務めた。それぞれが異なる立場で「被災地」に関わる中で育んできた視点を持ち寄り、「いかにして記憶を残し、継承するのか」という問いに向き合った。(以下敬称略、所属は座談会当時)
――自己紹介と伝承活動を始めた動機やそれぞれの施設を設立した思いをお聞かせください。
中筋:「無理じゃないか」と思いながらも、アーティスト仲間と手を組んで始めたのが、「おれたちの伝承館」です。原発事故について語るとき、「賛成か反対か」という二元論に持ち込まれてしまう。でも私は、そのイエスでもノーでもない「間(あわい)の世界」にこそ、人が何を感じるか、何を考えるかという大切な部分があると思っています。公的な施設が見せてくれる震災や事故の記録はとてもよくできている。でも、そこにある余白、つまり揺れ動いた感情や未来への願いは、民間だからこそ伝えられる。いろんな立場、いろんな表現が交わる場所で、訪れた人が心を震わせ、「私も話したい」と思えるような場を作りたいんです。
里見:私は2014年、水俣病歴史考証館を訪ねました。そこで、多様な立場の人の声を聞き、初めて水俣病の「実態」が実感として心に届いたんです。翌年、福島県田村郡三春町の「コミュタン福島」を見たとき、「これは本当に真実を伝えているのか?」と疑問が浮かびました。水俣での体験が頭をよぎり、「民の立場」で何かを伝えたいと強く思ったのです。震災当時のまま残る場所を残せないかと相談した双葉郡の自治体では「無理だ」と言われ、観光事業者からも「(いわき湯本温泉に)里見くんのせいでお客さんが来なくなる」と忠告されました。でも、私は「なかったことにする」のが一番イヤなのです。だからこそ、自分の場所と自分の資金で「原子力災害考証館furusato」を立ち上げました。私が伝えたいのは、ふるさとの本質。土や空気、景色、そこにいた人のこと。その喪失の意味を、次の世代へしっかりと語り継いでいきたい。
丹治:私は東京で映画制作に関わっていた頃に出会った方との出会いをきっかけに、いわき市に移住しました。2011年の原発事故では、自宅が30キロ圏外で避難指示は出なかったけれど、自主的に会津、そして県外へと避難。群馬県前橋市では「福島から来た人はお金をもらっているでしょ」とか、「家を買えるのは補償があるからでしょ」といった誤解を何度も受けました。ある保育園では、「福島の子は中学生まで生きられない、かわいそうね」と言った保護者もいました。そんな現実に、13年向き合ってきました。私たちは国の責任を問う裁判を起こしましたが、最高裁ではその責任を否定され、深い失望を感じました。それでも、「なかったこと」にしてはいけないという思いで、仲間と一緒に双葉郡の宝鏡寺の庭に「ヒロシマ・ナガサキ・ビキニ・フクシマ伝言館」をつくりました。長野にある戦没画学生慰霊美術館「無言館」にならい、私たちは語ることを選びました。事故の真実と、ふるさとを奪われた人たちの想いを、次の世代へつないでいく場として、これからもこの場所を守っていきたいと思います。
――今、福島に必要なこと、それぞれ足元で考えてきたこと、運営する中で考えてきたことについて、教えてください。
中筋:僕は「オルタナティブ」という名前をつけましたけど、本当は「アネックス」、つまり“もう一つの部屋”という意味を込めた場所なのです。福島の伝承活動には長く関わってきましたが、今いちばん必要だと思っているのは、知らない人を巻き込んでいくための新しいアプローチ。特に若い人にとって、原発事故の記憶ってどうしても“重くて灰色”に見えがちです。だからこそ、どう心を動かせるかを真剣に考えています。
震災後、土木によって整えられた場所に、花を咲かせるような活動をするのがアーティストの役割だと思ってきました。でも、国策でやってきた“華やかさだけのアート”では、肝心なものがガラスの下に押し込められてしまう。それじゃ駄目なのです。僕は広告の世界にもいたので、裏側の資金の流れや、操作される情報の仕組みにも敏感で。だから「おれたちの伝承館」って名前をつけて、検索で偶然たどり着いた人にも真実が伝わるように工夫しています。「福島は終わった」と思っている人に、どう驚きを届けるか。花で迎えて、展示で立ち止まらせる。そんな仕掛けを、福島で僕は続けています。
里見:僕が当主を務める旅館「古滝屋」は、増改築を重ねすぎて、まるで迷路みたいな建物になってしまいました(笑)。だから、お客さんがふとエレベーターで最上階に来て、看板を見て「なんだこれは」と、原子力災害考証館furusatoに迷い込んでくるんです。原発事故に関心があって来られる方もいますが、偶然の出会いから何かを感じて帰ってくださるのが一番うれしいですね。
あるとき、旅館を利用された家族のお父さんから電話がありました。夕食の時に、子どもが*「汐凪(ゆうな)ちゃんの場所が心に残った」って話したそうです。事故や避難という言葉を使わなくても、「命」や「大切な人に思いを伝えること」の意味が届いたんですね。それを聞いて、本当に胸が熱くなりました。
たとえ1人でも2人でも、心の奥に何かが届いていたらそれで十分。数じゃない。それが、今の僕の一番の原動力です。
丹治:「みんなちがって、みんないい」って、金子みすゞさんの言葉がありますよね。私が運営している伝言館も、まさにその精神でやっています。「今の福島第一原発ってどうなっているの?」「なぜ原発がここに建ったの?」という素朴な疑問に、真正面から向き合いたい。例えば、燃料デブリ(1号機から3号機の原子炉内で溶け落ちた燃料)。約880トンあるっていうけど、単位を変えると8億8000万グラム。で、いま取れているのはほんの0.7グラム。そういう現実を、ちゃんと理解したいという人は少なくないんです。事故の経緯、廃炉の現状、漁業者や住民の声、裁判の行方—理屈っぽいかもしれないけど、資料とともにしっかり伝えています。時には「頭が痛くなる」なんて言われるけど、「気持ちを整理できた」と壁に自分の考えを書いていく人もいる。そういう反応が、何よりの手応えです。
今、特に注目しているのはALPS処理水の問題です。「流しているだけで、投棄じゃない」と言い張る東電。けれど、不安を感じていること自体がすでに被害です。平穏な暮らしが侵されている現実を、法廷で、資料で、しっかり訴えていく。福島には感動や涙だけじゃなくて、怒りや問いも残していく必要がある。町ごとに小さくてもいい、資料館が広がるような未来を。誰もが話していい、そんな空気のある場所をつくっていきたい。それが、私の願いです。
――では、最後に今後の展望について一言ずつお願いします。
中筋:僕が一番大事だと思っているのは、やっぱり「伝えていく」ということ。伝承っていうと、どうしても“語る側”に意識が向きがちだけど、それを受け止めて、次の世代を連れてくる人―つまり、ちょっと“悪い大人”も必要なのですよね。去年、福島市内の高校生たちがここに来てくれました。でも、すんなり来られたわけじゃなかったのです。教育委員会の中には「中核派がいるかもしれない」とか言い出す人もいて、本番の数日前に校長先生がこっそり視察に来たんですよ(笑)。「いや、全然悪いことやっていませんから」とちゃんと説明して、「大丈夫ですね」と言ってもらえて、ようやく実現したという経緯がありました。
そうやって、ちょっとした“力学”も必要だけど、やっぱり最後は、そういう勇気ある先生の存在が大きいですよね。来てくれた生徒たちの中で、1人でも2人でも何かが心に引っかかれば、それで十分だと思っています。
里見:資料として配った新聞記事を、皆さんぜひ読んでいただきたいです。これは新潟日報の記者さんが、半年くらいかけて取材して、3月11日に出してくれた特集記事なのですけど、新潟も福島と無関係じゃないという視点で、本当に丁寧に書かれている。僕も最後に「福島を教訓にしてほしい」って言葉でコメントを締めさせてもらいました。ただ、難しいのは、本当に読んでほしい人―つまり、ちょっと距離を置いている人や、当事者意識が薄い人―ほど、なかなかこっちには来てくれない。どうやって、そういう人たちに足を運んでもらえるのか。それが今の大きな課題だと思っています。
丹治:活動拠点である「伝言館」の隣には「未来館」という学習スペースがあります。30人くらいが集まって映像を見たり、意見交換したりできる場所で、”宿坊”も併設しています。最近では、首都圏や関西の大学ゼミがそこに泊まって、最後にうちの館で1日学習して、反省会までやっていってくれるようになりました。学生と向き合うのは大変だけど、そんなふうに“学びの場”として使ってもらえるのは本当にありがたいことです。
ただ現実には、入館料も取っていないので、運営はほぼ年金と募金頼り。展示物の維持だけでもいっぱいいっぱいです。誰がこの場を次に継いでくれるのか、どうやって続けていくのか―課題は山積みです。仮に、浜通り全体をカバーするような大きな施設を作ったとしても、担い手がいなければ意味がない。10年後、いや、5年後すら見通せない状況です。だからこそ、細くても長く、続けていくことが何より大事だと思っています。皆さんのアイデアや協力が、この伝承の輪を広げる力になります。どうか、これからも一緒に考えていけたら、私は本当にうれしいです。
対談の最後、三人の言葉を聞きながら、私は不思議な感覚を覚えた。「語り続けることの意味」「伝えようとする人を支える大人の存在」「学びの場を守り抜こうとする覚悟」――そのどれもが、今この瞬間の言葉というより、未来に向けて差し出された“バトン”のように思えた。驚いたのは、福島の伝承の場が、決して「過去を封じ込める場所」ではなかったということだ。ここには、若者が来るのを待つだけでなく、連れてこようとする大人がいて、迎え入れようとする人がいて、何かを残そうとする意志がある。静かで、力強い営みだった。「細くても長く続けていくことが大事」という丹治さんの言葉が、いまも耳に残っている。たとえ数年先が見えなくても、それでも足を止めずに継いでいく。そこにあるのは「義務」ではなく、「希望」なのかもしれない。
この日聞いた声の一つひとつが、震災を知らない世代にも届いてほしい。そう願わずにはいられない時間だった。
*汐凪(ゆうな)ちゃんの場所
木村紀夫さんの次女・汐凪(ゆうな)ちゃん(当時7歳)は、地震直後、祖父と母がそれぞれ近所の児童館にいた汐凪ちゃんを迎えに行ったものの、3人は避難の途中で津波に巻き込まれたとみられている。しかし、捜索に向かった父・木村紀夫さんは、翌日の福島第一原発の爆発による強制避難指示で捜索に行けなくなる(祖父と母は4月に遺体で発見)。2016年、大熊町内の海岸で汐凪ちゃんが身につけていたマフラーと骨の一部が見つかり、DNA鑑定で汐凪ちゃんのものと確認。現在、考証館furusatoで、木村さんが再現した当時のがれきと共に、汐凪ちゃんの写真や遺品が展示されている。
参照:ヒロシマ・ナガサキ・ビキニ・フクシマ伝言館(福島県双葉郡楢葉町大字大谷字西代58番地の4 宝鏡寺境内)
原子力災害考証館furusato(福島県いわき市常磐湯本町三函208いわき湯本温泉 古滝屋9階)
https://furusatondm.mystrikingly.com
おれたちの伝承館(福島県南相馬市小高区南町2丁目23)
https://suzyj1966.wixsite.com/moyai
情報提供元:ローカリティ!
その魅力を共に愛する仲間を募れる住民参加型・双方向の新しいニュースメディアを目指しています。
- カテゴリ
- 大規模災害