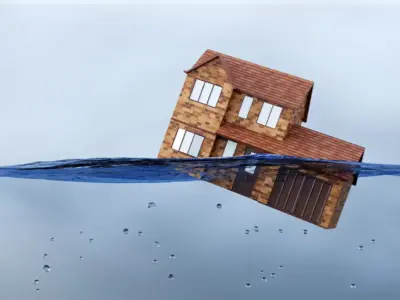復興予算と地域格差、被災地支援の公平性を問う

震災から年月が経過しても、被災地復興の歩みには地域ごとのばらつきが残っています。国は毎年、数兆円規模の復興予算を投じてきましたが、その分配の公平性には今も疑問が投げかけられています。災害からの再生は単なるインフラ復旧ではなく、人の暮らしや地域経済の再構築に直結する問題です。復興予算のあり方を見つめ直すことは、これからの防災・減災社会を築くうえで欠かせない視点といえるでしょう。
復興予算の偏りが生む地域格差
復興庁の公表資料によると、東日本大震災以降に計上された関連予算の総額は、2024年度までで約36兆円に達しています。被災地の道路や防潮堤、住宅再建に多くの資金が投じられた一方で、事業の採択状況を詳しく見ると地域間で顕著な差が生まれています。大都市圏や観光産業が集中する地域は、経済効果が見込める大型インフラ整備により優先的に予算が配分されているケースが多く、人的・技術的資源に乏しい小規模自治体では申請や計画策定の段階で遅れが生じやすい実情があります。
例えば、東北地方の沿岸部では自治体職員の人員不足が続き、2023年度時点で一部自治体の復興事業執行率は平均の約70%にとどまりました。国の制度は「公平な支援」を前提としていますが、結果として“申請能力の高い自治体が有利”という構造が生まれています。制度設計の段階から、こうした実務的な格差を想定した支援体制を整えることが求められます。
公平な支援とは何かを再定義する
公平性という言葉は、しばしば「平等な配分」と混同されがちです。しかし、真に公平な支援とは、それぞれの地域が抱える被害の性質や再建の条件を丁寧に考慮した上で、必要なところに重点的に資源を届けることではないでしょうか。
たとえば、観光地を抱える地域では宿泊施設の再建が最優先となり、農村部では農地や水路の修復が地域の生命線となります。にもかかわらず、現在の制度では予算申請のフォーマットが全国一律で、地域特性を反映しにくい側面があります。中小企業庁の報告によると、災害関連融資を受けた中小事業者のうち、完全に事業再建を果たしたのは約65%にとどまり、資材価格の上昇や人手不足が足かせになっています。こうした現場の声を反映し、被災規模ではなく“再建の難易度”を考慮した評価軸を導入することが、公平性の再構築につながるでしょう。
さらに、災害時に声を上げづらい人々—高齢者、障がい者、生活困窮世帯—への配慮も必要です。復興のスピードだけでなく、「誰が取り残されているか」に焦点を当てた支援体制が、公平な社会を築く基盤になります。
復興から地域再生へ、予算の使い方を変える
復興予算の本来の目的は、被災地の「生活と経済の再生」です。近年では防災・減災と地域活性化を一体で進める動きが見られ、福島県浜通りでは再生可能エネルギー関連の産業誘致により、新たな雇用が創出されつつあります。このように、災害を契機に新しい地域経済の形を模索する試みは、単なる復旧を超えた“再構築”の段階に入っているといえます。
しかし、その一方で課題も残ります。内閣府の調査によれば、復興事業の約6割が事業終了後の維持費を確保できず、施設が十分に活用されていないケースも報告されています。短期的なインフラ整備に偏らず、地域人材の育成や教育・医療・福祉への投資を増やすことが、長期的な自立につながります。復興は「元に戻す」ことではなく、「より強くしなやかな地域を築く」ことに方向転換する必要があります。
まとめ
復興予算の配分をめぐる議論は、単なる財政問題ではなく、日本社会の構造そのものを映し出す鏡です。どの地域にも平等なチャンスを与えることは理想ですが、現実には、制度の運用力や地域経済の体力によって結果が大きく異なります。これからの被災地支援には、単一の基準ではなく、地域ごとに柔軟なアプローチを取る視点が求められます。
公平性とは「全員を同じ場所からスタートさせること」ではなく、「困難の度合いに応じて寄り添うこと」です。災害の多い日本において、予算の分配を通して誰を、どのように支えるのか。その答えを探ることが、真の復興と地域の未来を支える第一歩になるはずです。支援の“平等”ではなく、“公正”を重視する姿勢が、これからの復興政策に必要とされるのではないでしょうか。
- カテゴリ
- 大規模災害