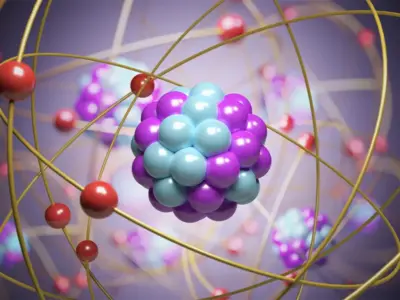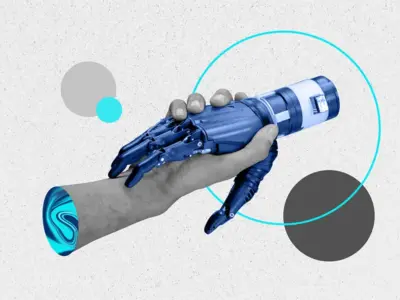国内ネットワーク事業者が直面する“海外ピアリングのリスク”と回避戦略の最前線

国内のインターネット利用は動画配信やクラウドサービスの普及によって増え続けており、それを支えているのが海外ピアリングという接続の仕組みです。国際トラフィック量は総務省の調査で年間約15%前後の増加が続いており、企業も個人も海外サービスを利用する機会が多くなっています。
国内ネットワーク事業者にとって国際接続は欠かせない基盤でありながら、その裏には地域差や規制、地政学的変動など、国内とは異なる条件が横たわっています。通信品質や安定性に影響する要因が複雑に絡むため、事業者はこの領域の判断に慎重になりがちです。
より良い接続環境を提供するためには、海外ピアリングに伴うリスクを正確に把握し、対応力を高める取り組みが欠かせません。
海外ピアリングに潜むリスクと、品質低下につながる要因
国内ネットワーク事業者が海外接続を検討する際、初めに意識するのがインフラ品質の違いです。欧米やアジアの主要IXは設備が整い安定した運用が期待できますが、地域によっては停電の発生頻度が高く、計画外のメンテナンスでトラフィックが揺らぎやすい環境も存在します。現地の規制状況によって帯域確保が制限される場合があり、国内側に責任がなくても応答時間が伸びるケースが起きています。
トラフィックの集中も深刻です。国際アクセスが増えるピーク時間帯には海外IXの混雑が発生し、国内のネットワークは正常でも遅延が起こります。一般的な国内通信が10ms前後であるのに対し、海外接続では100msを超える遅延になることもあり、業務利用では小さくない差として現れます。クラウド利用が標準化した現在、この乖離は企業システムの操作感にも影響する可能性があります。
地政学的リスクにも関係しており、海底ケーブルは国際情勢や自然災害の影響を受けやすく、2023年には太平洋側のケーブル障害で一部地域への遅延が通常の2倍近くになった例が報告されています。ケーブルは世界中に400本以上敷設されていますが、その多くが限定されたルートに集中しているため、障害の波及範囲は広くなりがちです。また、国際回線費用は地域差があり、為替の変動によって年間数%単位で費用が変わることがあります。契約期間が長くなるほどリスクが積み上がり、事業者にとっては慎重に検討すべき要素になるでしょう。
国内ネットワーク事業者が実践する回避戦略と安定化の取り組み
海外ピアリングのリスクを減らすため、国内ネットワーク事業者は複数の施策を組み合わせています。代表的なのが接続ルートの分散です。アジア・北米・欧州の複数IXへ接続し、障害発生時には自動で別ルートへ切り替える仕組みを用意しています。単一経路への依存を避けることで、海底ケーブル障害や地域の混雑が生じても品質の低下を抑えられます。
また経路選択の高度化も進んでおり、BGP最適化ツールを活用し、混雑を避けやすいルートを選択することで遅延の発生を減らします。クラウド事業者とのプライベートピアリングを増やす取り組みも効果的で、一般インターネットを経由しない経路が確保されるため、応答時間のばらつきが小さくなります。クラウドサービスの利用割合が高まる今、この方法の重要性は一段と高まっています。
現地パートナーとの連携体制も強まっているので、海外側の障害情報を即時に共有できる環境が整うことで、国内での対応が早まり、影響を最小限に抑えられます。IXごとの実測データを定期的に取得し、遅延傾向を可視化する取り組みも、障害予兆を早期に把握する助けになるでしょう。
安定した国際接続を支える今後の展望
国際トラフィックが増え続けるなか、国内事業者が海外ピアリングに向き合う姿勢は今後も重要性を増します。アジア太平洋地域では、2026年までに10本以上の新規海底ケーブルが開通予定とされており、経路の多様化が進む見込みです。これにより、国内ネットワーク事業者が選択できる接続パターンは増え、障害発生時の対応力も向上すると考えられます。
AIによる経路監視の高度化も期待されており、兆候を検知して早期に迂回経路へ切り替える仕組みが現実味を帯びています。ログデータの解析が進めば、過去の障害傾向からリスクの高い時間帯を予測することも可能になります。
海外ピアリングは難易度が高い領域ですが、事業者が工夫を積み重ねていけば安定性を保ちやすくなります。複数経路の確保、技術的な最適化、現地連携の強化などを組み合わせることで、利用者に安心して使える通信環境を届けられます。海外接続が当たり前になった今、この取り組みは国内インターネット基盤の信頼性を支える重要な工程と言えるでしょう。
- カテゴリ
- [技術者向] コンピューター