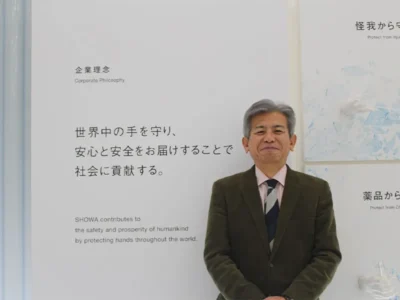“共感が先、販売は後”で伸びる、長期ブランド戦略論
現代のブランド戦略で重要性を増しているのが「パーパス」、つまり企業が社会に存在する理由や意義です。商品やサービスの差別化が難しくなるなか、消費者は単に価格や機能を比較するだけではなく、「そのブランドは何を大切にし、どのような社会を目指しているのか」という問いを投げかけています。企業がこの問いに真摯に応え、生活者の価値観と重なる部分を示すことができれば、信頼と共感が生まれます。
“共感が先、販売は後”という考え方は、この流れを象徴しています。まずは共感を軸に関係性を築き、その結果として購買が自然に積み重なっていく。販売を急がず、信頼を育てる姿勢こそがブランドの持続的な成長を支える基盤となります。
SNSとECが形づくる新しい消費心理
SNSは今やブランドにとって単なる宣伝の場ではなく、パーパスを生活者と共有する大切な接点です。人々は企業の公式発信だけでなく、実際のユーザーによる投稿や意見を通してブランドを評価する傾向を強めています。国内の調査でも、7割を超える利用者が購買前にSNSでの声を参考にしており、発信される情報の信頼性は「企業からの一方的な広告」よりも「生活者同士の対話」に移っています。
さらにECの領域では、ブランドの姿勢を体験として伝える試みが広がっています。たとえば環境保全をパーパスに掲げる企業が、商品の購入ごとに寄付や環境活動へ直接つなげる仕組みを整えれば、消費者は「買うことそのものが社会的な意義を持つ」と感じるようになります。AIを活用したレコメンド機能も、過去の購買履歴や関心に基づいた提案を行うことで、顧客に「自分の価値観を理解してくれるブランド」という印象を与えています。こうした体験は積み重なるほどに、消費者を一度限りの購入者から長期的な支持者へと育てていきます。
経済変動の中で強まる共感の価値
不安定な経済状況の中で、人々は価格の安さに目を向けつつも、安心感を与えてくれるブランドを求める傾向を示しています。国内の調査によれば、62%の消費者が「価格が高くても信頼できるブランドを選ぶ」と答えており、その背景には共感に基づく心理的な安心感があります。
ここで重要なのは、信頼の源泉が単なる製品の品質や機能だけではないという点です。企業が示すパーパスが社会的意義を持ち、生活者自身の価値観と響き合うとき、その信頼はより強固になります。環境問題や地域社会への貢献といった取り組みを一貫して発信し続ける企業は、経済状況に左右されにくい支持基盤を形成します。消費者にとって「購入を通じて社会に良い影響を与えられる」という実感は、価格や利便性を超える大きな動機となるでしょう。
共感を育てるブランド戦略の実践
共感を育てるためには、まずブランドが持つパーパスを明確に定義する必要があります。それがあいまいであれば、消費者の心に届くことはありません。存在意義をわかりやすく言語化し、未来に向けてどのような社会像を描いているのかを示すことが、信頼を築く第一歩となります。
次に重要なのは、生活者との対話を販売活動と切り離して考えることです。SNSで顧客の声に丁寧に応じたり、ユーザー投稿を公式に取り上げたりする姿勢は、消費者に「理解されている」という感覚を与えます。さらにAIを活用すれば、生活者がどのような価値観やストーリーに反応しているのかを把握でき、より的確に共感を設計することができます。
このように共感を中心に据えた取り組みを積み重ねれば、販売はその延長線上に自然と生まれます。短期的な販促に頼らず、長期的な視点で信頼を育てていくことが、激しい競争環境の中でブランドを強くする道筋となります。
まとめ
“共感が先、販売は後”という考え方は、今後のブランド戦略における指針といえます。SNSやECの普及、AIの進化によって、消費者の心理はこれまで以上に共感を基盤とする方向に変化しています。短期的な販促だけに依存するのではなく、人々の感情や価値観に寄り添いながら信頼を築いていくことが、長期的なブランド成長を支える力となります。
消費者が選ぶのは、機能や価格だけではなく、共感を通じて心を動かしてくれるブランドです。その共感を積み重ねていくことで、ブランドは単なる商品提供者から、生活者にとってかけがえのない存在へと進化します。未来の市場で生き残り、成長し続ける鍵は、販売よりも先に共感を大切にする姿勢にあるのではないでしょうか。
- カテゴリ
- ビジネス・キャリア