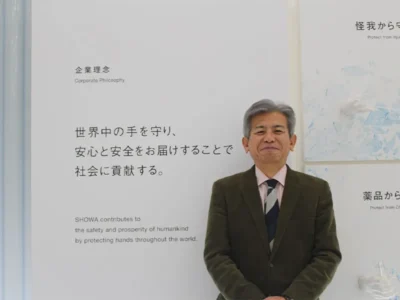ペットイベント市場の拡大が示す新しい消費の潮流

日本では、ペットが家族の一員として迎えられることが一般化し、ペットと過ごす時間に付加価値を求める人が増えています。その動きに呼応するかのように、ペット関連イベント市場は着実に成長を続けています。全国規模の展示会から地域コミュニティによる小さな催しまで、多彩なイベントが各地で開催され、消費者は単なる買い物以上の「体験」と「共有の場」を求めて集まっています。
矢野経済研究所の調査によると、2023年の国内ペット関連市場は1兆7,800億円に達し、全体の中でもイベントや体験型サービスの比重が増しています。数字が示すのは、消費者がモノよりもコトを重視するようになり、ペットとの時間をより充実させたいという意識の高まりです。こうした背景はイベント市場の拡大を強く後押ししているといえます。
情報発信が後押しするイベント市場の拡大
ペットイベントの成長を支えているのは、情報発信の仕組みの変化です。SNSや動画共有サービスでは、参加者がイベントでの体験を写真や動画で発信し、その場の雰囲気がリアルタイムで拡散されます。特定のハッシュタグを使った投稿は数十万件を超えることもあり、次の来場を促す大きな動機になっています。
従来型メディアの影響力も依然として強く、大規模イベントのテレビ中継や雑誌特集は幅広い層に情報を届けています。2024年に幕張メッセで行われた「ペット博」は、その効果を象徴する事例であり、12万人を超える来場者を記録しました。市場規模が広がっているだけでなく、カルチャーとして定着しつつあることを示す出来事といえます。
消費者行動から見える特徴
消費者の行動を観察すると、イベントに求められているのは単なる購買体験ではなく「特別な体験」であることが浮かび上がります。ペットと一緒に参加できるフォトブースや専門家によるセミナー、健康チェックやトレーニング体験など、学びと楽しみを組み合わせた企画は高い人気を集めています。実際の調査では、来場者の7割が「日常では得られない体験が参加理由になった」と答えています。
限定性も購買行動を刺激する大きな要素です。ある大手ペットブランドが会場限定で販売した商品は、通常品の1.5倍の速度で売り切れ、SNSでは数千件規模の投稿が広がりました。イベント体験と購買が密接に結びつき、情報発信によって再び循環するという新しい消費の流れが生まれているのです。
また、参加者の65%以上が「イベントを通じて新しい商品やサービスを知った」と回答しており、イベントは情報収集の場としても重要です。会場で得た知識や体験は消費者の次の選択に直結し、購買意欲を高める効果を持っています。
マーケティングに広がる新しい可能性
ペット関連イベントは、企業や自治体にとっても重要なマーケティングの舞台となっています。来場者が体験するプログラムを通じてブランドの価値を伝えることは、従来の広告以上に深い印象を残します。健康診断サービスや飼育相談コーナーを提供すれば、単なる販促を超えて「役立つ存在」として記憶される可能性が高まります。さらに、マイクロインフルエンサーとの連携も効果的です。フォロワー数が少なくても熱心なコミュニティに影響力を持つインフルエンサーの発信は、共感を伴って拡散されやすく、購買行動を促す力があります。費用対効果の観点からも注目度は高まっています。
市場の予測では、ペット関連産業全体が年率3〜5%の成長を続けるとされ、体験型イベントの重要性はさらに大きくなると見込まれています。消費者行動の分析を基盤に、文化的な要素を取り込んだ戦略を展開できるかどうかが、次の成長段階に進む鍵となるでしょう。
まとめ
ペット関連イベント市場は、趣味や娯楽の領域を超えて、生活文化そのものを豊かにする場へと発展しています。SNSを通じた共有は来場者の体験をさらに広げ、購買行動やブランド認知に直結しています。消費者は商品を手に入れるだけでは満足せず、ペットとともに価値ある時間を過ごし、その体験を他者と共有することに大きな意味を見出しています。
今後の市場拡大には、体験型コンテンツのさらなる充実、デジタルとリアルを融合させた取り組み、そして消費者の価値観に寄り添ったマーケティングが不可欠です。ペットをめぐるカルチャーはますます多様化し、それに応じた戦略を持つ企業や自治体が新しい成長機会をつかむでしょう。ペットイベントは単なる商業活動を超え、人とペットの絆を深める場として、今後も社会に大きな影響を与え続けていくと考えられます。
- カテゴリ
- ビジネス・キャリア