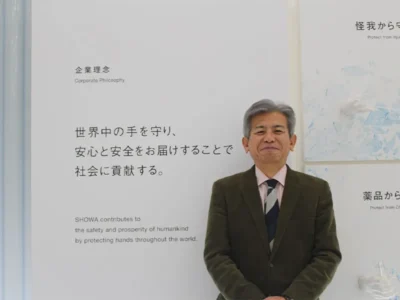副業解禁が生む新しいキャリア形成の可能性

日本企業の働き方は、ここ数年で大きな変化を遂げています。かつては一つの会社で定年まで勤め上げることが理想とされてきましたが、人口減少や経済の不確実性が増す中で、そのモデルは揺らぎ始めました。とりわけ注目されているのが「副業解禁」です。政府の後押しや企業の制度改革によって副業を選択する人が増え、個人のキャリア形成の在り方はより多様で柔軟なものへと移行しています。
副業解禁が広がる背景
副業をめぐる制度が注目されるようになったきっかけの一つは、2018年に政府が働き方改革の一環として副業・兼業を推進し、モデル就業規則から「副業禁止」の条文を削除したことでした。それ以降、企業側の意識も変化し、厚生労働省の調査によれば2023年には副業を認める企業が全体の約6割に達しています。2018年当時は2割に満たなかったことを考えると、急速な広がりといえるでしょう。
背景には労働市場の構造的変化があります。正社員の給与水準が伸び悩む一方で、デジタル技術の進展により、在宅やリモートでできる仕事が増えました。クラウドソーシングやオンライン教育の普及は、副業に取り組みやすい環境を整えています。リクルートワークス研究所の調査によれば、2024年時点で正社員の35%が副業を希望しており、特に20代後半から30代前半の若手世代に意欲が高いことが示されています。副業は「余裕がある人の選択肢」から「一般的なキャリア形成の一環」へと変化しつつあります。
キャリア形成における新しい価値
副業が注目される理由は、単に収入を補うだけではありません。複数の仕事を通じて新しいスキルを習得したり、異なる業界に触れたりすることで、自身の市場価値を高める効果が期待できます。たとえば、営業職の人がデジタルマーケティングの副業に挑戦すれば、データ分析や広告運用の知識を身につけられ、本業の営業活動にも応用できます。
さらに、キャリアのリスク分散にもつながります。従来は一社への依存が大きく、会社の業績に個人の人生が左右されがちでした。副業を持つことで複数の収入源を確保でき、景気変動や突然のリストラに備えることができます。フリーランス協会の2024年調査では、副業を行っている人の約40%が「将来的に独立を視野に入れている」と回答しており、働き方の多様化が確実に進んでいることが分かります。
このような動きは「ポートフォリオキャリア」という概念とも重なります。一人の人間が複数の役割を持ち、それぞれの経験を相互に活かすことで長期的にキャリアを成長させていく考え方です。欧米では広く浸透しているスタイルで、日本でも少しずつ受け入れられ始めています。
日本企業が直面する課題
副業解禁の流れは歓迎される一方で、企業にとっては新たな課題も突きつけられています。まず、労働時間の管理が挙げられます。総務省の統計によれば、副業従事者の平均労働時間は週10時間程度ですが、繁忙期には20時間を超える人も存在します。長時間労働が常態化すれば本業への集中力が低下し、過労リスクが高まります。企業は従業員の副業状況を把握し、無理のない働き方を支援する必要があります。
また、情報管理の問題があります。同業界で副業をする場合、機密情報の持ち出しや利益相反のリスクが避けられません。経団連の調査によると、副業を認めている企業の約7割が「事前申請制」を導入しており、透明性の確保に努めています。ルールが曖昧なまま副業を容認すれば、トラブルの火種となりかねません。
そして、評価制度の見直しも必要です。副業を行う社員の成果をどのように評価し、本業の昇進や給与に反映させるかは、まだ議論が始まったばかりです。副業経験を評価に活かす仕組みが整えば、むしろ人材の流出を防ぎ、組織全体の競争力強化につながる可能性があります。
副業が描く未来の働き方
副業解禁は、個人にとっても企業にとっても大きな可能性を秘めています。社員が社外で得たスキルや人脈を本業に活かすことで、組織の知識基盤が強化され、新しい事業機会を生み出すことも可能です。実際に、副業制度を導入したある大手IT企業では、社員の離職率が3年間で15%から8%へと半減した事例が報告されています。副業が社員のモチベーション向上と定着率改善に寄与した好例です。
今後は「副業=収入の補助」という従来のイメージから、「副業=自己投資」という認識へと移行していくことが重要になります。語学力を高めるために翻訳の副業を始める人や、将来の起業を見据えて小規模な事業を試みる人など、多様な選択肢が広がっています。企業も社員の副業を制約するのではなく、社内で共有できる学びとして歓迎する姿勢を示すことが、競争力の強化につながります。
副業解禁が社会に定着すれば、働き手は自分らしいキャリアを築き、企業は多様な知識と経験を取り込みながら新しい価値を創出する好循環が生まれます。その先に描かれるのは、画一的な「会社人間」ではなく、複数の顔を持ちしなやかに働く人々が共存する未来です。
- カテゴリ
- ビジネス・キャリア