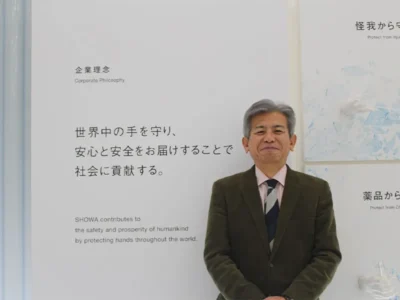賃上げムードの裏で中小企業が直面する新たな試練とは

賃上げの機運が高まり、ニュースや政策発表では「賃金上昇」「好循環」という言葉が頻繁に聞かれるようになりました。しかし、その華やかな見出しの陰で、中小企業は静かに苦境に立たされています。原材料費の高騰、円安による輸入コストの増大、そして人件費の上昇が重なり、経営の基盤が揺らいでいるのが現実です。大企業の賃上げが景気回復の象徴として扱われる一方で、地方の事業者や製造業の現場では「賃上げをしたくてもできない」という声が絶えません。
賃上げの波に取り残される中小企業
政府の賃上げ要請を受け、2025年度の賃上げ率は中小企業で平均4.48%に達する見通しです(帝国データバンク調査)。ベースアップを実施する企業は全体の56.1%と、表面的には「賃上げの定着」が進んでいるように見えます。しかし、実際に6%以上の賃上げを計画している企業は9.1%にすぎず、34.6%の企業は「持続的な賃上げは難しい」と回答しています。
賃上げを阻む最大の要因は、原材料費や人件費の上昇を価格に転嫁できない構造です。とくに下請け企業や地域密着型の中小事業者は、取引先との力関係が弱く、価格交渉の余地が限られています。2024年度には全国平均で最低賃金が51円引き上げられましたが、それに伴うコスト上昇を販売価格に反映できた企業は全体の半数以下にとどまります。さらに、人材の確保と育成にも課題があります。人手不足を背景に求人広告費が上昇し、採用しても早期離職が相次ぐケースも見られます。結果として、賃上げの意義を理解しつつも、経営の持続性を守るために慎重な姿勢を取らざるを得ない企業が増えています。
「賃上げをしないと人が来ない」「賃上げをすると経営がもたない」という二律背反に直面する中小企業の姿は、今の日本経済の歪みを象徴しています。
円安がもたらす新たな格差構造
賃上げを阻むもうひとつの要因が、円安によるコスト上昇です。2024年の為替レートは一時1ドル=160円台を記録し、エネルギー・原材料価格の上昇が中小企業の収益を圧迫しました。中小企業庁の調査では、円安によって「原材料の仕入価格が上がった」と回答した企業が全体の約6割にのぼり、そのうち約半数が「価格転嫁がほとんどできていない」と答えています。
大企業の場合、海外売上比率の高さが円安による収益押し上げ要因になりますが、中小企業の多くは国内市場中心です。みずほリサーチ&テクノロジーズの試算では、円安が大企業の営業利益を平均1.9%押し上げる一方、中小企業では1.3%押し下げる影響があるとされています。この差は、為替変動が単なる経済指標ではなく、経営格差を拡大させる要因となっていることを示しています。
こうした状況の中で、仕入先の多様化や為替リスクヘッジを進める中小企業も出てきました。しかし、金融知識や取引ネットワークの差から、こうした対策を講じられる企業は一部に限られます。円安を「輸出競争力の向上」と単純に喜べない理由が、ここにあります。
支援策が届かない「制度の壁」
政府は賃上げを促進するため、「中小企業向け賃上げ促進税制」などの支援策を用意しています。この制度では、給与総額を一定割合以上引き上げた企業が、最大45%の法人税控除を受けられる仕組みです。しかし、制度を活用している中小企業は限定的です。
その理由は、要件の複雑さにあります。教育訓練費を前年度比5%以上増加させることや、経営計画書の提出といった条件を満たす必要があり、人的リソースの少ない企業には大きな負担となります。手続きの煩雑さを理由に利用を断念する事例も少なくありません。税制支援を受けても即座に資金繰りが改善するわけではありません。賃上げは「現金流出」であるのに対し、税控除は「翌年度以降の減税効果」であり、タイムラグが存在します。このギャップが、資金余力の乏しい企業には致命的となる場合があります。
経済政策が掲げる「賃上げによる経済循環」を実現するには、制度設計の簡素化や即効性のある支援が不可欠です。中小企業が制度を活用しやすい環境を整えることこそ、政策の実効性を高める第一歩といえるでしょう。
企業が取るべき生存戦略とは
厳しい環境の中でも、道は閉ざされていません。いくつかの中小企業は、賃上げを「経費」ではなく「投資」として位置づけ、積極的に改革を進めています。
まず、生産性を高めるためのデジタル化投資が注目されています。クラウド会計や在庫管理システム、AI受注分析の導入によって業務効率を改善し、同じ人員でより多くの価値を生み出す体制を整える企業が増えています。これにより、労働生産性が10〜20%向上した事例もあります。
また、報酬体系の見直しも効果的です。給与全体を一律に引き上げるのではなく、スキルアップ支援や成果連動型のボーナス制度を導入し、従業員のモチベーションを高める方法が採られています。柔軟な勤務制度や在宅勤務の導入も、働きやすさの向上と採用力の強化につながっています。価格転嫁の難しさを補うために、ブランド力の強化や付加価値創出に取り組む企業もあります。技術力や地域性を前面に出した製品開発を行い、単なる価格競争から脱却する動きが広がっています。こうした取り組みは、短期的な利益には直結しなくても、長期的な経営基盤の強化につながります。
まとめ:賃上げの時代に問われる「経営の底力」
賃上げが社会的ムードとして広がる今こそ、中小企業は自らの経営力を問われています。賃上げは単なる人件費の上昇ではなく、企業の信頼と人材確保に直結する経営課題です。持続的に賃上げを実現するためには、デジタル化による効率化、取引構造の見直し、そしてブランド価値の向上が欠かせません。政策や支援制度に頼るだけではなく、現場主導の改善を積み重ねることが、これからの中小企業の生存条件となります。
賃上げムードの中で流されるのではなく、流れを自らの成長へと変える視点が求められています。経営環境が厳しさを増す今こそ、「人を大切にする経営」が真価を問われる時代です。
- カテゴリ
- ビジネス・キャリア