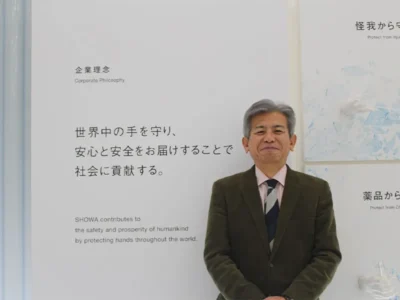働き方改革再評価、選ばれる企業の条件とは
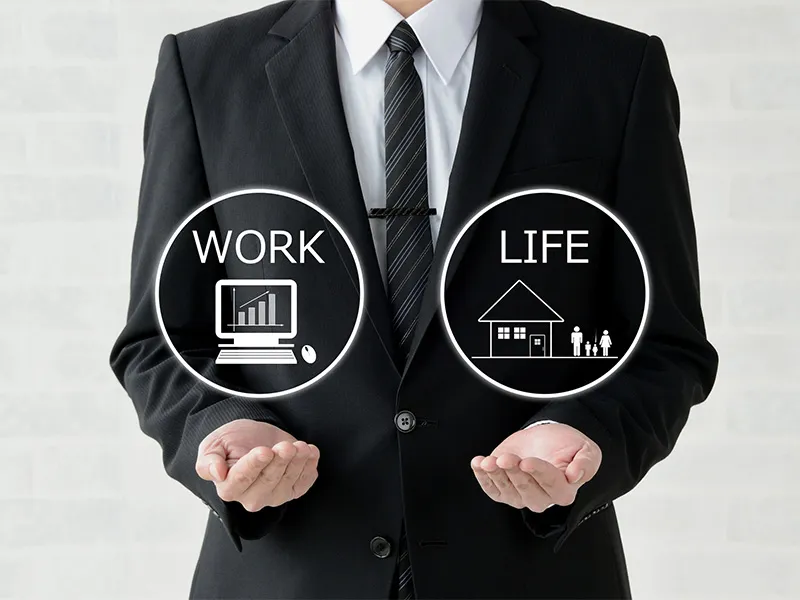
働き方改革は「導入したかどうか」から「従業員が実際に使えているか」へ、評価軸がはっきり移りました。採用市場では求人票の文言よりも、柔軟な制度が日常運用として根づいているか、評価と賃金が納得できるか、そしてスキルを磨ける環境かが問われています。転職・副業・リモートといった選択肢が広がった今、働く人は企業を吟味する立場にあります。だからこそ企業は、制度の棚卸しと運用の質の引き上げを同時に進める必要があります。
制度があるだけでは「働きやすさ」は生まれない
働き方改革が掲げる目的は、長時間労働の是正や柔軟な働き方の実現、公正な待遇を通じた生産性の向上にあります。時間外労働の上限規制、有給休暇の取得義務化、同一労働同一賃金といった制度は、多くの企業に導入されました。しかし、実際に制度が「使われているか」という点では課題が残ります。連合の調査によると、時間外労働の上限規制を「内容まで理解している」と答えた人は68.9%にとどまり、特に20代以下では理解が浅い傾向があります。勤務間インターバル制度を知っていると答えた人は38.4%程度であり、制度そのものが浸透していない現実が浮かび上がります。
形だけの制度整備では、従業員の満足や定着にはつながりません。制度の存在よりも、それが「使いやすいか」「心理的に使える雰囲気があるか」が問われています。上司やチームの理解が得られない環境では、有給休暇もテレワークも形骸化してしまいます。つまり、制度が整っているかよりも、職場文化がそれを支えているかが本質的な課題なのです。また、賃金格差も見過ごせない問題です。労働政策研究・研修機構の報告では、非正規雇用の賃金は正社員の約63%にとどまっています。雇用形態の違いが待遇やキャリア機会の差に直結している状況は、従業員の意欲を削ぐ要因になっています。働き方改革が進んでも、賃金や評価の公平性を確保できなければ、従業員の信頼は得られません。
「選ばれる企業」は何を備えているか
働き方改革の再評価が進む背景には、労働市場そのものの変化があります。リモートワーク、副業、フリーランスなどの多様な働き方が定着し、企業に属することが「唯一の選択肢」ではなくなりました。結果として、優秀な人材は働く場所を自ら選び、企業に求める基準も変化しています。
株式会社あしたのチームの調査では、求職者が企業を選ぶ際に重視する項目の上位は「柔軟な働き方」「成果に見合った報酬」「スキルアップの機会」でした。特にリモート勤務の自由度や副業制度の有無は、若年層にとって重要な判断材料となっています。
一方、企業にとっては“人材の奪い合い”が日常化しています。単に給与を上げるだけでなく、働く人が「ここで成長できる」と感じる環境づくりが不可欠です。柔軟な勤務制度やフレックスタイム制度を運用していても、実際に上司が利用を認めない雰囲気があれば、それは制度が機能しているとは言えません。制度よりも「使いやすさ」「心理的安全性」が問われる時代に移行しているのです。
世代と職種が求める「理想の働き方」
企業が選ばれる条件は、世代や職種によっても異なります。20〜30代の若手層は、ワークライフバランスやキャリア形成を重視します。残業の少なさや有休取得率だけでなく、「自分の意見が尊重されるか」「挑戦の機会があるか」といった点を重要視する傾向があります。
30〜40代の中堅層になると、評価制度や報酬の透明性が重視されます。努力が正当に報われない環境では離職率が高まりやすく、特に成果を可視化できる人事制度が整っている企業ほど、従業員満足度が高いという傾向が見られます。50代以上のシニア層は、柔軟な勤務形態や再雇用後の働き方に関心を寄せています。定年延長制度、副業許可、リスキリング支援など、人生100年時代を見据えた働き方の選択肢が重視されるようになっています。
職種別に見ると、エンジニアやデザイナーなどのクリエイティブ職ではリモート中心の働き方が浸透している一方、営業や接客業では対面業務が多く、柔軟性の確保が課題です。業種特性を踏まえた制度設計がなければ、従業員の不満を解消することはできません。
働き方改革の「再評価」から「再構築」へ
今、企業に求められているのは、制度を再評価するだけでなく、働き方を再構築する姿勢です。単に「残業削減」や「リモート推進」にとどまらず、個人のキャリア支援や学び直しを企業戦略の一部として位置づけることが求められます。
経済産業省の調査によると、リスキリングに投資している企業の売上成長率は平均で1.5倍高いという結果が出ています。社員のスキル成長が企業価値の向上に直結していることは明らかです。さらに、働く人々が安心して意見を述べられる「心理的安全性」を確保する文化も重要です。失敗を恐れずに挑戦できる環境が、イノベーションや生産性向上を生み出します。こうした内面的な改革こそが、企業の持続的成長を支える基盤となります。
選ばれる企業になるためには、外向けのブランド力だけでなく、内側からの信頼づくりが欠かせません。採用サイトや広報活動で「制度」を発信するだけではなく、実際に働く社員の声やキャリア事例を可視化し、「この会社で働きたい」と思える実感を届けることが大切です。
まとめ:働き方改革の“次のステージ”へ
働き方改革の目的は、単なる労働時間の短縮ではなく、働く人が誇りと幸福を感じられる社会の実現にあります。いま求められているのは、制度の再整備ではなく、働く人と企業の関係性を再定義することです。選ばれる企業とは、柔軟な制度を形だけでなく実際に運用できる企業、公正な評価制度を持つ企業、そして従業員が学び・成長できる場を提供する企業です。これらを総合的に実現できたとき、働き方改革は「義務」ではなく「文化」として根づくでしょう。
改革の目的は、企業の効率化ではなく、働く人が誇りをもって生きられる環境を作ることです。企業がその原点を見失わずに歩みを続けるとき、働き方改革は真の意味で“実を結ぶ文化”として定着していくでしょう。
- カテゴリ
- ビジネス・キャリア