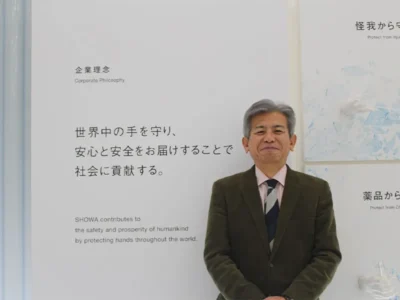AI採用面接の普及が進む中 “人を見る目”は誰が持つのか
技術が見抜けない“人間らしさ”の行方
AIを活用した面接選考が広まりつつある現在、企業はますます短時間で大量の応募者をふるいにかけることが可能になりました。発話内容や表情、声の抑揚、さらには語彙の傾向までもがデータ化され、候補者の「適性」や「性格特性」を数値で示す仕組みが一般化しつつあります。経済産業省の報告によると、2024年時点で国内企業の約2割が採用プロセスの一部にAIを導入しており、5年以内には半数を超える見込みです。
企業にとってAIは効率化の象徴であり、膨大な応募者を短時間で評価できる利便性があります。しかし、その裏で問われているのが、「人を見る目」をどのように保ち続けるかという本質的な課題です。機械が候補者の“数値化された印象”を示すようになった今、人事担当者の直感や経験、そして人間的な洞察はどこへ向かうのでしょうか。
効率の裏側に潜む評価のゆがみ
AI面接の導入目的は、判断基準を標準化し、評価のばらつきを減らすことにあります。従来の面接では、面接官の主観や感情が影響しやすく、同じ候補者でも担当者によって評価が分かれることがありました。AIはこの属人的なばらつきを補い、定量的な視点を加えることで公平性を高めると期待されています。
しかし、AIが学習するのは過去の採用データであり、そのデータに偏りがあれば結果も偏ります。かつて米Amazonが導入した採用AIでは、過去に男性社員が多かった履歴を学習した結果、女性候補者を低評価する傾向が生じ、最終的にシステムが撤廃されました。この事例は、AIが効率化の道具である一方で、人間の偏見を拡大させる危うさを示しています。
また、AIのアルゴリズムがどのように評価を導き出しているかを説明できない「ブラックボックス化」の問題も浮上しています。応募者から「なぜ不合格になったのか」と問われても、担当者が十分に説明できない状況が生まれているのです。公平性を守るはずのAIが、逆に透明性を損なうリスクをはらんでいます。
数字では測れない“人間の余白”
AI面接では、言葉の使い方や声の調子、視線の動きなどが数値化され、スコアとして提示されます。しかし、面接で表れる表情や話し方は、その人の状況や文化的背景、心理的状態によって大きく変化します。たとえば、初めてのオンライン面接で緊張する学生や、通信の遅延で間の取り方が不自然になる応募者など、AIには読み取れない文脈が多く存在します。加えて、応募者の中には「AIに好印象を与える受け答え」を学習し、意図的に採用されやすい話し方を身につける人も増えています。AIの評価ロジックを逆手に取ることで、高得点を狙うような“戦略的面接”が一般化すれば、面接の本質が形骸化しかねません。
こうした中で、最終的な判断をAIに委ねるのではなく、人間の観察力を交えて候補者の本質を見抜くことが重要になります。数字では示せない“余白”をどう評価するか——その視点こそ、AI時代の採用における新しいテーマです。
人事の役割は「判断者」から「通訳者」へ
AIが面接データを解析し、スコアを提示する時代において、人事担当者の役割は大きく変わりつつあります。これまでのように「評価を下す存在」ではなく、AIが示すデータを文脈に沿って解釈し、人間の感覚で補正を行う“通訳者”の役割が求められています。たとえば、AIが「自己表現力が低い」と判定した応募者が、実際にはチームのバランスを保つ協調性に優れている場合もあります。逆に、AIが高評価をつけた候補者が、組織文化に馴染まず早期離職するケースもあり得ます。このようなズレを埋めるには、データを鵜呑みにせず、数字の背後にある人間らしさを読み取る力が不可欠です。
最近では、AI面接の結果と人事担当者の最終判断の差異を分析し、アルゴリズムの精度を検証する企業も出てきました。PwC Japanの調査によると、AIを導入している企業の約65%が「最終判断は人間が行う」と回答しており、デジタルと人的判断を両立させる“ハイブリッド採用”が主流になりつつあります。
まとめ――“人を見る目”を技術とともに磨く
AIが採用の現場に浸透することは避けられません。むしろ、その流れを拒むよりも、どのように共存させるかが問われています。企業が行うべきは、AIを「選別の機械」として使うことではなく、候補者の可能性を多面的に引き出すための“補助装置”として位置づけることです。採用において本当に重要なのは、企業が「どんな人と働きたいか」を明確に定義し、その価値観をAIの設計やデータに反映させることにあります。そして、AIが提示する結果をそのまま採用判断に使うのではなく、人事がその背景を理解し、組織の文化や将来性と照らし合わせながら最終判断を下すことが望ましいでしょう。
AIは完璧な判断者ではありませんが、正しく使えば“人を見る目”を支えるパートナーになり得ます。技術の力と人の洞察を重ね合わせること。それが、これからの時代に求められる「人を活かす採用」のあり方ではないでしょうか。
- カテゴリ
- ビジネス・キャリア