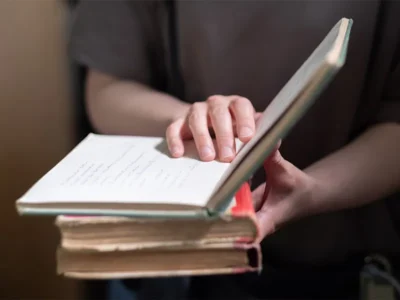親として知っておきたい“育児中のマナールール”

子どもが生まれてからの日々は、慌ただしくも愛おしい時間の連続です。しかし、子どもが成長するにつれて、周囲との関係や公共の場でのふるまいに悩むことも増えてきます。そんなとき、親としてどのようにふるまい、どのように子どもと向き合えばよいのでしょうか。社会の一員として、子どもが健やかに育つためには、親自身がマナーやルールを理解し、それを日常の中で自然に伝えていくことが求められます。
挨拶はすべての人間関係の入り口
子どもにとって、最初の社会との接点は家庭です。そしてその中で学ぶ「挨拶」は、人間関係の第一歩と言えます。たとえば、毎朝「おはよう」と笑顔で声をかけること、買い物先で「ありがとうございます」とお礼を伝えること、友だちとの遊びで「ごめんね」と謝ることなど、一つひとつが礼儀を育てる大切な習慣となります。
子どもは親の背中を見て育つと言われるように、大人が丁寧に挨拶する姿を見せれば、それは自然と子どもに伝わっていきます。たとえ幼い子どもでも、何度も繰り返すことで挨拶が身につき、やがて自分から言葉を発するようになります。
公共の場では「静かに」よりも「周囲への配慮」
電車の中や病院の待合室、図書館などでは、静かな環境が求められます。とはいえ、子どもに「静かにして」と一方的に注意するだけでは、本質的な理解にはつながりません。重要なのは「なぜ静かにすべきなのか」を、子どもの年齢に合わせた言葉で丁寧に説明することです。
電車で大きな声を出しそうになったときには、「今はたくさんの人が疲れていて、静かに過ごしたいと思っている時間なんだよ」と具体的に状況を伝えることで、子どもはその場の空気を感じ取る力を育むことができます。
しつけは“怒る”ことではなく、“理解を促すこと”
育児のなかで、子どもがマナーを守れない行動をとることは多々あります。そのたびに感情的に叱ってしまう親も少なくありません。しかし、しつけとは怒ることではなく、子どもがなぜその行動が良くなかったのかを理解し、自ら正すことができるように導くことです。
たとえば、食事中に立ち上がってしまった子どもに対して、「座りなさい!」と叱るよりも、「食べているときに立つとこぼれて危ないよ。座って食べようね」と、理由とともにルールを伝えることで、子どもは納得しやすくなります。
お金に対する礼儀も、幼いうちから伝える
現金に触れる機会が少なくなっている現代ですが、子どもにお金の大切さや扱い方を教えることは、将来の金銭感覚や社会的マナーに大きく影響します。たとえば、お札をくしゃくしゃにしたり、床に置いたりしてしまったとき、「お札はたくさんの人が大切に使っているものだから、丁寧に扱おうね」とやさしく教えることで、自然と節度ある態度が身につきます。
また、お年玉やお小遣いをもらった際には、「ありがとう」と感謝の言葉を伝えることを習慣づけることで、金銭面におけるマナーだけでなく、人とのつながりの大切さも学ぶことができます。
親のふるまいが、子どものマナーの土台に
子どもが身につけるマナーの多くは、実は日常生活の中で無意識に見ている大人の行動によって形成されます。スーパーで他人とぶつかったときに「すみません」と一言添える、レジで「ありがとうございます」と言う、こうした小さなふるまいを積み重ねることが、子どもにとっての最高の“マナー教育”となります。
大人が堂々とマナーを守り、丁寧に人と接する姿を見せることこそが、育児中の最大のしつけといえるのではないでしょうか。
おわりに:マナーは“守るもの”ではなく、“伝わるもの”
育児中のマナールールは、決して「これをしなければならない」といった義務ではなく、子どもと社会をつなぐための“橋渡し”のような存在です。子どもが成長する過程で、多くの人と出会い、関わっていくなかで必要となる礼儀や思いやりの気持ちは、日々の生活の中で親から少しずつ受け取っていくものです。
そしてその一つひとつの言葉や行動が、将来、子ども自身が誰かを思いやる大人へと育っていくための土台となります。マナーとは押し付けるものではなく、やさしく伝え、共に育んでいくもの。親自身もまた、子どもと一緒にマナーを学び直す機会を楽しみながら、日々の育児に向き合っていけると良いですね。
- カテゴリ
- 学問・教育