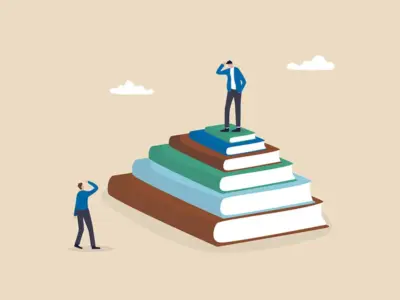リカレント教育の推進:社会人が学び直すための環境整備
「リカレント教育」とは何か?
「リカレント教育」とは、社会人が学校教育を終えた後も、必要に応じて学び直しを行う仕組みのことです。1970年代に経済協力開発機構(OECD)が提唱した概念で、生涯にわたって教育と仕事を交互に繰り返す「循環型の教育システム」を意味します。日本語では「学び直し」や「再教育」とも表現され、特に近年では、急速に変化する社会や職場環境に対応するための“スキルのアップデート”という意味合いで広く使われるようになりました。
AIやデジタル技術の進化により、これまでになかった職種が生まれたり、既存の仕事が大きく変化したりする中で、従来の知識や技術だけでは対応できないケースが増えています。こうした状況に対応する手段として、リカレント教育はますます重要になっています。
なぜ今、社会人の「学び直し」が必要なのか
こうしたリカレント教育の必要性は、データにも表れています。経済産業省の調査では、企業の約67%が「従業員のリスキリング(新たなスキルの習得)が必要」と回答しています。特にIT、デジタルマーケティング、データ活用などの分野では、わずか3〜5年でスキルが陳腐化するとも言われており、定期的なスキルの見直しが欠かせません。
一方で、学び直しに関心を持つ社会人は多いにもかかわらず、実際に行動に移している人は少ないのが現状です。2022年の民間調査では、社会人の56%が「学び直しに関心がある」と答えている一方で、実際に教育サービスを利用しているのはわずか12%にとどまっています。このギャップを埋めるためには、時間・費用・情報といったハードルを下げるための環境整備が急務です。
学び直しを支える教育機関と社会の取り組み
大学や専門学校では、社会人が柔軟に学べるよう夜間や週末、またオンラインによる履修証明プログラムの提供が進んでいます。たとえば東京大学や一橋大学では、年間100講座以上の社会人向け講義を実施し、全国から多様な世代の受講者が参加しています。
企業も積極的に学びを支援し始めており、社員一人あたり年間10万円までの学習費用を補助する制度を導入する企業も見られます。また、政府の「教育訓練給付制度」では、指定講座を受講した場合に最大70%(上限56万円)の補助金が支給されるなど、公的支援も整備されています。さらに、神戸市のように自治体と大学が連携し、地域住民向けの公開講座を提供するケースも増えています。2024年度には神戸市で延べ1万人以上が講座を受講するなど、地域ぐるみで学びを促進する取り組みも注目されています。
情報発信の力と学びの選択肢を広げるメディアの役割
近年では、SNSやYouTube、ビジネス系Webメディアなどを通じて、リカレント教育に関する情報が身近になってきました。たとえば「30代からの学び直し」「未経験からデータサイエンスへ」といった体験談は多くの共感を集め、再生回数が数十万回を超えることもあります。
これにより、「自分には難しい」と感じていた学び直しが、「やってみたい」「やってみよう」と思えるようになりつつあります。メディアは、知識を提供するだけでなく、学びへの心理的な壁を取り払う役割も果たしているのです。
学び続ける社会の実現に向けて
リカレント教育は、個人のキャリア形成だけでなく、社会の持続的な成長にもつながる重要な基盤です。働き方や生き方が多様化するなかで、「学び直し」は一部の人だけの選択ではなく、誰にとっても身近な“当たり前の選択肢”になるべきです。
そのためには、個人の意志だけでなく、企業、教育機関、自治体、そして国全体が連携して、誰もが無理なく学べる環境を整えることが不可欠です。学びは、年齢や職業を問わず、人生を豊かにする力を持っています。「今さら」ではなく「今から」始める学びが、これからの社会を支える原動力となるでしょう。
- カテゴリ
- 学問・教育