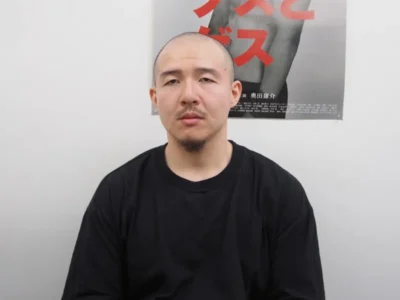サウナブーム第2章──癒しを超えて観光資源化が進む理由
心と経済を温める、新しい「ととのい」のかたち
サウナがもたらす心地よい発汗とリラックスは、ストレス社会を生きる人々にとって欠かせない習慣になりました。けれども今、サウナは単なる“癒しの場”を超えて、新たな社会的価値を帯び始めています。全国に3,500を超える施設があり(日本サウナ総研2024調べ)、都市部だけでなく地方にも個性豊かなサウナが次々と誕生しています。その多くが、地域の自然や文化、食を取り入れた“体験型観光”として再定義されているのです。
この潮流は、コロナ禍を経てライフスタイルが多様化し、「心身の健康」と「地域の豊かさ」を両立させたいという意識が高まったことに端を発しています。旅の目的が“観光地を巡る”から“整う時間を過ごす”へと変化し、サウナは今や新しい観光戦略の要となりつつあります。
「整う」から「繋がる」へ──体験価値の拡張
サウナの魅力は、温度と湿度だけでは語り尽くせません。施設のデザインや体験のストーリー、そしてそこに関わる人との交流が重要な要素になっています。北海道の「白銀のサウナ」では、雪景色の中でロウリュを楽しめる幻想的な空間が人気を集めています。長野県の「森のサウナ」では、地元の木材を使った香り豊かな建築が訪れる人の五感を刺激します。これらの事例は、サウナを通じて地域と人が結びつく新しい形を示しています。
観光庁の推計によると、国内のウェルネスツーリズム市場は2025年には約1.2兆円規模に達する見込みです。その中でも「サウナ付き宿泊プラン」の利用率は過去3年で約1.8倍に増加しています。旅行者の目的が「観光地巡り」から「心身のリトリート」に変化したことで、サウナは地域文化を伝える場としての存在感を高めています。さらにSNSの普及がその流れを後押ししています。20〜40代の利用者が中心となり、“ととのう瞬間”を共有する投稿が増え、サウナは地域の魅力発信ツールにもなっています。ハッシュタグ「#サ旅」はX(旧Twitter)やInstagramで約200万件を超え、観光地としてのサウナの認知を高めています。
地域経済を温める仕組み──ビジネスと雇用の波及
サウナが観光資源として注目される理由は、心の癒しにとどまらず、地域経済への波及効果にもあります。秋田県で進行中の「サウナランドプロジェクト」では、老舗旅館を再生し、地元木材を使用したサウナ棟を新設。年間3万人以上が訪れ、関連する飲食・宿泊業への波及効果は2億円超、雇用も15人分生まれました。
企業の戦略面でも動きが活発になっており、多くの施設がデジタルマーケティングを取り入れ、来訪履歴や滞在時間のデータをもとにリピート施策を展開しています。ローカルブランドとのコラボ商品や「サウナ×音楽フェス」「サウナ×アート展」といった複合イベントも増え、体験価値を広げながら地域経済を活性化させています。環境配慮の面では、電気サウナの電力を再生可能エネルギーに切り替える動きが広がり、全国約200の施設がグリーン電力証書を導入(2025年7月時点)。サウナがもはや“消費施設”ではなく、“持続可能な地域インフラ”へと変わりつつあることを示しています。
未来へ続く「温もりの文化」──観光と健康の新しい交差点
サウナの未来を見据えると、観光・健康・環境の三つの要素をつなぐハブとしての可能性が広がっています。日本各地に根づく温泉文化との親和性は高く、既存の温泉地がサウナを導入することで新しい層の観光客を呼び込む事例も増えています。例えば大分県別府市では、温泉とサウナを融合させた「スチームリゾート構想」が始動し、国内外からの来訪者数が前年同期比で25%増加しました。
地域の伝統工芸や自然資源を生かした“地産地消型サウナ”の開発も進んでいます。地元の木材、湧水、食材を使うことで、地域の循環経済を支える仕組みが整いつつあります。こうした取り組みは、単なる観光ビジネスを超え、人々が心身を整えながら地域に貢献する新しい形のツーリズムを築いています。
サウナブームの第2章は、単なる一過性のトレンドではありません。人が集い、地域が潤い、文化が息づく“循環型の温もり”を広げる動きです。癒しを求める行為が、結果として地域経済や環境に優しい未来を支える。サウナは今、その象徴として確実に日本の観光のかたちを変えています。
- カテゴリ
- 趣味・娯楽・エンターテイメント