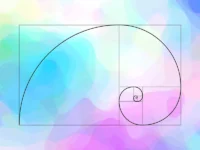夫婦で始めたNISA、パートナーが亡くなった後の運用は可能?

NISAは投資による利益が非課税となる制度として、多くの家庭で利用されています。夫婦それぞれが口座を持てば、非課税投資枠を2人分活用できるため、教育費や老後資金の準備に役立つ手段として注目されてきました。しかし、人生には予期せぬ出来事が訪れます。長年共に資産形成を進めてきたパートナーが亡くなった場合、そのNISA口座を残された配偶者や子供が引き継いで運用できるのか、疑問を抱く方も少なくありません。制度の仕組みや相続手続きの流れを理解しておくことは、家族の将来を守る上で大きな安心につながります。
パートナーのNISA口座はどうなるのか
NISAは個人専用の非課税制度であるため、口座名義人が亡くなるとその効力は消失します。制度上「一人一口座」が原則であり、他人がそのまま運用を引き継ぐことはできません。実務では、金融機関に死亡届を提出し、名義人の証券口座全体について手続きを進める必要があります。
NISAで保有していた株式や投資信託は、いったん課税口座に移されるか、相続財産として評価されます。例えば100万円分の投資信託をNISAで運用していた場合、亡くなった時点での評価額がそのまま相続資産として扱われる仕組みです。相続後は非課税の枠組みが失われ、通常の金融資産と同じように課税対象に含まれます。国税庁の指針でも、相続税の申告においてはNISAの有無を問わず時価評価額を明記する必要があると定められています。
また、相続税の面では配偶者に大きな優遇があります。配偶者が相続する場合、1億6,000万円または法定相続分まで非課税となるため、残された家族にとって税負担は比較的軽減されやすい仕組みになっています。こうした制度を理解した上で相続資金を新NISAに再投資することが、今後の安定した生活設計に役立ちます。
残された家族にできること
口座を直接引き継ぐことはできませんが、相続した資産をどのように使うかは家族の選択に委ねられます。配偶者がすでに自分のNISA口座を持っている場合、受け取った資金を非課税枠に改めて投資することが可能です。2024年から新しいNISA制度が始まり、年間で最大360万円、総額で1800万円まで非課税で投資できるようになっています。夫婦二人分を活用できれば、資産形成の効率を大きく高められるでしょう。
教育費や住宅資金など、将来に備える資金として活用する場面も少なくありません。相続した資金を預貯金に置いておくだけではインフレによる目減りのリスクがありますが、投資信託などを利用して長期的に分散投資を行えば、その影響を和らげる効果が期待できます。かつて利用されていたジュニアNISAは終了しましたが、親が自分のNISA枠を通じて子供の教育資金を準備するという考え方は引き続き有効です。
相続税に関しては、配偶者に対して特例が設けられています。配偶者が受け取る場合は、1億6000万円または法定相続分まで非課税とされるため、多くの家庭では相続税の負担を大幅に軽減できます。この仕組みを理解し、残された資産をどのように再投資するかを考えることが、家族の生活を守る上で大切です。
手続きの流れと専門家の活用
相続手続きは感情的にも大きな負担となる場面ですが、期限や必要書類を踏まえて冷静に進めることが求められます。金融機関に死亡の事実を届け出ると、口座の残高証明書が発行され、その後に資産の分割や移管が行われます。必要書類には戸籍謄本や相続人全員の印鑑証明などがあり、集めるのに時間がかかる場合もあります。さらに、相続税の申告は相続開始から10か月以内と定められており、期限を過ぎると加算税が課されるため注意が必要です。
こうした事情を踏まえれば、専門家に相談することは有効な手段となります。税理士は相続財産の評価や申告を担い、ファイナンシャルプランナーは相続後の資産をどのように運用していくかについて助言します。司法書士は不動産登記を主に扱いますが、金融資産の名義変更に関与することもあります。相続は法務・税務・金融が複雑に絡み合うため、一人で全てを対応するのは難しく、必要に応じて複数の専門家を組み合わせることが現実的です。
まとめ
夫婦で始めたNISAは、パートナーが亡くなると非課税の恩恵をそのまま引き継ぐことはできません。口座は名義人専用の制度であり、死去の時点で効力を失う仕組みになっています。しかし、相続によって受け継いだ資金を自身のNISA枠で再投資すれば、長期的な資産形成を続けることは可能です。
相続税の軽減措置や新NISA制度の拡充といった制度を活用すれば、残された家族が経済的に安心できる環境を整えられます。大切なのは、相続が発生してから慌てるのではなく、生前から準備を進めておくことです。家族間で情報を共有し、手続きに必要な書類を把握しておけば、いざという時に冷静に対応できます。夫婦で築いた資産をどのように守り、次の世代へと受け渡していくのか。NISAをきっかけに、家族の未来を見据えた対話を重ねることが何よりの備えになるでしょう。
- カテゴリ
- マネー