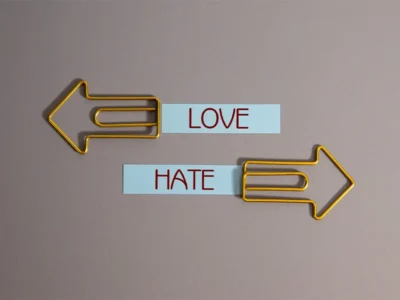ママ友づきあいがラクになるちょうどいい距離感とは?

進歩が成長し、保育園や幼稚園や小学校に通い始めると、自然と始まるのが「ママ友」との関係です。送り迎えのたびに顔合わせ、行事や習い事で交流が生まれる——そんな日常の中で、「どうすれば正しいのだろう」と戸惑った経験はありませんか?
こどもが保育園や幼稚園、小学校に通い始めると、親として避けて通えないのが「ママ友づきあい」です。 ママ友との関係は、一時「子どもを通じた人間関係」であるため、現場のように明確なルールもなければ、旧来の友人のような安心感もありません。そのため、「どう関わればよいのか分からない」と感じる方も多いでしょう。
約7割のママが「ストレスを感じたことがある」
全国の育児中の母親1,000人を対象とした2023年の調査(育児生活サポート調査室)によると、全体の68.4%が「ママ友との関係にストレスを感じたことがある」と回答しています。特に30〜40代のママは、子育てに加えて仕事や家事の負担も大きいため、ママ友との人間関係まで気を配る余裕がないという現実もあります。 さらに、SNSやグループLINEなどによるコミュニケーション疲れも、今後大きくなっています。
なぜママ友との距離は難しいのか?
ママ友との関係は、どこか「特別で、だけど不安定」なものです。 子どもから生まれたつながりは、自然なようでいて、実はとても繊細なバランスの上にあります。 例えば、学生時代の友人なら気が合う人同士が集まりますが、ママ友は「子どもが同じクラス」「同じ保育園の送り迎え時間」という偶然に会える関係です。実際、「親同士が仲良くしていないと、子どもが浮いてしまうのでは」という不安から、気を使いすぎてしまうこともよくわかります。
心理学見てから見て、ママ友との関係性は「ソーシャルスペース(1.2〜3.6m)」と呼ばれる、心の距離の中でも特に微妙なゾーンになります。さらに、ママ友同士は「友達」でも「仕事仲間」でもありません。そのため、関係のルールが問題なく、どこまで共有すればいいのか、どう振る舞えばよいのか、手探りになりやすいのです。共通の趣味や目標もなく、立場や環境もバラバラです。
本当は、ママとの距離が難しい理由は、「関係があいまいなこと」「求められるが分からないこと」、そして「自分の気持ちと立場のバランスが取りにくいこと」にもあると考えられます。
自分の性格に合った距離感を選ぶ
ママ友づきあいで一番大切なのは、「周囲と同じようにしなければいけない」とは思わないことです。 他のママたちが頻繁にランチ会を開いていても、自分がそれなりに疲れてしまうのであれば、無理に参加する必要はありません。ないを選ぶことが、長く無理なく続けられる関係につながります。
また、自然な挨拶ができるようになれば、相手にも安心感が伝わり、少しずつ会話が生まれてきます。 少人数で話すほうが落ち着く人は、グループLINEで無理に会話を広げるよりも、一人のママと個別に行動する方が気が楽です。実際、「ママ友付き合いで一番ラクだった」と感じている人の多くは、「無理せず自然体でいられる相手との関係」に落ち着いている傾向があります。
ストレスを減らすための小さな工夫
ママ友関係を穏やかにしながら、ストレスを減らすためには、ちょっとした工夫も効果的です。
家庭の教育方針や経済情勢など、プライベートな内容には踏み込まず、「子どもの最近の様子」や「行事の情報」など、誰にとっても話しやすい話題を話すことが大切です。
また、SNSやグループLINEは便利な反対、距離感が崩れやすいツールでもあります。すぐに返信しなければと焦ったり、スタンプ一つで相手の機嫌を見てしまうような状況は、心の疲労につながります。自分の都合に合わせて対応することで、相手にも「お互い様」という自然な感覚が育まれていきます。
「ありがとう」「受け止めます」といった感謝の言葉をさりげなく伝えることも、良い関係を継続する効果があります。会話の中に一言添えるだけで、相手の心和らぎ、自分自身も無理のない関係を築けるようになります。
完璧な関係を求めず、自然体で向き合う
ママ友づきあいは、人生の中でも限られた時間に特別に生まれた人間関係です。 子どもが成長すれば環境は自然と変わり、今の関係も少しずつ形を変えていきます。気が合う人とだけ、ゆっくり優しくなっても良いですし、挨拶だけで十分な相手がいても完全に問題はありません。 大切なのは、あなた自身が「心地よい」と適切な関係であることです。
ママである前に、一人人としてのあなた自身が、安心できる場所であることが、子どもにとっても家族にとっても、何よりの支えになるのです。
- カテゴリ
- 人間関係・人生相談