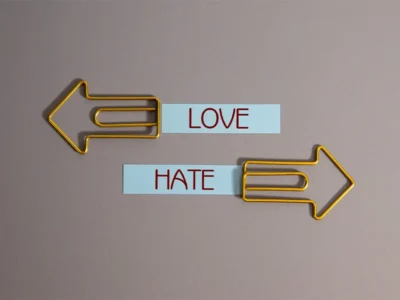子どもの心を開くには?“問い詰めない”聞き方のすすめ

「うちの子、最近あまり話してくれない…」「聞いても“別に”しか返ってこない」。そんなもどかしさを感じたことはありませんか? 子どもの本音を知りたいと思う一方で、無理に聞き出そうとすると、かえって距離ができてしまう——これは多くの親が抱える共通の悩みです。
実は、子どもが本音を語るかどうかは、「何を聞くか」ではなく「どう聞くか」にかかっています。信頼関係を築く聞き方は、子育てだけでなく、職場や友人関係など幅広い場面でも役立ちます。
子どもが本音を語るまでに必要な「7回の対話」
ある心理学調査では、人が心を開くまでには最低7回以上の対話が必要だとされています(カリフォルニア大学のコミュニケーション研究より)。この回数は、家庭内でも例外ではありません。特に思春期の子どもにとっては、自分の気持ちをうまく言葉にできないことも多く、親が焦って質問を重ねれば逆に心の扉を閉ざしてしまう結果になりかねません。
だからこそ、1回の会話で答えを得ようとせず、数回に分けてじっくり向き合う姿勢が大切です。「急がず、繰り返し、待つ」ことが、信頼の土台をつくっていきます。
子どもは“安心できる相手”にしか本音を見せない
2022年に実施された内閣府の調査によると、小中学生のうち約68.4%が「親には悩みをすべて話していない」と答えています。その理由として最も多かったのは、「言ってもわかってもらえないと思うから」(約35%)でした。この結果からもわかるように、子どもは“理解されるかどうか”を非常に敏感に感じ取っています。
親がどれだけ子どもを思っていても、「この人に話してもいい」と思ってもらえなければ、本音は語られません。子どもにとっての「安心できる相手」とは、失敗や悩みを打ち明けても否定されず、静かに耳を傾けてくれる存在なのです。
会話は「問い詰め」ではなく「寄り添い」がカギ
子どもとの会話で「今日どうだった?」と聞いた際に、「べつに」「ふつう」としか返ってこないという経験は、多くの親がしています。このような返答が続くと、「どうして話してくれないの?」と感じてしまうかもしれませんが、実はこのような返事には理由があります。
親が無意識のうちに「ちゃんと話しなさい」「何があったのか教えて」と問い詰めてしまうと、子どもは「答えなきゃいけない」「正解を言わないといけない」とプレッシャーを感じてしまいます。そこでおすすめしたいのが、“質問”ではなく“引き出す”という意識です。「そのとき、どんな気持ちだったのかな」「最近、楽しそうに見えるね。何かいいことあった?」といった、感情に焦点を当てた言葉を投げかけることで、相手は自分の気持ちに向き合いながら話すことができます。このような聞き方は、カウンセリングの現場でも効果的な手法として使われています。
「沈黙」を大切にする聞き方
会話の中で沈黙が生まれると、親としてはつい焦ってしまいがちです。しかし、この3〜5秒間の沈黙は、子どもが自分の気持ちを言葉にするための大切な“思考の時間”です。
子どもが「学校、ちょっとイヤかも」と口にしたとき、「何がイヤなの?誰かに何か言われたの?」と矢継ぎ早に質問すると、子どもはその場から逃げたくなってしまうことがあります。そこであえて少しの沈黙を挟み、子どもが続きを話すまで待つことで、「この人は私の気持ちを待ってくれる」と信頼が深まります。
非言語のコミュニケーションが安心感をつくる
言葉だけでなく、表情やしぐさもまた、子どもに安心感を与える大切な要素です。心理学者メラビアンの研究によれば、人の印象は言葉よりも93%が非言語情報(表情や声のトーン、視線など)に左右されるとされています。
たとえば、子どもが話しているときに目を見て優しくうなずくことや、テレビやスマホを置いてしっかり向き合うこと。それだけで、子どもは「話してよかった」と感じるのです。大人にとっては小さなことに見えても、子どもにとっては大きな安心感につながっています。
「小さなつぶやき」を見逃さないこと
「学校つまんないな…」「○○ちゃんと話してないかも」といった、何気ない一言にこそ、子どもの本音が隠れていることがあります。こうしたつぶやきを「そうなんだ」で終わらせず、「それってどんなときに思うの?」「そう感じたのは最近なのかな?」とやさしく聞き返すことで、会話が広がり、より深い感情に触れることができます。
とくに就学前の子どもや、小学校低学年の段階では、自分の気持ちを言葉で整理するのが難しい時期です。だからこそ、親が“翻訳者”として子どもの言葉に耳を傾ける姿勢が求められます。
まとめ:親子の信頼関係は“聞き方”で深まる
子どもの本音は、「答えを急かす聞き方」ではなく、「そっと寄り添う姿勢」の中でこそ生まれます。親が正解を求めるのではなく、子ども自身の気持ちに耳を傾け、「どんな言葉も受け止めるよ」というメッセージを届けることが、何よりの信頼づくりになります。
毎日の会話の中で、共感し、見守り、待つ——この小さな積み重ねが、やがて大きな安心感となって、子どもは自然に心を開いてくれるようになります。「話してよかった」「聞いてくれてうれしい」と子どもに思ってもらえるような、そんな聞き方を、これから少しずつ育てていきませんか。
- カテゴリ
- 人間関係・人生相談