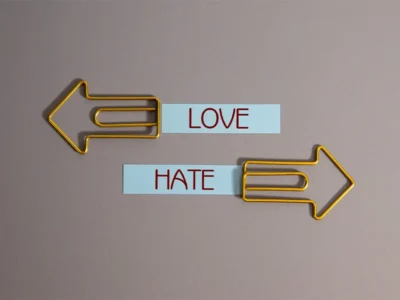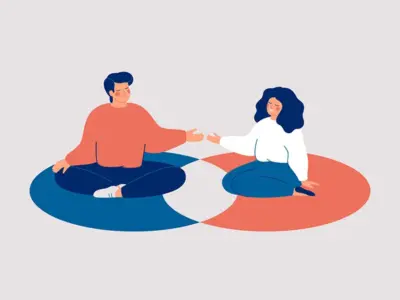「正解のない時代」をどう生きるか:制度と価値観の間で

現代社会を生きる私たちは、目の前に現れる様々な選択肢に対して、常に「制度に従うか」「価値観を優先するか」という問いを突きつけられています。これは、表面的には就職・子育て・老後など人生の節目での判断に見えますが、根底には「自分は何を信じて生きるのか」「社会とどう関わるのか」という、より深い人生観や社会観が潜んでいます。
制度がもたらすのは「安心」だけではない
制度とは、国や企業、地域社会などが定めるルールや仕組みを意味します。日本においては、学歴社会・年功序列・終身雇用・公的年金・健康保険・義務教育といった制度が戦後の社会基盤を支えてきました。制度に従うことで、ある程度の安定や見通しが得られるのは確かです。多くの人が、制度に沿って生きることで「正しい人生」「常識的な選択」をしているという安心感を抱いています。
しかし、制度が設計された当時とは社会の構造も人々の価値観も大きく変わっています。例えば、単身世帯は2020年時点で全体の38%を超え、かつて主流だった「夫婦+子ども」の家族像とは大きく異なる現実があります。それにもかかわらず、税制や年金制度など多くの社会制度は未だに「標準世帯」モデルを前提としています。結果として、制度に従うことが必ずしも公平や合理性を保証するとは限らないのです。
価値観を軸に生きるという決断の重み
一方、自分自身の価値観に基づいて人生を設計するという生き方は、近年ますます注目されています。たとえば、「結婚しない」「子どもを持たない」「会社に属さずに働く」といった選択は、制度的には想定外であることも多いですが、本人にとっては自分の価値観に正直な生き方です。
このような生き方は、自由や充実感をもたらす一方で、経済的・社会的なリスクも伴います。たとえば、フリーランスとして働く人は、会社員と比べて社会保障が薄く、老後の備えも個人の責任に委ねられます。また、世間の理解が得られにくい選択をする場合、「それで大丈夫なの?」「親を安心させたいのに…」といった葛藤も生まれます。
つまり、価値観を優先して生きるには、制度に代わる「自分なりの軸」と、周囲の反応に耐えるための内的な強さが必要なのです。
仕事・家族・老後——選択が交錯する3つの局面
働き方の再設計
従来の「会社に入って一生勤め上げる」という制度的キャリアモデルに対し、現代は多様な働き方が選べる時代となりました。副業・フリーランス・パラレルキャリアなど、企業外でも価値を生み出せる場が広がっています。中でも注目されているのが「意味報酬(パーパス)」を重視する傾向です。ある調査によれば、20代の約65%が「お金よりも社会的意義や自分の納得感を重視する」と回答しており、キャリア観のシフトが明確に現れています。
家族のあり方と子育ての選択
かつては「結婚して子どもを育てること」が人生の王道とされていましたが、今や多くの人が「結婚しない人生」や「ひとり親での子育て」「LGBTQ+カップルでの養育」など、制度にとらわれない選択を行っています。ところが、扶養制度や育児休業制度などの法制度は、この多様性に必ずしも追いついていません。自分たちの価値観を優先すると、制度の恩恵から外れるというジレンマに直面するのです。
老後に向けた人生設計
日本の公的年金制度は、「65歳で定年し、年金で暮らす」というモデルを前提に設計されています。しかし実際には、老後も働きたい・働かざるを得ないという人が増加しています。また、資産形成・ライフシフト・地域移住など、自分の価値観で老後を設計する人も少なくありません。NISAやiDeCoといった制度も整備されつつありますが、「制度を活用するには自ら学び、判断する」というリテラシーも求められています。
制度と価値観を対立ではなく、対話させる
制度に従えば安心が得られますが、それが必ずしも自分に合っているとは限りません。一方で、価値観を優先すれば自己実現は果たせるかもしれませんが、制度が与える安全網を手放すリスクもあるでしょう。
だからこそ重要なのは、「制度か、価値観か」という二項対立ではなく、「どの制度をどの程度活用し、自分の価値観をどう守るか」という対話的アプローチです。現代を生きる私たちには、「制度の恩恵を享受しつつ、自分らしい選択も諦めない」柔軟さが求められています。
たとえば、会社員でありながら副業で自分の好きなことを追求する人、親の介護と仕事の両立を制度に頼らず地域とのつながりで解決する人など、両者を組み合わせる実践も増えてきました。選択肢は広がっていますが、だからこそ「自分にとっての幸福とは何か」を丁寧に問う姿勢が欠かせません。
- カテゴリ
- 人間関係・人生相談