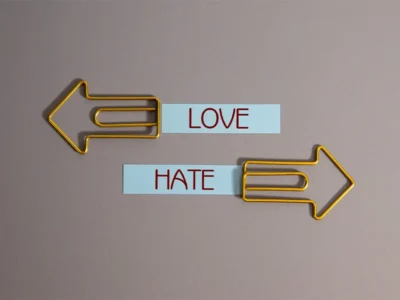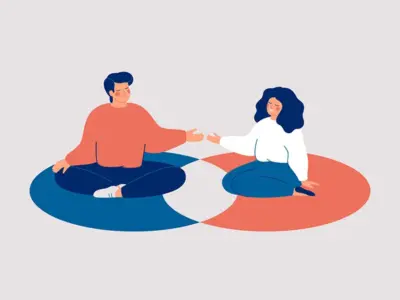大人の友人関係減少は必然か?社会学的に読み解く
大人になると友人が減るのはなぜか
成長の過程で私たちは多くの人と出会い、学校や部活動、アルバイト先などの共同体で自然に友情を築きます。しかし社会人になると、「気づけば友人が減っている」と感じる人は少なくありません。背景にはライフステージの変化や社会構造の影響があり、これは個人の努力不足だけでは説明できない現象です。
内閣府の「社会意識に関する世論調査」(2022年)によれば、20代で「親しい友人が5人以上いる」と答えた人は約40%ですが、50代では20%程度まで下がります。加齢とともに家庭や仕事といった責任が増え、自由に使える時間やエネルギーが減ることが大きな要因と考えられます。日本社会に根強い長時間労働の文化や、家族への責任感の強さも、友人関係の縮小に拍車をかけているのでしょう。
減少の裏にある「選別」と「質の深化」
友人が減る一方で、残った人間関係はより濃く、信頼できるものへと変化していく傾向があります。英国の人類学者ロビン・ダンバーは「人間が安定的に維持できる人間関係は150人前後、その中でも親密に関わる相手は5人程度」と提唱しました。数が減ることは決してネガティブではなく、むしろ少数精鋭の関係へと移行する自然な流れといえます。
リクルートが2021年に行った調査では、40代以上の7割が「数人の友人で十分」と答えています。これは、大人の友情が量から質へと移り変わっていることを示すデータです。一方で、大人の友人関係には「マウンティング」のリスクも潜んでいます。仕事での役職や収入、結婚や子育ての有無など、ライフステージに差が生じるほど比較や競争が入り込みやすくなり、疎遠になってしまうケースも少なくありません。友情を保つには、利害や肩書きに縛られないフラットな関係性をいかに維持するかが重要になります。
独身・既婚・パートナーの有無と人間関係
ライフスタイルによって友人関係の形は変わります。独身者は自由な時間を持ちやすいため、趣味やコミュニティを通じて新しいつながりを築く機会に恵まれています。総務省の国勢調査では、生涯未婚率が男性28%、女性18%を超えており、今後独身者はさらに増加すると見込まれています。こうした背景もあり、独身者が多様なコミュニティを拠点に人間関係を広げる傾向は強まりつつあります。
一方で、既婚者やパートナーを持つ人は、家庭中心の生活へと比重が移る傾向が顕著です。育児を通じたママ友・パパ友との交流が生まれる一方、子どもの成長とともに自然に関係が薄れていくこともあります。また家庭内に相談相手がいるため、外部の友人への依存度が下がることも少なくありません。しかし独身であっても孤独感のリスクは存在します。NHKの「国民生活時間調査」(2021年)では、独身中高年の約3割が「誰とも連絡を取らない日が週に3日以上ある」と回答しており、社会的孤立の深刻さがうかがえます。独身者の自由さと孤立のはざま、既婚者の安定と関係の限定性。いずれも長所と課題を併せ持つ点が特徴的です。
大人の友人関係を育むために
大人になってから友人関係を維持・発展させるためには、意識的な工夫が欠かせません。まず大切なのは「時間の質」です。長時間一緒にいることが難しくても、短時間でも定期的に連絡を取り合うことで関係は維持できます。オンライン会議やチャットツールの普及により、距離を超えたつながりを続けやすくなった点は現代の強みです。
役割や比較から自由になれる関係を意識することも重要です。社会学では人間関係を「道具的関係(利害や役割に基づくもの)」と「表出的関係(共感や感情に基づくもの)」に分けます。大人の友情を長く保つには、職場や生活環境の差に左右されにくい「表出的関係」を築くことが求められます。さらに、新しいコミュニティへの参加も効果的です。地域活動やボランティア、趣味のサークルなどは、共通の関心を土台にフラットな関係を築きやすい場です。オンライン上のコミュニティやSNSも、価値観の近い人と出会うきっかけになっています。
まとめ
大人になると友人が減っていくことは、社会的役割やライフステージの変化に伴う必然的な現象といえます。しかし、減ったからといって人間関係の価値が下がるわけではなく、むしろ残るつながりは濃く深くなりやすい特徴があります。独身か既婚かにかかわらず、数人でも本音を語り合える友人は人生を豊かにし、孤立のリスクを和らげる存在となります。
現代社会では孤独や孤立が深刻な課題として取り上げられていますが、意識的に時間を確保し、比較や役割に縛られない関係を大切にすることで、大人になってからも新しい友情は築けます。数よりも質を重視し、小さなつながりを育てていくことこそが、これからの時代に求められる人間関係の在り方ではないでしょうか。
- カテゴリ
- 人間関係・人生相談