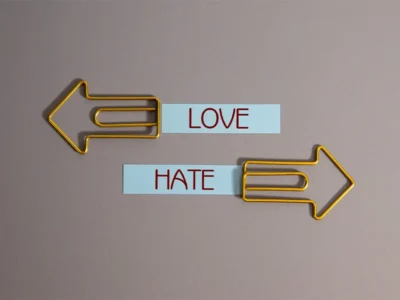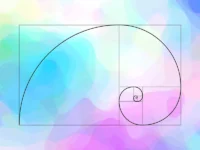【連載:ちえシェアの現場から】戦争孤児からIBMエンジニアへ──諦めなかった少年が見た未来<前編>

家族を失い、病に倒れ、飢えに苦しんでも――少年は歩みを止めませんでした。
戦争孤児として満州から引き揚げた柴原喬さん(88歳)の幼少期は、現代に生きる私たちには想像しがたいほど過酷なものでした。
満州の地で生まれ、孤独のなかを生き抜いた少年は、のちに日本IBMのエンジニアとして仲間とともに未来を切り拓いていきます。
「どんなときも、諦めなかった。それが生きる力になったのです」。
Dress aging合同会社が主催するイベント「ちえシェア」で語られたのは、過酷な体験を越え、希望をつかんだ一人の男性の物語でした。
▼ちえシェアイベント詳細はこちら
戦後80年。戦争体験を未来へつなぐ──Dress agingが挑む「人生のちえ」の循環 | OKWAVEメディア,OKWAVE media
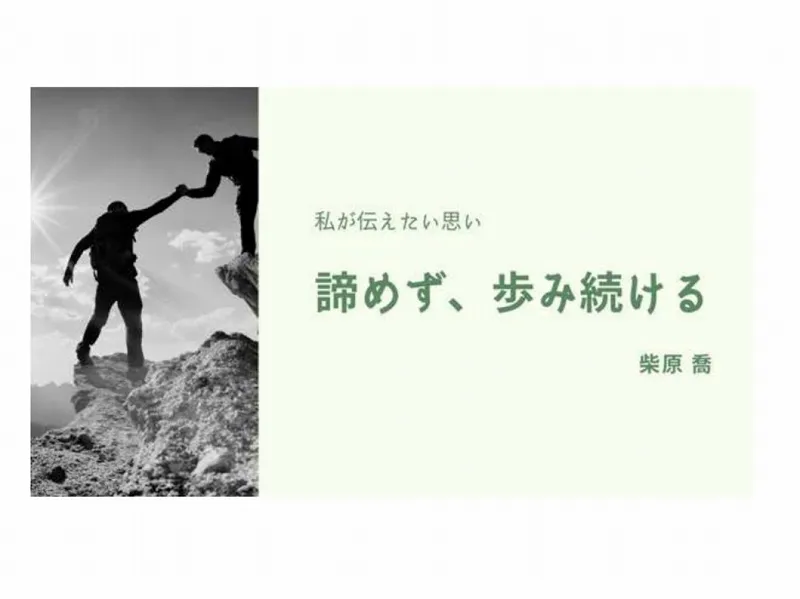
満州に生まれた少年
1937年、柴原喬さんは、旧満州国・奉天市(現・瀋陽)に産まれハルピンで育ちました。。関東軍の陸軍技術中尉であった父と、優しい母、祖父母、弟妹たちとともに、豊かな自然に囲まれた穏やかな日々を過ごします。幼い柴原さんにとって世界は美しく、山のないハルピンは果てしない大地と赤い夕陽が輝く大陸だったといいます。
けれど、平穏な時間は長くは続きませんでした。
母の死、そして戦争の影
1940年。ハルピンで腸チフスが大流行します。3歳の柴原さんの母も感染し、陸軍病院で息を引き取りました。小さな柴原さんは、突如大きな拠り所を失ったのです。
その後、戦争はますます激しくなり、1945年8月。日本の敗戦と同時に、ソ連軍の侵攻が始まります。
父は強制労働で送られ、残された老人、女性、子どもは別の陸軍官舎へ避難します。しかしそこもまたソ連軍の侵攻の地となり、恐怖におびえる日々が続いたのです。
彼らの主な要求は、金銭、女、腕時計。抵抗すれば、殴られ、殺される。そんな状態でした。
絶体絶命のなかの一筋の光
ある朝、柴原家にもソ連兵が押し寄せました。ピストルを突きつけ、腕時計を差し出せと怒鳴る兵士。柴原さんの家には柱時計しかありません。それを指さした継母(実母死後、父と再婚)の言葉に、兵士は逆上しました。
全員に両手を上げて壁際に立つよう命じます。凍りつくような空気の中、祖父だけが立ち上がれませんでした。(のちに緊張で足が震えて動けなかったといいます)
そのとき、別のソ連将校が入ってきました。彼はその光景を見て、静かに祖父に手を差し伸べ、家族を解放したのです。
「ソ連兵にもこんな人がいるんだ――」。絶望の中に、柴原さんは一筋の光を見たと言います。
けれど、午後には男狩りが始まり、祖父は連れていかれてしまいました。
ハルピン陸軍官舎からの脱出
「ここにいたら殺されるか、餓死してしまう。ならば祖国に少しでも近づこう」。
ハルピンの花園国民学校を目指し、女性と子どもだけの集団脱走が決行されました。道中数々の人が命を落とします。ようやくたどり着いたその翌日、祖母が還らぬ人となり、それに続いて幼い妹が飢えで息を引き取りました。残されたのは、継母と乳飲み子の弟、そして柴原少年。それもなんとか生きながらえているという、過酷な状況でした。
収容所の劣悪な日々
ハルピンで捕らえられた一家は、新香坊収容所に連行されます。そこは元・家畜小屋。臭気と寒さに包まれた劣悪な環境でした。
過酷な環境下に耐えながら生を繋いでいるある日、継母が突然いなくなります。「お母さんは、あんた一人なら生きていけると思って出ていったんだよ。だから恨んじゃいけないよ」。隣のおばさんにそう告げられ、柴原少年は再び一人ぼっちになりました。
しかし、そんな柴原少年に、懐かしい訪問者がきたのです。
祖父です。男狩りの末、別の場所で父と再会し、孫を探して来てくれたのです。「その日から家族が二人になり、私の心は癒されていきました」。
チフスとの闘い、祖父の死
収容所では、赤い高粱(コウリャン)を炊いたわずかなおかゆが一日2食という食事環境。着の身着のままの衣類に、月1回の風呂。栄養失調と不衛生な環境から、シラミがわき、発疹チフスが蔓延してきました。
柴原さんと祖父も、発疹チフスにかかってしまいます。枕を並べて高熱と幻覚にうなされ、凶暴化して祖父に殴りかかってしまったこともあったと言います。少しずつ意識が戻っていき、立ち上がれるくらい回復したその当日、柴原さんを支えてくれた祖父は命を落としました。
1946年、柴原少年は再び孤児となりました。それでも、生きることを諦めませんでした。

人の優しさが生かしてくれた
大人たちは食料を求めて収容所の外へ出るようになります。けれど、子どもの柴原さんには何もできません。残酷にも、体力回復とともに空腹感も強烈になっていきます。そんな彼に、向かいの小屋の青年・シバタさんが食料を分けてくれるようになりました。
「周囲の大人たちの優しさに支えられながら、私は生きる気力を取り戻していきました」。
その優しさは、のちに人生の指針となる“ちえ”になりました。
絶望の荒野を歩く──引揚げの日々
1946年9月、9歳になった柴原さんに待望の引揚げ命令が出ました。1000キロ先の港を目指して、無蓋列車と徒歩での長い旅が始まりました。飢えと渇きに耐えながら、柴原さんはただ“生きる”ことだけを考えていたといいます。喉の渇きで目が覚め、雨が降ったことを幸運と喜びながら命からがらひたすら先を目指す。泣く泣く子どもを預ける親、力尽きて無念の死を遂げる者、野宿をしながら集落を見つけては水乞いをする日々。そんな壮絶な時間のなか、それでも歩みを止めませんでした。ようやく港に着き、引揚げ船で日本へ向かっている間も、毎日のように水葬が行われていました。
灰色の大地の果て、ついに日本の港にたどり着いたとき、見えたのは緑に覆われた山々でした。
「日本の山の緑を見た瞬間、ああ、日本は平和だと思いました」。
帰国。そして次の章へ
何でも食べた。
何でも飲んだ。
生きることを諦めなかった少年は、ついに故郷にたどり着きました。
実母の実家で、6歳になった弟と再会。その瞬間、長い孤独の時間がようやく終わりました。
「どんなにつらくても、諦めなければ、いつか希望は見える」。
次回、柴原さんが帰国後に歩んだ“再出発の人生”をお届けします。
- カテゴリ
- 人間関係・人生相談