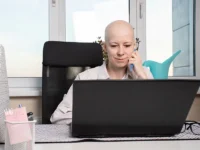“持ち家でも安心できない?”老後の住宅維持費にご注意

「持ち家さえあれば老後は安泰」。そう信じて家を購入し、長年ローンを返済してきた方にとって、退職後の生活は安心のはず――。けれども、近年はそう言い切れない現実が見えてきました。
物価の上昇や年金不安が重なるなか、持ち家でも暮らしを続けるには一定の出費がつきまといます。住まいを維持するための費用は、想像以上に家計に影響を与えるものです。老後資金の計画を立てるうえでは、住宅維持費という視点を避けて通ることはできません。これまで頑張って手に入れた「自分の家」が、安心の礎になるか、それとも不安の火種になるかは、準備次第で大きく変わります。
見えにくい住宅維持費、実はこんなにかかっている
住宅ローンを完済すれば、家に関する費用は大きく減ると思いがちですが、現実にはさまざまな出費が続いていきます。たとえば、毎年かかる固定資産税は、都市部であれば10万円を超えることも珍しくありません。加えて、建物の老朽化にともなって、屋根や外壁の塗り替え、給湯器や配管の交換といった修繕が必要になる時期も訪れます。
築30年を超える住宅では、外装や内装を含む大規模なリフォームが必要になることもあります。外壁の再塗装に80万円、キッチンや浴室の入れ替えには150万円前後かかる場合もあるため、まとまった費用が求められます。こうした工事は急を要することも多く、老後の限られた収入では対応が難しくなる場面も出てきます。さらに、年齢を重ねるとバリアフリー対応も検討したくなります。階段に手すりを設置したり、段差を解消するリフォームは、一箇所につき5万〜20万円ほどの費用がかかることもあり、これも無視できない負担です。
物価高と年金不安が住宅費に追い打ちをかける
かつては、年金と少しの貯蓄があれば穏やかに暮らせるという見通しが一般的でしたが、今ではその前提が崩れつつあります。2020年代以降、光熱費や日用品、建築資材などあらゆるものの価格が上昇し続けています。たとえば、電気料金は5年前と比べて約1.5倍、建築用合板などは2倍以上に高騰しているケースもあります。
一方で、公的年金の支給額は物価の伸びに追いついていないのが現状です。2024年度の年金支給額の改定幅はわずか2.7%増にとどまり、実質的には生活費の高騰に追い付けていません。特に夫婦2人暮らしの平均支出が月25万〜30万円に対し、年金受給額が20万円に届かない世帯も多く、住宅維持費がのしかかることで生活が圧迫されてしまう恐れがあります。さらに、通院や介護にかかる交通費やサービス利用料が増えることで、想定外の出費が発生することもあり、住宅にかかる費用を軽視することはできません。
老後資金に住宅維持費をどう組み込むか
老後の家計を安定させるには、住宅維持費を想定した資金計画を立てておくことが欠かせません。一般的には、年間15万〜20万円程度を「住宅の維持コスト」として見積もっておくとよいとされています。さらに突発的な修繕に備えて、100万円以上の予備費を確保しておくと安心です。
現役時代から計画的に貯蓄と投資を組み合わせることも効果的です。預金だけではインフレに弱く、将来的に価値が目減りするリスクもあります。つみたてNISAやiDeCoといった制度を活用すれば、少額からの積立によって老後資金を増やすことが可能です。リスクを抑えながら運用できる商品を選ぶことで、資産の安定性を保ちながら備えることができます。
また、自治体によっては高齢者向けのリフォーム補助金や、介護保険による住宅改修支援制度などが用意されている場合もあります。こうした制度を上手に活用すれば、出費を抑えつつ安心して住み続けることができます。
持ち家を安心に変えるには「備え」と「選択」が鍵になる
持ち家があるという安心感は、確かに大きな支えになります。しかし、維持には費用がかかり、何もしなければ安心は長くは続きません。暮らしの中で、住まいの状態や家計のバランスを見ながら、将来の選択肢を少しずつ整理していくことが大切です。
状況によっては、バリアフリー住宅への住み替えや、子世帯との同居、資産活用としての売却・賃貸なども視野に入れる必要が出てくるかもしれません。いずれの選択も、慌てて決めるより、時間に余裕があるうちから準備を進めたほうが結果的に後悔のない決断につながります。
持ち家は「資産」であると同時に、「責任」でもあります。これからの暮らしを安心して過ごすために、住宅維持費の現実を知り、具体的な行動につなげていくことが、将来への確かな備えになるはずです。
- カテゴリ
- 生活・暮らし