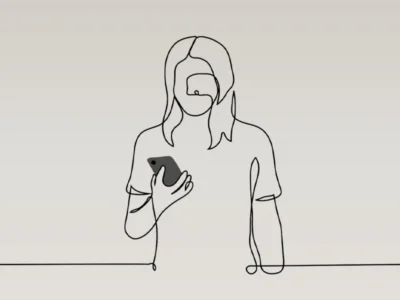競合との違いを際立たせる“課題起点”型コンテンツ

どれだけ優れた製品やサービスを提供していても、それが伝わらなければ意味がありません。特にSaaSプロダクトのような無形商材は、特徴の違いがユーザーに伝わりづらく、競合との差別化に苦戦する企業も多いのではないでしょうか。
従来のように「機能」や「価格」といったスペック勝負では、ユーザーの心に響きにくくなっている今、注目されているのが“課題起点型コンテンツ”です。これは、ユーザー自身が抱える悩みや不安から出発し、その解決策として自然に自社プロダクトを導くマーケティング手法です。
つまり、「売りたいこと」ではなく、「共感されること」を起点にする。これこそが、現代の情報過多時代において、顧客の心を動かし、競合と差をつける鍵となります。
SaaSプロダクトはなぜ差別化が難しいのか?
SaaS(Software as a Service)とは、インターネットを通じて提供されるソフトウェアサービスのことです。クラウド上で提供され、インストール不要、サブスクリプションで柔軟に使える点が魅力で、企業の業務効率化やDX(デジタルトランスフォーメーション)を支える存在となっています。
しかしその一方で、機能やUIが類似した競合が多く、ユーザーから見れば「どれも似たようなサービス」に見えてしまうのが現実です。特に中小企業の経営層や現場担当者にとっては、専門用語が多く、違いを正しく比較すること自体が難しい場合もあります。
そのため、「課題をどう解決できるか」という視点でコンテンツを設計し、SaaSの提供価値を“自分ごと”として認識してもらうことが非常に重要なのです。
課題起点型コンテンツとは何か?
課題起点型コンテンツとは、ユーザーが抱えている悩みや業務上の課題を出発点に構成されるコンテンツです。「誰が、どんな場面で、どんなことで困っているのか」を明確に描き出し、その上で解決の手段として自社サービスを提示することで、自然で押しつけがましくない訴求が可能になります。
たとえば、SaaS型の営業支援ツールを訴求する際、「営業成績が伸び悩んでいる新人スタッフが、日報の自動化でどのように成長できたか」といった具体的なストーリーを描くことで、読者は共感しながら内容に引き込まれ、自社の課題に照らし合わせることができます。
なぜ“課題起点”が差別化に有効なのか?
1つのSaaSに複数の競合が存在する中で、見た目や機能での差別化は限界があります。そこで重要なのが、「誰のどんな課題を、どう解決するか」という本質的な価値の提示です。SaaSプロダクトの購入判断は、日常業務の中で「困っていること」が起点となることがほとんどです。たとえば、「請求書の発行ミスが多くて困っている」「営業報告が属人化していて非効率」など、現場のストレスや手間が導入のきっかけになります。
このとき、課題起点型コンテンツでは、「なぜその課題が起きているのか」「放置するとどんな問題があるのか」「どう解決できるのか」という流れを、ユーザーの目線で丁寧に描いていきます。そして、課題の解決手段のひとつとして自然にSaaSプロダクトを紹介することで、読者の納得感と共感を得やすくなるのです。
成功のポイント:ストーリーとリアルな変化
課題起点型コンテンツを効果的に運用するための具体的なポイントは以下のとおりです。
-
ターゲットを明確にする
「経理部門の月末業務」「営業チームの属人化」など、課題を細分化して、読者が自分の状況に照らしやすいテーマを設定します。 -
実在するようなストーリー構成
抽象的な表現よりも、実在の人物を想定した具体的なストーリーが読者の共感を引き出します。 -
ビフォーアフターで成果を明示
「導入前は月20時間かかっていた業務が5時間に短縮」といった具体的な数字が説得力を増します。 -
継続的な改善と活用
コンテンツは一度作って終わりではなく、定期的に更新し、ホワイトペーパーやSNS広告など他のチャネルでも展開していきます。
経営とブランディングにも波及するメリット
課題起点型のアプローチは、単なる広告や集客手法にとどまりません。「顧客の課題に真摯に向き合う企業」としての姿勢は、ブランドイメージそのものを高め、経営全体に良い影響をもたらします。
特にSaaSのような無形商材は、企業の思想やサポート体制、導入支援などの“周辺価値”が判断材料になりやすいため、課題起点型コンテンツが果たす役割は非常に大きいのです。
まとめ:プロダクトではなく“解決”を語ろう
どれほど優れたSaaSであっても、「自分には関係ない」と思われてしまえば選ばれることはありません。だからこそ、まず顧客の課題に丁寧に向き合い、「その課題、私たちが一緒に解決できますよ」という姿勢を示すことが、競合との差を生む第一歩となります。
課題起点型コンテンツは、売り込むのではなく“寄り添う”姿勢を体現し、結果としてブランドの信頼を高めていく力を持っています。これからの時代のコンテンツ戦略は、競い合うのではなく、共に悩み、共に歩むこと。そんな関係性を築ける企業こそが、顧客に選ばれ続けるのではないでしょうか。
- カテゴリ
- インターネット・Webサービス