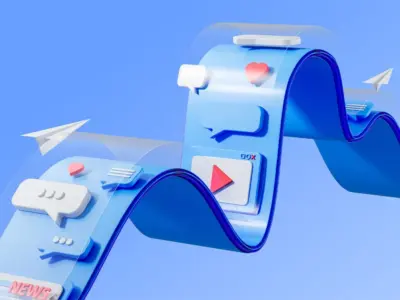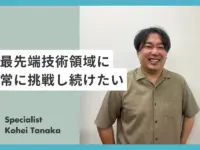クラウド大手の障害が浮き彫りにした“分散化”の逆説
安定を求めた集中が、思わぬ脆さを生む状況
インターネットを支える基盤の多くがクラウドへ移行し、日常生活のあらゆる場面でクラウドサービスが機能しています。行政手続き、オンライン決済、EC、コンテンツ配信など、さまざまなサービスが同じクラウド基盤を前提に構築され、安定した運用を実現してきました。しかし、規模が大きく信頼されているクラウド事業者でも障害が発生し、複数サービスが同時に停止する事例が報告されています。
たとえば2025年において、世界的に影響を及ぼした障害が連続し、私たちのインターネット依存構造の脆弱性が改めて露呈しました。大規模クラウドは堅牢である一方、多くのサービスが集まるほどに一点への依存が強まり、障害時には広い範囲が影響を受ける構造に変化しています。この状況は、クラウドが持つ分散の特徴と、集中によって効率を高める構造の間にある矛盾を鮮明にし、分散化の在り方を改めて考える必要性を示しています。
技術進化がもたらした集中構造と“逆説”の背景
仮想化技術やネットワークの高速化が進むにつれ、多くの企業は自社設備を減らし、クラウドへ移行していきました。総務省のデータによると、国内企業のクラウド利用率は2023年に72.4%へ達し、10年前の約2倍となっています。特に中小企業では、自社でサーバーを管理する負担を減らせることから、クラウドへの依存度が急速に高まりました。
一方、大規模クラウドが高いシェアを獲得するにつれ、インターネットは本来の分散型アーキテクチャとは異なる方向に進んでいきました。処理能力やセキュリティ、運用コストの面で大手クラウドが優位なため、企業は自然と同じプラットフォームに集まる流れが形成されています。
結果として、多くのWebサービスが同一クラウド事業者に依存し、障害発生時には複数の企業で同時に機能停止が起きる構造が生まれました。つまり、クラウドの安定性を求めて集中させた結果、その集中が新たなリスクを生み、分散化の概念と逆行する状況が形づくられています。この矛盾が、クラウド需要が増え続ける現在の課題といえるでしょう。
分散化を再構築する取り組みとリスク回避への模索
大規模障害を経験した企業の多くが、システム構成を見直しています。特定クラウドへの依存度を下げ、別環境に切り替えられる仕組みを整える取り組みが増えており、マルチクラウドやハイブリッドクラウドが選択肢として注目を集めています。複数クラウドを併用すれば、障害発生時の影響を抑えられる可能性が上がり、サービス継続性を確保しやすくなります。
ただし、この手法にも懸念があり、複数クラウドを管理するための人材や運用コストが増えやすく、中小企業では負荷が大きくなることが避けられません。データ同期やアプリケーションの互換性を保つ作業は高度であり、負担が増すほど別のトラブルを引き起こす可能性もあります。分散化が新たなリスクを生む可能性は常に伴い、単純にクラウドを増やせば解決する問題ではありません。
また、国内の物理インフラにも偏りがあり、主要なデータセンターの多くが都市部に集中しているため、大規模災害や地震によって複数施設が同時に稼働停止に陥るリスクが指摘されています。論理的な分散を進めても、基盤となる物理インフラが偏っていれば十分な安全性が確保されないことが課題として残っています。
持続的なインフラに向けた視点と未来像
クラウドの集中がもたらした逆説的な構造を踏まえると、必要なのは「分散を目的にした分散」ではなく、持続性と安全性を軸にした再設計です。国内ではデータセンターを地方へ分散させる取り組みが進みつつあり、北海道や九州など電力供給が安定し、災害リスクが比較的低い地域での施設建設が増えています。海外では国産クラウド基盤を強化する動きも活発になり、各国が自国のインフラ主権を高める戦略を示しています。
クラウド単体ではなく、エッジコンピューティングとの組み合わせも注目されています。利用者の近くでデータ処理を行う仕組みが広がれば、通信遅延が減り、障害発生時にも影響範囲を限定しやすくなる効果が期待されます。5Gネットワークによりエッジノードの構築が容易になったことで、クラウドとエッジを統合する新しい分散モデルが現実味を帯びてきました。
こうした動きは、インターネットの本来の姿である「強靱な分散ネットワーク」を再び取り戻すための一歩ともいえます。クラウドの利便性を維持しながら過度な集中を避ける取り組みは、企業規模を問わず重要性が増していくでしょう。安定したサービス提供を支えるための基盤が整っていけば、国内のインターネット環境はより安全で柔軟なものへと向かうはずです。
- カテゴリ
- インターネット・Webサービス