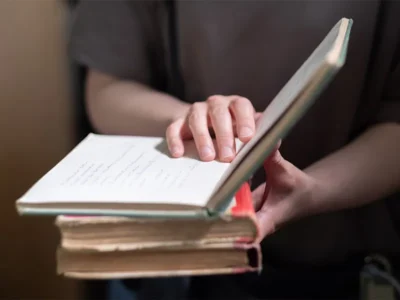知っていることより考えられること──これからの教育の軸とは?

テストで高得点を取ることが、かつては「賢さ」の証とされていました。暗記力やスピードがものを言い、答えをいかに早く導き出せるかが評価の基準になっていた時代では、それが最適な判断だったのかもしれません。しかし、社会やテクノロジーの進化によって、今や知識の価値は大きく変わろうとしています。
正解のある問いよりも、自ら問いを立て、情報を組み合わせて考え抜く力が求められる時代です。こうした変化の中で、教育の軸をどのように見直していくべきか。知識を超えて「思考」を育てる教育のあり方に目を向ける必要があります。
正解を知る力から、考え続ける力へ
学校教育ではこれまで、教科書の内容を正確に理解し、定められた形式で再現する力が重視されてきました。全国学力・学習状況調査などの結果からも、日本の子どもたちの「知識再現力」は安定して高い水準にあります。一方で、実生活に即した応用問題や、自由記述による思考表現の場面では、正答率が伸び悩んでいる傾向が見られます。
これは、答えを導き出す訓練に偏りすぎて、自らの視点で考え、理由をもって主張する力が十分に育まれていないことの表れです。情報はスマートフォンで瞬時に手に入る時代になりましたが、その情報をどう扱い、どのように活用して社会や他者と関わっていくかの力は、意識的な教育がなければ身につきにくいものです。
「思考力」「判断力」「表現力」といった言葉は、教育指導要領にも明記されていますが、それを具体的に育てる授業設計や評価体制の整備には、まだ課題が残されている状況です。
家庭の期待と、子どもの自律性のはざまで
子どもの進学や学力向上に熱心な保護者の存在は、教育現場において大きな影響力を持っています。とくに都市部では、小学校入学前からの先取り学習や中学受験への準備が一般的になりつつあります。こうした教育熱の背景には、「良い大学に入ることが安定した人生への第一歩である」という根強い価値観があります。
ただ、社会の変化に目を向けると、企業の採用活動では学歴よりも人間性や実行力、多様な価値観に対応できる柔軟性が重視される傾向が強まっています。複数の就職調査によると、学生の「思考の深さ」や「対話力」を評価軸に加える企業が年々増えており、ペーパーテストだけで測れない資質が問われる時代になりつつあります。
にもかかわらず、家庭内では依然として「知識量」や「模試の偏差値」に偏った評価がなされがちです。子どもの好奇心や創造性は、周囲の期待に応えようとする過程で置き去りにされることもあります。本来、学ぶことは自己表現であり、内面から湧き上がる興味や問いと結びついた営みです。子ども自身の思考を信じ、試行錯誤を見守る姿勢が、これからの家庭教育に求められているように思われます。
教育現場の挑戦と展望
一部の学校では、これまでの知識中心の授業を見直し、「探究的な学び」を取り入れる動きが進んでいます。たとえば、地域社会の課題をテーマに、グループで調査し、解決策を考えるプロジェクト学習は、生徒たちの思考力や協働性を引き出す手法として注目されています。ある高校では「地域の高齢者向け交通支援策を提案する」という課題に取り組み、生徒が役所に提言を提出するまでに至った事例もあります。
こうした学びでは、答えの正確さよりも、思考のプロセスや他者との対話が評価対象となります。それによって、学習者自身が「考える喜び」や「問いを深める面白さ」を実感することができ、内発的な学習意欲につながっていきます。しかし、すべての学校でこのような実践ができているわけではありません。教員の負担や評価制度の未整備、ICT環境の地域差といった構造的な課題も多く、現場では試行錯誤が続いています。それでも、こうした挑戦を積み重ねていくことが、教育全体の質を押し上げる鍵になると考えられます。
社会と接続する学びが未来を拓く
人生100年時代を見据えると、「学び」は子ども時代に完結するものではなく、生涯にわたって続くものへと広がっています。社会構造の変化にともない、働きながら新たな知識やスキルを獲得し直すことが当たり前になりつつあります。文部科学省が実施した調査によれば、社会人のうちおよそ6割が「学び直しに関心がある」と答えており、企業や自治体もリスキリングを支援する制度づくりに乗り出しています。
このような背景を踏まえたとき、学校教育が果たすべき役割は、単に知識を教えることではなく、「自分で学び続ける力」を育てることに移行していく必要があります。問いを持ち続け、自ら情報を集め、他者と意見を交わしながら思考を深めていく力。それが、どのような時代でも柔軟に生き抜いていく基盤となるのではないでしょうか。
学校だけでなく、家庭や地域、そして社会全体が「学びの場」として機能するような仕組みづくりが、これからの教育には欠かせません。個人が学び、成長していくことが、社会全体の活力につながる未来。その実現に向けた第一歩が、教育の再構築にあるように感じられます。
結びに代えて
教科書の知識をなぞるだけでは、目の前の世界に向き合う力は育ちにくいかもしれません。子どもたちが自らの問いを持ち、自分の言葉で考え、行動に移していく力こそが、これからの社会を支える原動力となります。知っていることに満足せず、問いを持ち続けること。それを支える環境を、私たち大人が丁寧につくり上げていくことが、新しい教育の姿を形づくっていくのではないでしょうか。
- カテゴリ
- 学問・教育