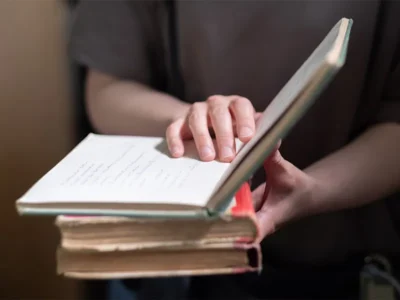“スキルよりセンス”と言われる時代の学び方

テクノロジーの進化が仕事の定義を揺らし、資格や専門知識だけでは差別化しづらい状況が広がっています。AIや自動化ツールを使えば、翻訳、画像制作、コード生成といった業務が短時間で完了し、作業の均質化が進む一方、何を目指すかを設計する力や、利用する情報を選び取る眼差しが重要性を増しています。PwCの世界CEO調査(2024年)では、経営者の約7割が「創造性と独自の発想が組織の持続的成長に寄与する」と回答しており、単なる知識量ではなく、状況を読み解き、新しい意味を生み出す力が価値を持っていることが示唆されています。
知識は不可欠ですが、それだけでは到達できない領域が確かに存在しています。問いを立て、価値を見いだす姿勢こそが、キャリアの芯を形づくる時代になっています。
センスとは“感覚”ではなく、観察と解釈の積み重ね
センスという言葉には、どこか生まれ持った印象が伴います。けれども、仕事の現場で求められるセンスは、感覚的なひらめきだけではありません。状況の背景を読み取り、情報を組み合わせ、新たな視点を提示する力に近いものです。たとえば、プロダクト開発に携わる人は、ユーザー調査の数値だけでなく、利用者の表情や行動の意味を細かく捉え、言語化していきます。飲食業界では、レシピの技術だけでなく、空間の温度や照明、音、香りまで含めた体験設計が差を生む場面が増えています。デザイン思考を取り入れた企業の株価成長率が市場平均を約2倍上回ったというデータ(DMI)もあり、センスが意思決定や価値創造に結びついている姿が見えてきます。
この能力は、日常の観察や学習の姿勢を重ねることで磨かれます。気づいた変化を放置せず、「なぜそう思ったのか」を自分に問い返し、言葉として残す習慣が、感覚を思考に変える入り口になるでしょう。
センスを育てる学び方――体系化と実践の往復
スキルは手順として覚えられますが、センスは経験と言語化の積層によって育ちます。オンライン学習プラットフォームUdemyの利用調査では、技術習得講座と並び、UX思考やビジネスモデル構築講座の受講者が2年間で約35%増加しており、知識と発想の接続を志向する学びが広がっていることが確認されています。
実践に移す際は、小さなアウトプットを重ねる形が効果的です。副業でプロジェクトに参加したり、社内で新しい提案を行ったり、オフラインコミュニティで議論に加わることで、自分の考えを試し、視点を更新できます。異なる業界や年代の人と対話する経験は、自分の常識がどこにあるかを知る手がかりにもなります。
さらに、学んだ内容を“自分の表現”として整理する過程が、理解を深める支えになります。ちょっとした疑問をメモに記録し、気になったサービスの体験を分解し、気づいた仕組みを図に起こしてみる。このような営みは、小さく見えても、発想の質を引き上げていく要因となるでしょう。
ツールが進化するほど“自分の視点”が価値になる
AIが助けてくれる場面が増えるほど、ツールの操作よりも、何を問い、どのような未来を描くかが大切になります。生成ツールは答えを示してくれますが、問いの方向性が曖昧なら、出力される情報も散漫になります。そこで必要になるのは、好奇心を起点に、自分なりの視点を育てる姿勢です。興味を持ったテーマを深掘りし、気になる企業の戦略を読み解き、街中で目にした工夫を解説してみる。こうした習慣が、判断の軸を太くしていくのでしょう。
スキルとセンスは対立しません。むしろ、技術が発達した世界では、センスが技術を活かす方向を決めます。積み重ねた知識に新しい視点を与え、状況の変化にしなやかに応じる姿勢が、これからのキャリアを支える土台になります。便利さが広がる時代だからこそ、自分の思考を丁寧に育てる時間が、未来を穏やかに切り開く力へとつながっていくはずです。
- カテゴリ
- 学問・教育