投資は大人だけのものじゃない──広がるNISA制度と全世代の資産形成
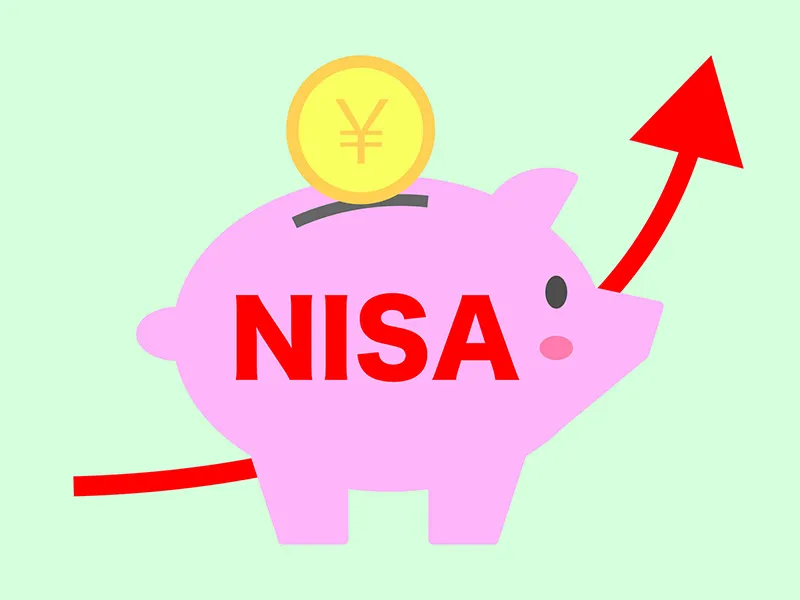
「投資は経験のある大人だけが行うもの」。かつては、そう考えるのが一般的でした。しかし2024年の制度改正を経て、NISAは年齢や経験に関係なく、誰もが参加できる仕組みへと形を変えつつあります。2025年8月時点では、未成年向けの「こども支援NISA(仮称)」や、シニア向けの「プラチナNISA(仮称)」など、年齢制限の見直しを視野に入れた新制度の設計が進んでいます。これは単に非課税枠を広げるにとどまらず、家族という単位での資産形成を促進し、金融リテラシーの世代間共有を後押しする動きでもあります。
制度の現在地:全年代が参加できるNISAへ
現在のNISA制度は、「つみたて投資枠」と「成長投資枠」の2本柱で構成されており、年間最大360万円、通算1,800万円までが非課税で投資できるようになっています。これは従来の制度と比べて大幅な自由度と柔軟性を持ち、長期・分散・積立の原則に沿った運用設計が可能となりました。
こうした枠組みをベースに、未成年と高齢者それぞれの立場に寄り添った制度拡張が検討されています。未成年を対象とする「こども支援NISA(仮称)」では、親の管理のもとでつみたて投資を行える仕組みが想定されており、年間120万円程度の非課税枠が議論されています。一方で、高齢者向けに設計されている「プラチナNISA(仮称)」は、毎月分配型の投資信託やインカムゲイン重視の資産運用を非課税で支援する制度として構想されており、引退後の生活資金の補完を視野に入れています。
このように、制度の変化は「全年齢にとっての投資の入り口」を整備する方向へと動いており、それぞれの世代が自分のタイミングで金融と向き合える環境が整いつつあります。
家族で資産形成と向き合う時代へ
投資を始めるにあたり、資金の大小よりも大切なのは、正しい知識と「続ける姿勢」です。たとえば高校生が月1万円ずつ、年利4%で18年間つみたてを行えば、総額は約260万円に達します。これは、ただ貯金するだけでは得られない価値の積み重ねです。
また、退職後の生活を迎えたシニア世代にとっても、資産をゆるやかに運用しながら毎月の生活費を補える仕組みとして、NISAは有力な選択肢となります。生活費を取り崩すだけでなく、配当や運用益を得ながら「資産を活かす」という発想が、老後に安心感をもたらす手段として注目されています。
こうした投資の考え方を家庭の中で共有することで、世代間の金融リテラシーの差も徐々に埋まっていきます。親が証券口座の仕組みを子どもに説明し、祖父母が自らの投資経験を語る——そんな家庭内の会話が、知識や考え方を自然に受け継いでいく土壌になります。
金融リテラシーを育てる社会的な土壌も整備中
金融リテラシーの向上を制度と並行して進める取り組みも進化しています。文部科学省は、2022年度から高校家庭科に「資産形成」の授業を本格的に導入し、金融庁も年代別の教材や解説動画の配信に取り組んでいます。これにより、これまで「知らなかったから始められなかった」という障壁が、少しずつ取り払われつつあります。
ただし、情報過多の時代においては、誤った知識や極端な投資手法がSNSなどを通じて拡散されやすく、正しい情報の選別が難しくなっています。特に、投資経験の浅い若年層や、運用に不安を抱える高齢者にとっては、制度のわかりやすさと同じくらい、信頼できる情報源の存在が重要です。地域でのセミナー、FP相談、対面による説明機会の拡充など、制度と教育が並走する環境の整備が、今後ますます求められます。
投資が当たり前になる未来へ
NISAの年齢制限緩和は、投資という行為を一部の層に限定された専門的行動から、生活の中にある選択肢のひとつへと押し上げる契機になります。少額からでも時間を味方につけて資産を育てる未成年、安定収入を求めて配当型商品を活用する高齢者、そしてライフイベントを見据え中長期で資産運用する現役世代。それぞれの目的に応じた投資行動が認められることで、金融に対する心理的なハードルは確実に下がっていきます。
そしてその変化は、家庭や地域といった私的な空間にも波及します。親子で資産の話題を交わすこと、祖父母が若い世代に体験談を語ること、教育現場で「お金の使い方」を学ぶこと。こうした営みの積み重ねが、個人の資産形成を支えると同時に、社会全体の経済的な安定や自律性にもつながっていくのではないでしょうか。
まとめ
NISA制度は、単なる税制優遇制度にとどまらず、人生のあらゆるフェーズに対応できる資産形成の基盤へと進化しつつあります。こども支援NISAやプラチナNISAといった構想は、未成年から高齢者までのすべての人に投資の選択肢を与えるものであり、それぞれの世代が自分に合ったかたちで金融と関わるための制度的土台となります。
投資が「特別なスキルを持つ一部の人」だけのものではなく、家庭内で語られ、実践され、学ばれていく対象になったとき、金融リテラシーの裾野は確実に広がります。そしてその先には、誰もが自分らしくお金と向き合える、より柔軟で持続可能な社会が見えてくるはずです。
- カテゴリ
- マネー



























