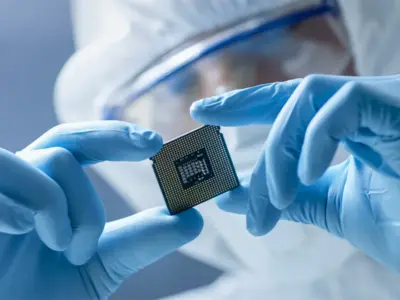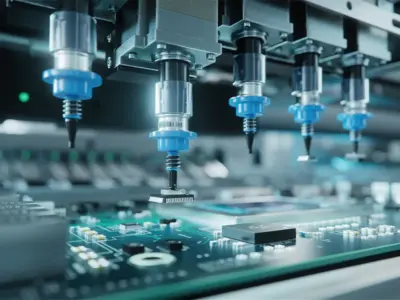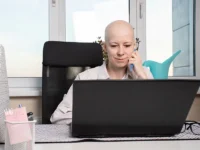宇宙デブリ除去のビジネス化、地球軌道が“廃棄物管理”対象に?
宇宙も「持続可能性」が問われる時代へ
地球のまわりを漂う“宇宙デブリ”とは、役目を終えた人工衛星やロケットの残骸、破片、ネジのような小片までも含む人工物の総称です。自然発生したものではなく、人類の宇宙活動によって残された「使われなくなったモノ」が軌道上に残っている状態と言えます。
欧州宇宙機関(ESA)の統計では、10センチ以上の物体が約4万個、1ミリ〜1センチの微細な物体は10億個以上あると推計されています。これらは秒速7〜8キロメートルという弾丸をはるかに超える速度で飛行しており、衛星や宇宙ステーションに衝突すれば重大損傷につながります。安全な軌道利用が難しくなると、通信・気象観測・災害監視といった地上インフラにも影響を及ぼすため、宇宙空間の“持続可能性”はすでに地球社会の課題になりつつあります。
この状況を踏まえ、軌道環境を保全しながら衛星運用を続ける取り組みが重要視され、宇宙デブリ除去が新しい産業領域として注目を浴びています。
宇宙デブリ除去がビジネスとして成り立つ理由
宇宙開発はこれまで政府主導の分野でしたが、通信衛星コンステレーション事業の拡大やロケット再使用技術の進展によって民間参入が加速しました。2023年だけで世界の衛星打ち上げ数は2,300機を超え、2030年には年間数千機規模になると予測されています。この流れの中で、衝突リスクを低減し、軌道を“安全に使い続ける”仕組みは不可欠です。
JAXAの公表資料によると、衛星運用時に年間数回の衝突回避機動を行う例が確認され、運用コストや燃料消費、ミッション効率の低下につながっています。こうした背景から、「衝突回避やデブリ撤去に投資する方が長期的には合理的」という判断が民間企業で進み、需要が生まれています。
実際、2024年には日本のAstroscaleがJAXAと約120億円規模の契約を締結し、ロケット上段の除去ミッションを受注しました。政府案件のみならず、海外衛星事業者との契約も視野に入っており、サービス事業として収益性が現れつつあります。投資面でも、国際的な宇宙基金やベンチャーキャピタルが宇宙環境保全領域への出資を進めており、市場形成が進展しています。
デブリ除去技術の現状と多様化するアプローチ
実現方法は複数あり、対象に応じて使い分けられています。ロボットアームで破片を掴んで大気圏に再突入させる技術、大型物体を専用衛星で牽引する方法、地上レーザーなどを用いて微小な推力を与え軌道を調整する方法などが研究・実証段階から商用化に進みつつあります。
欧州ではClearSpace計画が進み、2020年代後半には実機回収を目指す予定です。日本でも、衛星寿命管理や軌道上サービスと組み合わせた「総合宇宙運用サービス」が構想され、機体再利用技術や補給システムと併せて、宇宙空間における経済圏が形成される可能性があります。ただし、対象物が高速回転していたり、形状が複雑だったりする場合、捕捉には精密な制御とセンサ技術が求められます。その意味で、除去技術は宇宙ロボティクスと航法システムの最先端領域といえる状況です。
国際ルール整備と市場の将来性
宇宙空間はどの国の領土でもないため、所有権や責任の所在が複雑です。国連や各国機関でルール整備が議論され、打ち上げ後の衛星処理義務や軌道利用のガイドラインが少しずつ形になりつつあります。デブリ除去が「公共性の高い有償サービス」として認識されれば、保険制度や国際的な運用協定が整備され、市場の安定にもつながります。民間スタートアップと国家機関の連携が進むなかで、宇宙環境管理は航空交通管理のように、国際協調の枠組みを持つ可能性があります。
将来を見据えると、日本は軌道デブリ対策技術や衛星運用技術に強みを持ち、アジア地域の宇宙安全保障や民間事業支援でもリーダーシップを発揮できる立場です。宇宙環境を守る技術と仕組みを磨くことは、地球規模の課題解決と産業育成の両立につながります。
まとめ:地球を守る視線は、いま空のさらに外側へ
私たちはこれまで、地球上の環境保全を中心に取り組んできました。しかし、社会の基盤として宇宙が重要になった現在、地球軌道も“守る対象”に含まれています。デブリを減らし、衛星が安全に活動できる空間を維持することは、通信・物流・災害対策といった日常生活の安心とも直結します。
宇宙は無限の空間ではなく、人類が共有する資産です。次の世代にも安全に利用できるよう、技術開発やルール整備、そして持続可能なビジネスの形を築くことが求められています。宇宙を守る取り組みが、地球と未来の社会を守る基盤になるという視点が、これからの宇宙経済に欠かせない視座になりそうです。
- カテゴリ
- [技術者向] 製造業・ものづくり