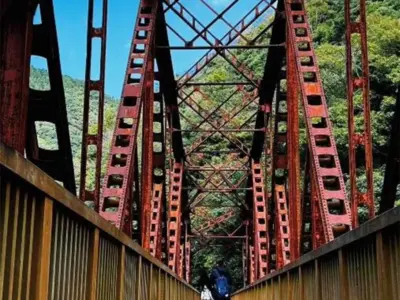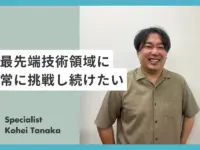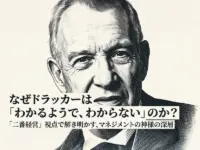親子二人三脚で描く“光と影の芸術”「永井克明・豊人ステンドグラス二人展」開催【福島県須賀川市】
希少なヴィンテージガラスと現代ガラスを融合させ、光と影で空間を満たす──。そんな芸術作品に出会える展示会が今月初め、福島県須賀川市のギャラリーマスガで開催された。出品したのは、ステンドグラス作家の永井克明さん・豊人さん(神奈川県相模原市)。作品に使っている素材は、世界でも入手困難なヴィンテージガラスだ。親子の感性が響き合う約100点の作品が放つ光が、ギャラリーの空間をやわらかく照らし出した。須賀川で紡がれたそのストーリーをたどってみたい。
想像を超えるステンドグラスの可能性
会場に足を踏み入れてまず驚いたのは、「重い」「壊れやすい」「冷たい」という一般的なガラスのネガティブな固定観念が消えていったことだ。目の前にある作品は、優しい色調と流れるような曲線、そして大胆な構成で生き生きとした表情を見せる、いわゆる“ガラス細工”の枠を超えた表現の数々だ。父・永井克明さんは、1970年代に渡米し、ステンドグラスの制作方法を本格的に勉強。その後、その腕が買われ、サンフランシスコのステンドグラスの会社にスカウトされ就職。世界的作家ピーター・モリカとの交流をはじめ、45年前に現地でしか手に入らないイギリスやドイツ製のヴィンテージ素材と出会った。入手困難な貴重な手吹きガラスと現代ガラスと組み合わせるフュージングという技法によって、独自の色彩とテクスチャーを生み出している。とりわけ印象的だったのは、複数のガラスを融合させて描いた抽象模様のランプ作品。見る角度によって色が変化し、まるでガラスが“呼吸”しているかのようだった。光が透けることで、ひとつの作品が複数の表情を持つ。
光が描く“もうひとつの作品”
展示の主役はガラス作品そのものだけではない。そこからあふれる光、そして生まれる影までもが“もうひとつの作品”として空間を彩っていた。ギャラリーの壁に広がる影は、まるでステンドグラスの魂の反射。ときに幻想的に、ときに静謐(せいひつ)にその影は作品と呼応しながらガラスの静かな声を可視化したかのよう。
ライトアップされた作品の一つは、光の揺らぎに合わせて空気まで振動するようで、時の流れを視覚化したような深い静けさを感じた。ギャラリーオーナーの増賀 睦朗さんが語った「影も作品として見てほしい」という言葉の意味が、展示を通じて心の底にじんわりと染み込んでいく。ステンドグラスが“光の芸術”であることを再認識させられた。
親子二人三脚、技と心の継承
永井さん親子が制作した作品をギャラリーマスガで展示するのは今回で3回目だ。父・克明さんの作品には、数十年にわたり磨き続けた技と審美眼、そして素材への深い愛情がにじむ。一方で、息子の豊人さんは、父の作品に憧れて創作を始め、植物をモチーフにしたオブジェやランプなど、瑞々しい感性で空間に彩りを添えていた。小さなガラス玉を組み合わせた作品からは、次代を担う作家としての新しい息吹と、父への深い敬意が感じられる。すべてが一点物の魅力。だからこそ、作品を前にしたときの“出会い”の重みと尊さが心に残る。
光と共に、暮らしに寄り添うアート
ステンドグラスと聞くと教会の荘厳な雰囲気を思い起こすことが多いが、今やその美は家庭の中にも溶け込みつつあるという。増賀 睦朗さんは「貴重な素材と永井さんの卓越した技術によって生み出される作品は秀逸。日本の住宅事情が大きく変化するなかで、ステンドグラスは床の間や掛け軸に代わる新たな“静の美”として、空間にうるおいと気品を与えてくれる」と穏やかな口調で熱く話した。日本の住環境も変化する中で、ステンドグラスの表現力、高い質を保ちながら、現代の建築のニーズに適応できるかどうかが環境と作品の調和を左右する。この展示会は光と影の共演、素材の希少性、そして親子の物語─五感を通して感じる体験型アートだ。
ステンドグラスの魅力は光を通して初めて完成する。作品にあたる光の強さ、角度、見る人の気分によって、まったく異なる表情を見せてくれる。つまり“変わり続けるアート”なのだ。ぜひこの光の芸術を、もっと多くの人に知ってほしい。
情報提供元:ローカリティ!
その魅力を共に愛する仲間を募れる住民参加型・双方向の新しいニュースメディアを目指しています。
- カテゴリ
- [地域情報] 旅行・レジャー