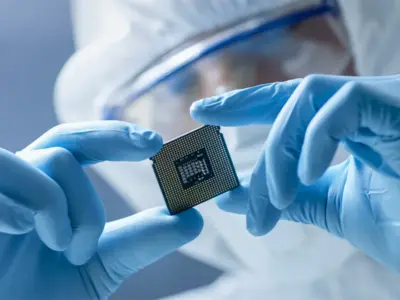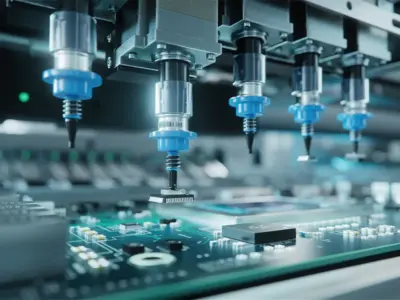急増する冷凍惣菜ニーズに応える製造業の挑戦とは

忙しい現代人の味方として、冷凍惣菜の需要が年々高まりを見せています。
共働き世帯や単身者、高齢者の増加といった社会背景に加え、「手軽なのにおいしい」「保存が利く」「選べる楽しさがある」といった利便性が消費者の心を掴み、多様なニーズを持つ層に支持されています。実際、2022年度の国内冷凍食品市場は前年比6.2%増の7,200億円を超え、特に惣菜カテゴリーは前年比で12%以上の成長率を記録しました(日本冷凍食品協会調べ)。
この急成長に対応するため、製造現場では従来の「大量生産・低コスト」志向から、「多品種少量・高付加価値」型へのシフトが急務となっています。
多様なニーズに応えるには、柔軟な製造体制が不可欠
冷凍惣菜の需要増加にともない、商品ラインナップの多様化が進んでいます。健康志向の高まりを受けたカロリーオフ惣菜や、アレルゲン対応商品、地域食材を活用したご当地メニューなど、ニーズはますます細分化しています。とある大手食品メーカーでは、1ヶ月に製造する冷凍惣菜の品目数が2018年には平均45品目だったのに対し、2024年には実に70品目以上にまで増加しています。
こうした多品種少量生産への対応には、製造ラインの柔軟性が求められます。異なる原材料や味付け、加熱条件に対応しながら、生産効率を落とさずに商品を切り替えていくには、従来の「1ライン=1製品」という考え方では対応しきれません。
技術者が工夫する“段取り替え”と“最適スケジューリング”
多品種少量生産において最大の課題のひとつが、「段取り替え」の時間と手間です。製造ラインで異なる商品を切り替えるたびに、原料タンクや充填ノズルの洗浄、機械設定の変更が必要となり、生産停止時間が発生します。たとえば一般的な冷凍惣菜工場では、商品1品目あたりの切替に20~30分を要する場合もあります。これが1日に10回以上発生すれば、大きなロスにつながります。
この課題に対し、現場の技術者たちは「クイックチェンジ」対応設備の導入や、洗浄作業の自動化、部品のモジュール化などの工夫を進めています。ある中堅メーカーでは、着脱式ノズルと自動洗浄機能を活用し、切替時間を平均30分から10分未満へと短縮。これにより月間生産量が約15%増加したという成果も報告されています。
さらに、生産スケジュールの最適化も重要な要素です。AIやIoTを活用した生産計画支援システムでは、販売実績や在庫状況、原材料の納品日などを加味してリアルタイムで生産順を最適化することが可能となっています。
品質管理の高度化が信頼を支える鍵
多品種少量生産では、各製品の特性に応じて工程管理を細かく変える必要があります。たとえば和風煮物と洋風グラタンでは、加熱温度や冷却スピード、保存方法が大きく異なります。こうした違いをすべての工程で厳密に管理しなければ、品質ばらつきや商品クレームのリスクが高まります。
そのため、冷凍惣菜製造においては「トレーサビリティ」と「数値化された品質保証」が欠かせません。最新の現場では、IoTセンサーを用いた温度モニタリングや、AIカメラによる見た目の合否判定などが導入されており、作業員の熟練度に依存しない安定した品質確保が可能となりました。
とくに注目されているのが、冷凍前の食材状態を画像解析で確認するAI技術です。例えば煮物では、「煮崩れ」や「色ムラ」などが味だけでなく見た目の印象にも影響するため、外観品質の自動チェック機能が非常に有効となっています。
デジタル技術との融合が未来の鍵を握る
こうした現場改革を支えているのが、デジタル技術との融合です。クラウドベースの生産管理システムを導入することで、製造現場・販売現場・物流拠点をリアルタイムでつなぎ、需要の変動に柔軟かつ迅速に対応できる体制が整いつつあります。例えば、店舗POSデータと生産指示が連動すれば、売れ筋商品の増産や不良在庫の削減が即座に行えるようになります。また、サプライチェーン全体の在庫可視化によって、余剰在庫や欠品リスクを大幅に軽減することも可能です。
将来的には、個人の嗜好や健康データをもとにしたパーソナライズ惣菜の製造なども現実味を帯びてきており、多品種少量生産が“当たり前”の時代は、すぐそこまで来ているといえるでしょう。
まとめ:多品種少量生産の工夫が、食の未来を支える
冷凍惣菜市場の成長は、単なる食の利便性の進化にとどまりません。そこには、製造業の現場で日々試行錯誤を重ねる技術者たちの知恵と工夫が詰まっています。段取り替えの効率化、品質管理の高度化、そしてデジタル技術との連携。これらすべてが結びつくことで、多様なライフスタイルや嗜好に応える製品が安定的に届けられています。
今後さらに進化する冷凍惣菜の世界では、「少量で多様なニーズに応える」ものづくりが、食の豊かさと安心を支える基盤となっていくでしょう。
- カテゴリ
- [技術者向] 製造業・ものづくり